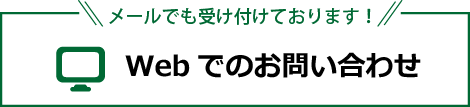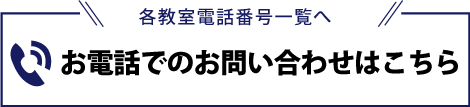教壇から見える風景
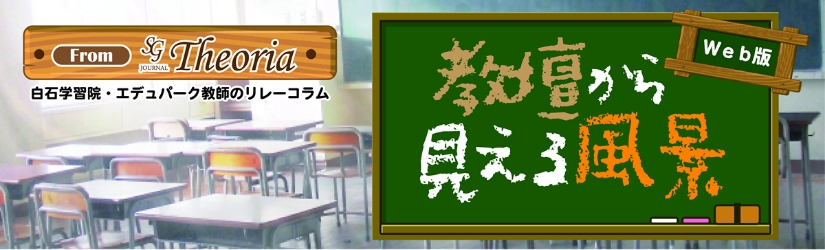
教壇から見える風景 Vol.3
みなさん、こんにちは。夏期講座も終わり、受験生のみなさんは大事な受験まで、残り数か月となりましたね。受験までの残りの期間の過ごし方や勉強に仕方についてお話ししてみたいと思います。
① 毎日勉強しよう。そのためには規則正しい生活を心がけよう!
これからの残りの時間をどれだけ勉強に時間を費やせるかということが大切になります。部活や習い事に充てていた時間を、どれだけ勉強にまわせるか、それが大切になります。そのためには、不規則な時間に起きたり、または寝たりするといったようなことをしていると、生活のリズムが崩れてしまいます。そうなると、いざ、勉強するぞ、となったときに、なかなか勉強に集中できなくなります。そのためにも、規則正しい生活を心がけるようにしましょう。
② 苦手な科目を克服しよう!
受験では、得意な科目の得点力は大切ですが、それと同じくらい苦手な科目でいかに失点を防ぐかということも同じくらい大切です。自分が苦手な科目を苦手なままにしておくと、受験の時に後悔することになります。苦手な科目はそのままにせず、勉強して、少しでも弱点をなくしていきましょう。
③ 先生にたくさん質問しよう!
上記の②の苦手科目の克服ですが、自分だけではなかなか難しいです。しかし、みなさんには塾の先生たちがついています。自分の苦手な科目の克服のために先生たちをうまく使ってほしいと思います。たくさん質問してください。白石学習院の先生たちは、みなさんの質問に親身になって答えてくれます。ただし、みなさんが質問するためには、みなさんがたくさん勉強することが必要です。そのことは忘れないようにしてください。
以上のことは、何の変哲のない、当たり前のことです。しかし、当たり前のことを「こつこつ」とやることが大切なのです。受験生のみなさん、最後までしっかりがんばってください。
(国泰寺教室 Y・T)
教壇から見える風景 Vol.2
みなさんこんにちは。
私は子供の頃から読書が好きで、漫画、小説、辞典、図鑑などジャンルや形式にこだわらず、多くの本を読んできました。今ではインターネットで気になる書籍を見つけたり、友人のお勧めの本があったりすると、すぐに電子図書で購入してしまいます。本の世界においてもデジタル化が目覚ましい今、紙の本の存在感は薄れつつあるようです。スマートフォンひとつで、いつでも多くの本に接することができる、本当に便利な時代になってしまいました。
紙の本の良さのひとつは、読んでいて心に響いたフレーズにマーカーを引いたり、出てきた言葉の意味を調べて余白に書き込んだりすることで、内容がより深く理解できたり印象に残ったりすることです。他にも、大事なページに付箋を貼るなどアレンジは無限です。本棚の整理中に昔の本に手がのびて、つい読みふけってしまったという経験もめずらしくありません。思い出のアルバムを馳せる。紙の本は古くなると、自分を振り返るためのアイテムにもなるんですね。本屋に行くことは「今の自分」を知ることにもなります。自分が手に取った本=自分が興味のあることなので、「どんな本に手がのびることが多いか」が自分を分析するための材料になるのです。とにかく文章が好きで色々と考えながら読んでいることが多かった、と思います。
また、語彙力がついてくると表現できることがらが増えていくので、会話をしたり、文章を書いたりすることがとっても楽しくなってきます。そうすると更にいろいろな言葉や漢字が知りたくなっていき、いいリズムが生まれます。知らない言葉がでてきたから、知りたい。知りたいことに関していろいろな数字が出てきたから、その使い方を知りたい。自分で読書を通じて課題を見つけ、そのことに対して興味を持ってほしいと思います。
(高校部 M・Y)
教壇から見える風景 Vol.1
私が主に担当している「算数パズル教室」では、今年度から新しい取り組みを始めました。
その名も「ヒアリングトライアル」。
講師が読み上げる問題をよく聞いて、メモや図はかかず、頭の中だけで答えを導き出して答える、という形式が特徴です。
最近のテレビ番組や動画サイトの投稿を見ていると「視覚優位」の傾向にありますよね。
出演者やインタビューを受けている人の発言を、テロップにまとめて表示して、分かりやすくしたりおもしろおかしくしたりしています。
視聴者側からすると、要点をつかみやすいという利点があるため、テロップが表示されるとつい視線がそこへ行ってしまいます。
でもその間に「聞く」ことがおろそかになってしまい、発言者がどのような言葉を選んで話していたかを聞き逃してしまうことがあります。
発言とテロップを比較しながら見ていると、「今の発言をそんなふうにまとめるのか」とか、「このテロップだと、発言とちょっとニュアンスが違うかも」と気づくことがありますが、テロップだけに集中していると、それに気づかないままになってしまうことも多いでしょう。
さて、「ヒアリングトライアル」に取り組み始めた子どもたち、結果はどうかというと、今のところ正解できる子は全体の4割程度、あとの子は間違えたり答えを書けなかったりという状態です。
ただ2回、3回と回を重ねるごとに、「聞き方」が変わってきているなと感じます。
耳を傾けて「一応聞いている」という状態から少しずつ「聞きながら考えている」のだな、という変化が子どもたちの様子から感じ取れるのです。
「聞き流す」「聞き逃す」ことなく、「しっかり聞きながら考える」ことができるようになると、学校や塾の授業から学び取れる量は、格段に増えると思います。みなさんもこれから、「しっかり聞く」ことにも意識を向けて、授業を受けてみてください。きっと新しい発見がありますよ!
(エデュパーク広島駅前本校 K・Y)