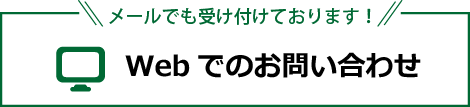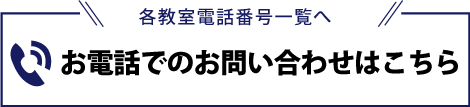愛情レシピ
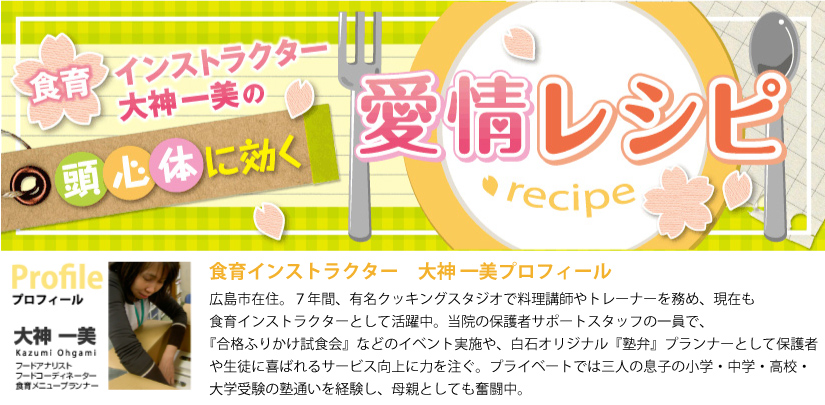
頭&カラダにいい基本のレシピ総集編!
受験生のお子様のための“頭&カラダのためになるレシピ提案”のコラムを書き続けて14年間!膨大な量のコラムとレシピになっていることに驚いています。
この度の年度末で一度コラムを見直しし、次期につなげていくために、【総集編】の見直し回とすることにしました。
そこで、今までお伝えをしてきました受験生のお子様のための“頭&カラダにいい基本のレシピ”を厳選して、BEST5!でお届けいたします。
Ⅰしっかり朝ごはんを食べないとエネルギー不足になり、元気に1日をスタートできません。朝ごはんが大切なことは常々お伝えし、朝早くから朝ごはんが食べづらい状態のお子様でも大丈夫!とオススメしてきた【具だくさんのお味噌汁】がこのコラムの基本でした。喉越しもよく、温かい汁物なのでカラダも元気に、そして具だくさんなので、一品で栄養もバッチリ!そして、何より朝食を作るお母様にも心優しいメニューとして紹介しました。

Ⅱ「“鮭”は受験生の強~い味方!」といことで、おいしさとともに、見逃せないのが“鮭”の成分!体づくりや脳の活性化、抗酸化作用といった、頭にもカラダにも良い栄養素がいっぱいの“鮭”には、DHA&EPAだけでなく、脳により多くの酸素を供給する働きがあってその結果、以前に覚えたことを脳に留めたまま、さらに新しい情報を覚える力がふんだんに発揮される「オメガ3脂肪酸」が豊富に備わっている、ということで“鮭”を使ったたくさんのレシピを紹介してきました。例えば、【鮭の幽庵焼きや更紗焼き】【鮭のホイル焼き】【鮭の炊き込みご飯】等々、中でも実は簡単に作れる【シャケフレーク】はご好評をいただきました!

【手作り☆鮭フレーク】
・鮭の切り身(甘塩OK!) 2切れ
・酒・みりん 各大さじ3
・塩 小さじ1/2~
・ごま油 大さじ1/2~1
①フライパンに、鮭と、酒・みりんを入れて、
中火で3~4分程度煮る。
②塩を加え、木べらで鮭を崩しながら、水分を飛ばしていく。(この時、骨も取り出す。)
③鮭に火が通り、ある程度水分が飛んだら、ごま油を加え、1~2分位煮絡めたらできあがり!~味見をしながら、塩分の調節をしてください。
★簡単~♪です。★
Ⅲ『塾デリカ』でも人気のドライカレー。
カレーはお子様が大好きだからだけではなく、カレー粉に使われる複数のスパイスには、ビタミンや鉄分、食物繊維などの成分が含まれているため、健康増進の効果があることを紹介しました。今では『塾デリカ』でも定番となっている【ドライカレー】のレシピをとりわけご紹介します!

【噂の!★ドライカレー】 4人分
・合挽ミンチ 200g
・玉ねぎ・人参 各200g(みじん切り)
・なす Ⅰ/2本 (みじん切り)
・パプリカ赤・黄 各1/4個(みじん切り)
・生姜・ニンニク 各1片(みじん切り)
・カットトマト缶 200g~1缶
・塩こしょう 少々
・ケチャップ 50cc(Ⅰ/4カップ)
・コスモカレー(中辛) 70g(約Ⅰ/2袋)
①フライパンに油をひき、生姜・ニンニクを炒めて、香りが出てきたら、ミンチとみじん切りにした野菜を入れて、塩こしょうをして炒める。(しんなりするまで、炒めます)
②①にカットトマト缶、ケチャップ、コスモカレーを入れて、後は煮込むだけ!
*普通のカレールーでもOK!2~3かけを細かく砕いて、使います。この場合は、煮込む時に、適量の水分(約30~50cc)を入れて、お好みの味に調整してください。そうすることで、焦げずに美味しくできますよ。
*トッピングに、野菜の素揚げや目玉焼き、アーモンドスライスやビーンズ、パセリなどをセレクトすれば、さらに栄養価がアップします!
Ⅳ私の原点でもある“体にやさしくて、頑張るお子様たちを応援する食べ物(!?)”として考えた【合格ひじき】。‘ひじきのウエットタイプのふりかけ’です。~大宰府の“梅の実ひじき”を意識して考えたものです。
薄味に煮た‘ひじき’に、カリカリ梅をはじめ五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて各々で作るふりかけです。五色の食材とは、「赤・白・黄・緑・黒」色の食材の見た目で判断することで、不思議と必要な栄養素がほぼバランスよく摂れるというもので、塾デリカやお弁当作り、日々の食事作りにも率先して取り入れて来たひとつの方法です。この五色を取り入れて作る【合格ひじき】です。

【手作り★合格ひじき】
・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で約100g
・だし汁 120~150cc (水 120cc+だしの素 小さじ1)
・醤油 大さじ2
・砂糖 大さじ1
・みりん 大さじ3
・昆布茶 小さじ2~3
(*隠し味になります!)
◎トッピング
・カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老・柚子の皮(細かく千切り)・白胡麻
・たらの実・ちりめん・かつお節(細かめ)・あおさ海苔・きざみのり等
①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水でひじきを戻します。(約10分位~)約8~9倍に増量しますよ!
②戻したひじきの水分をザルでしっかりと切って、だし汁と調味料をすべて合わせたもので煮る。汁気がなくなるまで、混ぜながら煮たら、【合格ひじき】の素のできあがり!
★少し乾煎りするように、しっかり水分をとばすことがポイントです!
③お好みのトッピングを適量、混ぜ入れて、お手製の合格ひじきふりかけのできあがりです。
Ⅴチョコレートには、驚くべき健康効果がたくさんあります。はるか昔、チョコレートは薬として重宝されていたのだとか!
実はチョコレートに含まれるカカオ成分には、カルシウム、鉄分、マグネシウム、亜鉛などのミネラルがバランスよく含まれていて健康効果も然ることながら、チョコレートの甘い香りには、集中力や記憶力を高める効果や神経を鎮静させる作用やリラックス効果が豊富に含まれる食べ物なのです。~やっぱり、受験生のお子様にも持って来い!だと思いますので、お勉強の合間にお口にポン!の【ロックチョコ】をBEST5の中に入れました。
そして、2月14日は“バレンタイデー”なので、頑張る皆様へのプレゼントの意味も込めました♪

【ロックチョコ】
・お好みのシリアル 適量
・マシュマロ お好みで
・チョコレート 100g(板チョコの場合2枚)
・牛乳 50ml~(様子を見ながら入れてみて!)
①マシュマロは小さめに切って、シリアルに混ぜ合わせておく。
②ボウルにチョコレートを割り入れて、沸騰直前の湯せんかけて溶かしていく。★グラグラと沸騰した湯せんでは、チョコレートに水分が入り、失敗の原因になります!
③チョコレートがある程度溶けたところに、人肌に温めた牛乳を混ぜ入れてさらによく溶かす。(①を入れた時のまとまり感で様子を見ます。)
④③に①を混ぜ入れて、スプーンなどを使ってお好みの大きさの塊にして、バットに乗せて冷やし固める。お好みでココアパウダーや粉糖を振って完成です!
まだまだ、ご紹介しきれないコラム&レシピがいっぱいで、迷いに迷ったBRST5でした。
14年間たくさん学んで考えて、アレンジしてきた多々のレシピは、これからの【塾デリカ】で活用され、登場していきます。
たちまちは、スタミナアップできる【肉巻きおむすび】が登場の可能性~~~。お楽しみに♪
長い間、コラムをご覧いただきましてありがとうございました!
白石学習院 食育インストクター
大神一美
【炊き込みご飯】で元気モリモリ!
寒い時期ですが、カラダも心も温かくなり、ほっこりする【炊き込みご飯】が美味しく感じられて食べたくなりませんか。
旬の食材があれこれ使え、醤油の香ばしい風味と出汁がしっかり浸みたお米で、おかわりが止まらなくなる味の【炊き込みご飯】が私は大好きです。
今回は、そんな【炊き込みご飯】をテーマに、健康に効果的だと思われる具についてお話してみたいと思います。
Q:【炊き込みご飯】で、最も美味しいと思う「具」を選んでください。
第1位:ゴボウ
第2位:鶏肉
第3位:油揚げ
第4位:きのこ
第5位:にんじん
管理栄養士さん、栄養士さんに行ったアンケート結果の【炊き込みご飯】編というのを、最近目にした順位です。
【炊き込みご飯】におすすめの「具」、第1位のゴボウは、まさに11月~2月頃の今が旬。老廃物を排出する作用がある水溶性食物繊維をたっぷりと含み、抗酸化作用もある優秀食材です。第4位のきのこと+ゴボウの組み合わせは、最も美味しいと思われる「具」の組み合わせでも選ばれています。美味しいだけでなく、不足しがちな食物繊維が更にたくさん取れるので、特にオススメです。ビタミンやミネラルが豊富になって、副菜のプラスαとして、バッチリです。
第2位の鶏肉は、ヘルシー食材だけでなく、“鶏ムネ肉”を使うと、受験生にとっても持って来い!の、持久力効果がアップします。
第3位の油揚げは、大豆の持つ栄養効果に期待が持てますし、旨味もアップ!(ただし、脂質が多いので、油抜きは忘れずに)
第5位のにんじんも、カロテンが豊富で、【炊き込みご飯】には欠かせない食材です。
そこで今回は、このアンケート結果を基に1位~5位の食材をすべて入れて元気になれそうな元気モリモリの【基本の炊き込みご飯】を作ってみました。

【基本の炊き込みご飯】 2~3人分
・米 2合
・水 2合分
・和風だしの素 小さじ2
・醤油、酒、みりん 各大さじ2
・鶏肉、油揚げ、人参、ごぼう、しいたけ&しめじ 各20~30g程度
①米を研ぐ。
②具材をカットする。熱が入りやすいように全てを小さめに切る。(火通りの悪いごぼうはささがきにしておく)~ごぼうに合わせて、鶏肉以外は千切りにすると味のしみ込み方も統一されますよ!
③炊飯器に、①と醤油、酒、みりんを入れ、だし汁(水+だしの素)を炊飯器の2合の目盛まで加えてサッと混ぜ合わせる。
④②の具材を上に乗せて、スイッチON!
*ポイント:ここで具材を混ぜ合わせてしまうと、熱の入り方にムラが出てしまい、米に芯ができてしまうので注意!~具材はお米の上に置いておきます。
⑤炊き上がったら、全体をサックリと混ぜて、数分蒸らして味を馴染ませる。
「だしの素:醤油:酒:みりん=2:3:3:3」は、【炊き込みご飯】の味付けの黄金比と言われています。お好みの食材を入れて、簡単に美味しくてお好みの【炊き込みご飯】ができあがること間違いなし!です。忙しい時には、おかずいらずで、食べ応えはたっぷりですし、メイン料理として、肉や魚のおかずがある場合、【炊き込みご飯】の具を野菜やきのこ類を中心にしてみることで、献立全体を見た時の栄養バランスが整います。
大切な栄養バランスが整えば、健康印の元気なカラダで、毎日過ごせるはずです♪
受験生応援★【ココア】!
受験真っ只中で頑張っている受験生のみなさ~ん、カラダを温めたり、ほんの少しのほっこり気分で気分転換するならば、【ココア】がベストなんですよ。
【ココア】はカラダによいと言われているのをご存じですか?!
毎日飲むなら、絶対【ココア】なんです。
カラダに良いと言っても何がいいのかな(!?)
まずは、【ココア】って何からできているのか(!?)ということで、ピュアココアの成分を調べてみたところ、<ビタミンB・カルシウム・食物繊維・鉄・エネルギー・ナトリウム・カリウム>さらに亜鉛・マグネシウム・カフェイン・ポリフェノール等、カラダに良さそうな栄養分として見覚えのあるものがたくさん含まれていました。
受験生には、特に積極的に摂取してもらいたいものがたくさん書いてありました!
また、そんな【ココア】の健康効果も調べてみたところ~、
①リラックス効果:【ココア】に含まれる香り成分と体を温める働き等で深くリラックスできます。ストレスも和らげてくれますよ!
②冷え改善効果:【ココア】には生姜よりも冷えを改善する効果があるとされています。体を温める保温効果が持続します!
③風邪予防効果:【ココア】は免疫を高め、風邪を予防します。インフルエンザウィルスに対しても強い感染阻害効果があるそうです!胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌の除去効果が高いそうです。
④貧血の改善:【ココア】はミネラル・鉄分が多く、貧血気味の人の予防や改善に効果を発揮します。
おまけに、⑤美肌効果や⑥心臓・動脈硬化予防まで備わっているので、お子さんだけでなく、お父様、お母様にもバッチリ!です。
そして、【頭の良くなる食材】として、持続効果があるとされる思考力にはかかせない「ポリフェノール」を含んでいます。
そしてそして、冷えに効くものと言えば、生姜だとばかり思っていましたが、実は【ココア】の方が効果的だったというのはかなり衝撃的!でした。
受験勉強中は、ブドウ糖の摂取は必要不可欠です。
ブドウ糖は炭水化物のごはんからしかとれませんが、脳は摂取糖分の3割も消費をするそうですから、合間の気分転換の時間でも、いかにして糖分を摂取するかということで【頭の良くなる飲み物】としても考えたい【ココア】です。
「これは飲むしかない!」ということで、いろいろな【ココア】アレンジを紹介します。飽きずにしっかり飲んでほしいから、いろいろとアレンジしながら、あと少し頑張っていきましょう!

【マシュマロココア】
ミルクココアにマシュマロを浮かべるだけ!
だんだんマシュマロが溶けてきて、甘味補給になります。
★何より気分転換に、ストレス解消にバッチリ!です。
我が家の息子たちも大好きな1品でした~。
【豆乳ココア】
ココアを豆乳で作るだけ!
甘味補給にハチミツを使ってみて~。
★食物繊維効果で便秘解消、イソフラボン効果で新陳代謝がアップします。
【シナモンココア】
ココアにシナモンをふりかけて~。
甘味補給にシナモンシュガーを使ってもおいしいです。
★胃腸の調子が悪い時や空っぽの胃に飲むといいそうですよ!
【生姜ココア】
・純ココア 小さじ山盛り2
・黒糖 小さじ1~2
・擦りおろし生姜 小さじ1
・牛乳or豆乳(お湯でもOK!) 150ml
★冷え改善に最強の飲み物と言われているのでかなりオススメです。ちなみに乾燥生姜を使った方が冷えには効果的なのだとか~!摩り下ろす手間も省け、時短にもなりますね。
母の援護射撃★【肉巻きおにぎり】
新年を迎え、いよいよ受験シーズンのスタートです。
今年度はコロナウイルスももちろんですが、インフルエンザや胃腸炎などのウイルス系が早い時期から流行ってしまい、なかなか気の抜けない受験期です。例年、受験時というものは健康に敏感になるものですが、そんな中で受験に立ち向かって行くお子様にとってストレスは半端ないものだと思います。とにかく、しっかり栄養と休息を取らせないと…と思ってしまう親心も大変な葛藤だと思います!“頭の良くなる食事”ということで、「何かを食べたから頭が良くなる」ということではなく、バランスよく食事を摂ることで健康になり、結果的に頑張れるカラダや頭(脳内)になるということで、【食事のケア=体調のケア】が受験期におけるお母様からの最大の援護射撃!ということになると思います。
しっかり食事を取らせるためには、栄養バランス=食事バランスが整った『一汁三菜』(日本型食生活)が大切だと言われます。
わかってはいても塾のある日など毎回家での食事は難しくなってくるのがこのシーズンです。すべての時間を惜しんで、勉強に頑張っているお子様たちですから、そんなお子様のためにも簡単に食べられて塾のお弁当にも最適なおにぎりでひと工夫を考えてみました!そのおにぎりとは、宮崎のB級グルメでひと時人気となり、お馴染みとなった【肉巻きおにぎり】~♪
こんがり焼いた豚肉に甘辛いタレが絡んだ、やみつき必須のおにぎりです。
おにぎりのごはんにはいろいろな具材を取り混ぜて、薄切りのお肉で包むので、栄養価のアップは間違いなしです。脳の栄養補給には、お米のブドウ糖が大切ですし、脳のスタミナにはお肉が大切なんです!豚肉を使えば、疲労回復効果も望めますから、ワンハンドで簡単に食べられて、お子様に喜んでもらえ、笑顔満点になる【肉巻きおにぎり】は、束の間の癒し気分に浸ってもらえる一品だと思います。笑顔や笑うことは、免疫力もアップしてくれますから一石二鳥かも(!?)です。
今回はおにぎりの具材として、前回のコラムで提案しました“合格ひじき”を混ぜました。
他にも長ネギや大葉を刻んだもの+白ごま、カットしたチーズ+刻んだたくあん、ちりめんetc.とても美味しいですよ。うずらの卵をごはんで包んでもテンションUP~♪です。

【肉巻きおにぎり】 4~5個
・ごはん お茶碗2杯分 *まぜる具材はお好みで!~今回は“合格ひじき”
・豚薄切り肉 2~3枚使用(1個につき) ~牛の薄切り肉でもOK!
・塩こしょう (肉の下味用) 少々
・ごま油 大さじ1程度
★タレ用合わせ調味料 ~合わせておく!
・醤油&酒 各大さじ1
・みりん&水 各大さじ2
①食材を混ぜたごはんでおにぎりを作る。
※固めに握るのが、ポイントです。
②ラップにお肉を広げて下味をし、①をのせて、おにぎりが見えなくなるまで隙間なくしっかりと肉を巻く。
※その後、ラップを使って、さらにギュッと握っておくのもポイント!です。~崩れずにキレイに仕上がりますよ♪
③ラップを外した肉を巻いたおにぎりに、薄く薄力粉をまぶす。(分量外)
④ごま油をひいた中火のフライパンで、肉の巻き終わりを下にして焼き目がこんがり付くまで動かさずに焼いていく。焼き目が付いたら次の面次の面と転がしながら焼いていく。
⑤肉に火が通ったらタレを加えて煮絡め、味をしみこませてできあがり!
★ポイントは長く焼きすぎないこと!全体に照りが出たら完成です。
★お好みで、白ごまを散らしてもOK!
★おにぎりを作る時にうずらの卵を入れて握ってもアレンジおにぎりができます。
★タレを市販の焼肉のタレや生姜焼きのタレ、あるいはめんつゆを使っても時短になり美味しいですよ。
結論から言いますと、受験勉強中は、ブドウ糖の摂取は必要不可欠!
脳は、ブドウ糖を一日に120g、1時間に5g消費し、摂取糖分の3割も消費をするそうです。とにかく、いかにしてブドウ糖分を摂取させるかということが、お母様の最大の援護射撃にかかっています~♪
白石学習院特製★合格ひじき
白石学習院の専属食育インストラクターとなって、初めて「食育イベント」をした際に、紹介した【合格ひじき】!私の原点でもある“体にやさしくて、頑張る子供たちを応援する食べ物(!?)”として、考えた‘ひじきのウエットタイプのふりかけ’です。

師走になりなんだか寒くなって来たど同時に、塾内の雰囲気も受験に向け、身の引き締まるような感じになってきました。
そんな時期だからこそ、原点の【白石学習院特製★合格ひじき】のお話です。
基礎案となっているのが、今でこそ、広島のデパートや通販でもお見かけするようになった『十二堂えとやの“梅の実ひじき”』です。ご存じですか(!?)~先日も、『秘密のケンミンSHOW』(TV番組)で、‘ごはんのお供’№1として紹介されていました。
福岡の合格祈願の神様でも有名な「太宰府天満宮」に位置する『えとや』というお店のふりかけで、大宰府の名産品のカリカリ梅の実が入ったあっさりとしたひじきがメインのふりかけです。
我が家の子供たちの受験期に「太宰府天満宮」のお守りと一緒に“梅の実ひじき”をいただいたことがきっかけで『梅の実ひじき』を知りました。これのアレンジで、ひじきを薄味に煮たものに、カリカリ梅をはじめ五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて…、各自各々で作るふりかけにしたものが【合格ひじき】です。
五色の食材とは、「赤・白・黄・緑・黒」色の見た目の判断でOK!のすべての食材が対象です。食材によって、栄養効果は多少変わってきますが、五色になるように食材をなんでも取り入れて作ると、不思議と必要な栄養素がほぼバランスよく摂れるというもので、塾デリカやお弁当作り、日々の食事作りにも率先して取り入れているひとつの方法です。
*赤色の効果としては、活力を与え、バイタリティーを高めます。‘血となり、肉となる’たんぱく質が豊富なものが多いと言われます。
*白色の効果としては、心を落ち着かせるごはんのイメージですから、‘体の素となる’イメージで、炭水化物が多く取れるようです。
*黄色の効果としては、脳を刺激して、希望につなげていけるイメージで、頭&体を動かすためのエネルギーや原動力になるものが多いです。
*緑色の効用としては、ストレスを和らげる心的効果が強く、野菜や果物に多い色ですから、体調を整えてくれるイメージのビタミン類が多いです。
*黒色の効用としては、安心感や強さ、自信を与え、体&頭、健康等の維持に必要な食材が多いです。
専門的にも立証されており、いろいろな専門書やレシピ本等も出ていますが、専門的なことを考えながらの毎日の食事作りはつらいですし、続かなくなりそうなので、「ザックリと大まかに捉えていきましょう!」という考えから、紹介をはじめた【合格ひじき】です。
これからいよいよ終盤の時期を迎え頑張る子供たちにとっては、とても大切な時期に入ります。‘食べることは生きること’と言われるように、しっかり食べることが大切な時期になりますから、ぜひ、お母様特製の『我が家の“合格ひじき”』を手作りして、食事や塾弁などに取り入れて見ませんか!

【手作り★合格ひじき】
・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で約100g
・だし汁 120~150cc (水 120cc+だしの素 小さじ1)
・醤油 大さじ2
・砂糖 大さじ1
・みりん 大さじ3
・昆布茶 小さじ2~3(*隠し味になります!)
◎トッピング
・カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老・柚子の皮(細かく千切り)・白ごま
・たらの実・ちりめん・かつお節(細かめ)・あおさ海苔・きざみのり等
①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水でひじきを戻します。(約10分位~)約8~9倍に増量しますよ!
②戻したひじきの水分をザルでしっかりと切って、だし汁と調味料をすべて合わせたもので煮る。汁気がなくなるまで、混ぜながら煮たら、【合格ひじき】の素のできあがり!
★少し乾煎りするように、しっかり水分をとばすことがポイントです!
③お好みのトッピングを適量、混ぜ入れて、お手製の合格ひじきふりかけのできあがりです。
【合格ひじき】を使って、アレンジもいろいろOK!

*例1<卵焼き>:卵に混ぜて焼いただけ!

*例2<ピーマン炒め>:千切りピーマンと【合格ひじき】を油で炒めただけ!(ほうれん草や小松菜でもOK!~卵とじでも美味しいですよ。)でもね。熱々のごはんにのせたり、混ぜていただくご飯のお供がとっても美味しいんです~♪
魚を食べると頭が良くなる~♪
「魚を食べると頭が良くなる~♪」
かつて(!?)『おさかな天国』という歌になって、スーパーの鮮魚コーナーで流れていたフレーズです。~ご存じですか?
その立役者が魚の油に含まれているDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)です。これらは体内で作り出せない必須脂肪酸の一種で、脳や神経細胞をつくったり、情報伝達をスムーズにしたりと様々な活躍をします。
脳が発達する成長期のお子様には非常に大切で、DHAとEPAを頻繁に摂取していた子どもは読解力が向上したという研究報告もあるんです。大人にとっても脳が活性化され認知症の予防になる上、血液をサラサラにしてコレステロール値や中性脂肪の値も下げる働きが認められています。まさに、頭にもカラダにも嬉しいDHA・EPAです!
これらの含有量は魚によって異なるようで、可食部の100g当たりでいうと、最も多いのは‘マグロのトロ’。そして、サンマにブリ、イワシ、アジの青魚にもたっぷりと含まれています。(もちろん、少し桁は違ってきますが白身魚にも含まれているんですって~。)
今回は旬のサンマを使って、“頭によい栄養たっぷり”のレシピをお伝えしたいと思いますが、栄養を余すところなく取り入れるための調理法は、フライパンやオーブンで調理するのがベター!サンマだと塩焼きにして、大根おろしで食べたくなりますが、これは魚焼きグリルや七輪等で焼くと仮定すると、焦げ目も香ばしく食欲UPは間違いないですが、魚の油が全部滴り落ちてしまいます。~実は、この魚の油が栄養たっぷりなのです。
しかし、魚の生臭みも含まれてしまうため、フライパンで焼いて、甘辛いタレで絡めて‘蒲焼き’にしたり、煮魚にするなら、煮汁ごと食べられるよう‘ブリ大根’のように、付け合せの野菜に煮汁を含ませたり、ハーブやスパイスなどを上手に使うのがポイントになります。
そこで、今回は【サンマの香草パン粉焼き】のご提案です。~オーブン焼きにしてみました!

【青魚の香草パン粉焼き】 2~3人分
・サンマの切り身 2~3尾分
・塩 少々
・ピザ用チーズ 適量
・じゃがいも 1個~5㎜厚にスライス
・塩こしょう 少々
※香草パン粉 ~合わせておく
・パン粉 大さじ4
・パセリ(生) 3g
・ガーリックパウダー 小さじ1/2
・オリーブ油 大さじ1
①サンマの切り身に塩をふりかけ、しばらく置く。~水分は拭き取っておく。
②耐熱容器に、スライスして水分に付けておいたジャガイモの水分を切ったものを並べて、塩こしょうを振ってラップをしレンジ500wで3分、チン!
③①の切り身の半分にチーズを適量のせて、半分に折って包んでおく。それに合わせておいた香草パン粉をまぶす。
④取り出した②の上に、チーズを広げるようにのせ、③の切り身を均等にのせていく。③の残りのパン粉を上に振りかけ、170℃でオーブン予熱を入れておいたオーブンで、15~18分焼き色が付くまで焼いたらできあがり!★必ず170℃でオーブン予熱を入れておくことがポイントです。
毎日でも食べたい魚ですが、下準備がかかってしまうのも否めません。
もっと簡単に魚を取り入れたいとお考えならば、サバやイワシ、サンマ、ツナなどの水煮缶を活用してみましょう。水煮缶は生の魚を缶に詰め、その缶ごと加熱しているのでDHAやEPAがそのままキープされているんだそうです。それらを例えば、カレーのお肉代わりに使って‘サバカレー’にしたり、パスタソースにしたり、サラダの具にしたり、味噌煮にしたりと、簡単に毎日の食事作りに活躍すること間違いなしですよ!
風邪予防対策のさつま芋!?
いつもの秋の季節とは違い、暖かい(暑い!?)日々が続いたり、一気に寒くなったりと寒暖差が大きくて温度調整がとても難しい最近です。体温調節の難しさからか、例年にない早いインフルエンザの流行でお子様方を取り巻く周辺も大変そうです。
早くも風邪シーズンの到来で、ワクチン接種や風邪予防の徹底が言われています。
食べ物の中では秋から冬にかけて、ちょうど今が旬の「さつま芋」!
「さつま芋」は冬に向けて、体調を整えていくにはうってつけの食材ということをご存じですか。
「さつま芋」は、ビタミンCが豊富で加熱しても壊れにくく、ビタミンB1・B2、カリウムも豊富!おまけに、皆様もご存じのとおり食物繊維が多いので整腸作用があり、腸内環境を整えてくれる食材です。腸内環境を整えるということは、免疫力を強化することにもつながるので、免疫力がアップされることで風邪などのウイルスにも強いカラダになるということなのです。
風邪をひきやすいこれからの時期は腸内環境を整えておくことが、最大の風邪予防対策のポイントとなりそうですね!
そんな「さつま芋」と言えば、『焼きいも』を一番に連想してしまいます。スーパーなどで焼きたての『焼きいも』のいい匂いが漂っていて、ついつい手が伸びてしまいますが、
それだけではないおすすめレシピをいくつかご紹介してみます。
食事になる「さつま芋」のレシピですよ。
これからの時期、間食やおやつだけではない積極的に食べなくては~♪の「さつま芋」です。~☆しっかり召し上がれ!!

【さつま芋&大豆の揚げ和え】 4人分
・さつま芋 中1本
・大豆水煮 50g
・片栗粉 大さじ3
・サラダ油 大さじ5
- 和風だし 小さじ1/2
- 醤油 小さじ1
- 砂糖 大さじ1
- みりん 小さじ1/2
- 米酢 大さじ1/2
・ちりめんじゃこ&ごま お好みで
①さつま芋はきれいに洗って、皮付きのまま一口大にカットして水にさらしておく。その後しっかり水切りをしておく。
②ビニール袋の中に片栗粉、①のさつま芋と大豆の水煮を入れて、シャカシャカ振ってまんべんなく絡める。
③フライパンに油を入れて熱し、②を入れて全部に火が通るまで、炒め揚げにする。
※②に油を絡めて、180℃のオーブンで5~7分焼いてもOK!ですよ♪
④鍋に●をすべて入れて、火にかけて沸騰させたところに③を入れ、ちりめんじゃこもいれて絡めたらできあがりです。仕上げにごまをふりかけましょう!
★お子様にも食べやすくて、なかなか人気の一品ですよ~♪

【お芋ごはん】 2人分
・米 2合
・さつま芋 中1本
・塩 小さじ1
・黒ゴマ 小さじ1
①さつま芋はきれいに洗って、皮付きのまま一口大にカットして水にさらしておく。その後しっかり水切りをしておく。
②炊飯器に洗ったお米と水量(2合用)を仕かけ、塩を入れて軽く混ぜておく。
③①を仕かけたお米の上にのせたら、スイッチON!
④炊き上がったら、黒ゴマを混ぜてできあがり。
★簡単~♪
旬の”秋鮭”は栄養満点!
季節の変わり目のこの時期は、昼夜の寒暖差も非常に大きくて、お疲れのカラダや何だか流行っているウイルスによる体調不良、また乾燥やアレルギー等の肌トラブルに見舞われているお子様も多いように感じます。元々乾燥肌のお子様にとっては、夏にたっぷり浴びた紫外線でダメージが蓄積しているうえに、気温も湿度も下がり、乾燥も加わることで、夏の疲れがド~ッ!とカラダや肌に出てきてしまうのだとか。
こんな季節に旬を迎える食材の【鮭】は免疫力をつけ、ハリのある潤うカラダ&肌を保つのにとても効果的なんだそうですよ。旬ならではの美味しさと使いやすさ、そして、あまりにも身近な食材の【鮭】はご家庭でも食卓に上がることが多いかもしれません。【鮭=サーモン】といえば、’サーモンピンク’という色があるほど、特徴的な赤い色をしていますが意外にも分類は白身魚なんですって!【鮭】は生まれ故郷の川を遡って産卵し子孫を残すことで知られていますが、この時強烈な紫外線を浴びるために活性酸素が大量に発生するそうで(=いわゆる、日焼けです)、この状態を強力な抗酸化力を持つ<アスタキサンチン>が活性酸素を除去して、【鮭】の身を守っているそうです。【鮭】の赤い色素はこの<アスタキサンチン>で、化粧品にも配合されている成分で、その抗酸化力はビタミンCの100倍、ビタミンEの1000倍とも言われています。<アスタキサンチン>は、肌だけでなく、万病の元になる活性酸素を除去するので、免疫力をアップさせて、血行をよくし、目の疲れや粘膜も丈夫にして、自然治癒力を高めてくれる効果もあるのだそうです。
これからの季節、風邪予防にもバッチリ!な食材です。ただ、【鮭】の<アスタキサンチン>は、【鮭】の焼き過ぎで焦がすと消失してしまうとのこと。~気をつけないと…です!見逃せない”鮭”の成分は、<アスタキサンチン>だけでなく、体づくりや脳の活性化、抗酸化作用と、頭にもカラダにも良い栄養素がいっぱいで子供も大人も積極的に食べたい食材です。
1体をつくるたんぱく質が豊富!
2カルシウムの吸収を助ける。
3脳を活性化するDHAもたっぷり!
4EPAで血液サラサラに!
5肉に比べて低カロリー。
いかがですか~!?すごいでしょう!!
そんな【鮭】を使って、【手作り☆鮭フレーク】はいかがでしょうか。
手作りと言っても簡単でとっても美味!の【鮭フレーク】は、作り置きができて保存も効くのでとても便利です。お弁当や朝ごはん等のご飯のお供として、そのままかけて食べるのみでなく、また卵焼きに入れて使ったり、炒め物や和え物にちょっと加えたりといろいろと使い勝手もいいですし、少しずつでも毎日食べられるということで、栄養も満点になりますね~♪

【手作り☆鮭フレーク】
・鮭の切り身(甘塩OK!) 2切れ
・酒・みりん 各大さじ3
・塩 小さじ1/2~
・ごま油 大さじ1/2~1
①フライパンに、鮭と、酒・みりんを入れて、中火で3~4分程度煮る。
②塩を加え、木べらで鮭を崩しながら、水分を飛ばしていく。(この時、骨も取り出す。)
③鮭に火が通り、ある程度水分が飛んだら、ごま油を加え、1~2分位煮絡めたらできあがり!~味見をしながら、塩分の調節をしてください。
★簡単~♪ですよ。★
秋の代表食材!★『きのこ』
‘食欲の秋’こそ、受験生の皆さんに栄養バランスのよい食事を取ってほしいから、“旬の食材のパワー”をたくさんいただきましょう!
実りの秋の季節を代表する数々の食材の中でも気になるもの、それは『きのこ』です。
『きのこ』には山になるほどのいろいろな種類があり、ほとんどの種類が秋に旬を迎えます。『きのこ』は、美味しいだけでなく低カロリーで、それなのに栄養満点なんです。
『きのこ』は、種類によって栄養効果が違うようで、よくスーパーでお見かけする『きのこ』だけでも、こんなに違うのですよ!
*しいたけ:脳の認知強化、記憶力アップ
*エリンギ:便秘・むくみ防止
*舞茸 :粘膜強化、美肌効果
*えのき :疲労回復効果
*しめじ :粘膜強化、肌荒れ防止

また、栄養価を見ても歴然で、ビタミンB1・B2、D等のビタミン類のみならず、食物繊維やミネラルの栄養分がたっぷりと含まれており、免疫力を高めるべく腸の力をアップしてくれます。その時々のメニューのお悩みに応じて、和洋中さまざまな料理に使える『きのこ』なので、この季節の【きのこの山】は外せませんよ~!バリエーションを変えてたっぷりと食べて欲しいと思います。
ちょっぴり『きのこ』が苦手~、という人もいるかもしれませんが、そんな苦手さんでも食べられるように、今回は形も味も変わって美味しく食べられるスープのご紹介です。
免疫力効果がアップして、腸活にもバッチリ!になるように‘ごぼう’も煮込んで【ごぼうときのこのポタージュ】にしました。これから寒くなってくるので、夜食などでもほっこり気分で、美味しいいですよ~♪

【ごぼうときのこのポタージュ】 2人分
・ごぼう 1本(約80g)
・しいたけ・えのき・しめじ・エリンギetc.
合わせて2パック位(約300g)
・玉ねぎ 1/4個
・白ネギ 1本
・青ネギ 1本
・牛乳 1/2カップ
・固形コンソメ 1個
・酢・バター・塩こしょう 適量
①ごぼうは皮をこそげ取り、斜め薄切りにしてから細切りにする。 酢少々と水2カップ程度の酢水に5分程度漬けて、ザルに上げて水気を切っておく。(アク抜きです)
②しいたけ、えのき、しめじ・エリンギは石づきを取り、小房に分け、適度な大きさに裂いておく。玉ねぎ、白ネギは薄切り、青ネギは小口切りにする。
③鍋にバター大さじ1を入れて中火で溶かし、玉ねぎ、白ネギを炒める。
※白ネギがない場合は、玉ねぎのみでOK!
しんなりしてきたら、ごぼう、きのこを加えて炒め、全体にバターが回ったら、水1カップとコンソメを入れ、15分程度弱火で煮る。
④柔らかく煮た後、粗熱をとり、ミキサーでペースト状にする。
⑤④を鍋に戻し入れ、牛乳を加えて混ぜて中火でひと煮立ちする。塩こしょう少々で味を整えたらできあがり!トッピングに青ネギを散らす。
繊維も多い『きのこ』や‘ごぼう’、食べず嫌いの食材もミキサーにかけるとたくさんの量を食べることができます。
クリーミーでリッチなお味になるので、“お代わり!”をしたくなる美味しさです~♪
旬の”茄子”を美味しく召し上がれ~♪
夏から秋にかけて旬の”茄子”!
焼く・煮る・漬ける・揚げる・蒸すなど、どんな使い方でも美味しく食べられる”茄子”には、’長茄子’や’千両茄子’、京野菜の’賀茂茄子’に’米茄子’、’丸茄子’、’水茄子’など、種類も多く古くから食材として食されています。
そんな”茄子”の主な栄養効果は、含有量こそ多くないものの子供たちのカラダを作る陰の立役者である”ビタミンB群”や”ビタミンC”、”鉄”や”カルシウム”、”食物繊維”などを幅広く含んでいます。また、近年注目されている抗酸化作用も含まれているのだとか。
そのため、”茄子”は『抗酸化・血流改善・神経伝達の活性化をサポートする』と捉えられています!
*夏バテ・食欲不振の緩和
*カラダの熱を外に放出することで火照りを除去
*肌や粘膜の強化
*記憶力のアップ
*疲れ目・眼精疲労の予防、視力低下の防御
*生活習慣病の予防 etc.
にオススメの”茄子”です!
受験生にとっても注目するべき【キーワード】にもなりそうな『ビタミンB群や記憶力UP、疲れ目や視力低下の改善』が盛りだくさんの”茄子”を使って、夕飯の一品にもなり、ペロリと食べられる”茄子”のメニューを紹介してみましょう。我が家では、再々登場する茄子メニューでその上簡単なので、お母様方のお役立ちの一品になること、間違いなしですよ~♪

【お茄子のやわらか煮】
・茄子 1パック:約4~5本分
・ごま油 大さじ1
- 砂糖 大さじ1
- みりん 大さじ1
- しょうゆ 大さじ2
- 水 100cc
・かつお節 1パック(4g)
・青ネギ 適量 ~小口切り
①茄子は、ヘタを落とし、縦半分に切って皮のところに斜めに切り込みを入れて、塩水に5分くらいつける。(塩水は、水2カップ:塩小さじ2)
※塩水に漬けることで、茄子の持っている水分を引き出して茄子が柔らかくなります。
②フライパンが冷たい状態で、①の茄子を入れて大さじ1のごま油を絡め、皮目をしたにして茄子が重ならないように並べたら、火をつけて茄子がジュクジュクになるまで蓋をして焼いていく。~約3分位
③②の茄子を返しながら、綺麗な茄子の色になってきたら、調味料を入れて煮ていく。
④調味料●を上から順番に入れていき、フタをしてさらに約3分~煮たら、かつお節を入れて絡め、青ネギを散らしたらできあがり!
※かつお節は、お出汁にもなるので、しっかり絡めます。
トロトロで、味がしみしみの茄子の煮物です。
熱々はもちろん、冷たく冷やしても美味しい【お茄子のやわらか煮】です♪
だんだん涼しくなってきて、食欲も出てくる初秋の夕飯のおかずに”持って来い!”だと思いますので、ぜひご賞味あれ~♡
【つくね丼】で「お月見」!
『十五夜』とは、旧暦の8月15日の月を指し、お月見をする習わしがあります。
「中秋の名月」とも呼ばれ、今年の2023年は9月29日です!
とっても暑かった今年の夏でしたが、ここ最近は朝夕になると秋を感じるような涼しさも味わえるような気候になって来ました!どこからか虫の声も聞こえてきて、お月様を見上げることも似合う季節の到来です。
この頃はイモの収穫期に当たるため、「芋名月」の別名もあるようです。
お月見団子、里芋やさつまいも等のイモ類、ススキ、秋の七草などをお供えして、実りの秋に感謝しながら名月を鑑賞してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、ススキは『秋の七草』のひとつです。(萩、桔梗、クズ、藤袴、オミナエシ、撫子、尾花=ススキです!)『春の七草』は“七草粥”にして食し、無病息災を祈るのに対して、『秋の七草』は、その美しさを鑑賞して楽しむもののようです。お月見の際に、ススキを飾って、彩りを添えてみてもいいですね。
『十五夜』のお供えの定番と言えば、“お月見団子”!穀物の収穫に感謝し、お米を粉にして丸めて作ったことが始まりと言われています。月に見立てた丸い団子をお供えし、それを食べることで健康と幸せを得られると考えられていました。『十五夜』では、お団子を15個お供えします。下から9個、4個、2個の15個を、また1年の満月の数と同じ12個(うるう年には13個)、15を簡略して5個をお供えすることもあるようです。
お月見団子を作るメニューでも良さそうですが、今回は、「お月見」メニューで食事になってしまう【つくね丼】で、「お月見」はいかがでしょうか。
まん丸のお月様に模した【つくね丼】ですよ~♪せっかくの「お月見メニュー」なのでイモ類のさといもを入れてみましたよ!

【お月見★つくね丼】 2人分
・鶏ミンチ 200g
・さといも 3個 (食べやすい大きさにカット)
・芽ひじき ひとつまみ(水戻し)
・青ネギ 1本(輪切り)
・白ごま 少々
●生姜 1片(すりおろし小さじ1分)
●しょうゆ 小さじ1
●酒 小さじ2
●片栗粉 大さじ1
<タレ>・しょうゆ&酒 各大さじ3・みりん 大さじ2・砂糖 小さじ4
①ボウルにミンチを入れて、●の調味料とともに均一に混ぜる。(*鶏ミンチは混ぜすぎると固くなりますよ!)
②里芋、ひじき、ネギ、白ごまを加えて、やさしく混ぜる。
③フライパンにサラダ油を小さじ1入れて熱したところに、スプーンを2本使って、まん丸になるよう形を整えて入れていく。片面、2~3分ずつ焼き付けていく。
④焼き色が付いたところで、酒大さじ2を回し入れて、フタをして蒸し焼きにする。(約1分位~)
⑤タレの調味料を合わせておいて、④のつくねを取り出した後、軽く油を拭いてからタレを入れて、熱していく。
⑥クツクツとなったところで、⑤のつくねを戻し入れて、タレを煮絡めてできあがり!
*熱々のごはんに、サニーレタスや大葉、ベビーリーフ等の上につくねをタレごとのせて、温泉卵や目玉焼きをトッピングします。
‘まん丸つくね’に、黄色い‘温泉卵のお月様’で、「お月見」です~♪
*お供え用の里芋やさつまいもの入ったお味噌汁と一緒にいただくのも良いですね。
‘朝ごはん’で生活リズムを整えていきましょう!
朝夕は少ししのぎ良くなったように思いますが、まだまだ日中はうだるように暑く、みなさん、思った以上に毎日疲れていませんか。
夏休みが終わったとは言え、汗をダラダラ流しながら、汗びっしょりで下校してくる子どもたちです。
こう猛暑が続くと、本当に体調管理の難しさを感じるだけでなく、長い長い夏休み明けということもあり、「生活リズムを整えること」の大変さを感じます。
「生活リズムを整える」には、一にも二にも朝ごはんをきちんと食べること!なんです。
朝ごはんは、1日のエネルギーの源ですから、朝はきちんと早起きをして、しっかり‘朝ごはん’を食べましょう!(百も承知だとは思いますが…)
わかってはいるけど、‘朝ごはん’が食べられないという子どもの意見も多々!
一日のすべてが終わる‘夜ごはん’をホッとした気持ちからか、しっかり食べてしまうので、‘朝ごはん’が食べられない。ヨーグルトだけとか、食べやすい菓子パンだけになってしまうとか、今時は朝からUbereatsでハンバーガーを頼んで食べる~、という声もありました。
便利な世の中になりました~。
でも、こんなダルダルの夏休み明けや猛暑のだる~い朝から、早く抜け出すには集中力を高める「レシチン」を含む食べ物が良いそうですよ~!
「レシチン」とは、特に大豆製品に多く含まれていて、納豆や豆腐、味噌やきな粉などいろいろな食材に含まれます。
この「レシチン」には、情報伝達などをスムーズにする働きがあり、記憶力アップの働きもバッチリ!で、カラダ&頭が資本となる受験生にとって、最強の栄養素のひとつでもあります。
そこで、ダルダルな夏休み明けの‘朝ごはん’に、「レシチン」を多く含む“納豆”と“お味噌汁”で、簡単だけど最強な【朝定食】にしてみてはいかがでしょうか。~‘朝ごはん’を食べないよりは、“少しでも食べる!”でも良いのです。少しずつ少しずつ、食べられようになるそうです。
ダルダルな休み明けだけでなく、寝起きはなかなか頭が働かないもの。
午前中から集中力を高めて、シャッキリ!と、おまけに勉強の効率も上がるように、朝から美味しくいただける<納豆朝定食>のオススメレシピです。
実は、冷蔵庫内にあるものをごはんにのせるだけ!
“納豆”が苦手なお子様でも、納豆臭さを感じることなく食べられてしまう、味噌+梅肉を混ぜた納豆ですから、忙しい朝には重宝すること間違いなし~♪です。
‘朝ごはん’で“納豆”と“お味噌汁”を食べていれば、どことなくホッ!とする私です。

【納豆の梅味噌丼】 1人分
・ご飯 1膳
・納豆 1パック
- 梅肉 大さじ1
- 味噌 大さじ1
- 水 小さじ2程度(~味噌を溶かすため)
- 付属のタレ 1パック
・大葉 2~3枚
・白ごま 適量
①ボウルに●を入れて混ぜ合わせておく。
②大葉は軸を切落として千切りにしたら、①に混ぜる用とトッピング用に分けておく。
③器にご飯を盛って、粘り気が出るまで混ぜ合わせた納豆をのせたら、大葉のトッピング用と白ごまを振ったらできあがり!
*ご家庭のお味噌汁とご一緒に、【朝定食】の完成です。
暑さ疲れ”対策に!★サラダうどん
毎日本当に暑い~!毎日毎日、‘酷暑’や‘猛暑’、‘熱中症警戒アラート’の文字が飛び交っています。
こんなに暑いと心配になってくるのは“夏バテ”という「暑さ疲れ」です。
「子供に“夏バテ”は無関係」なんて、思っていませんか。
“夏バテ”という「暑さ疲れ」で、朝からどんよりとしている子どもたちを多数みかけます。子どもの“夏バテ”対策も今や常識なのです。
ここ数年の異常な暑さも原因のひとつではありますが、生活習慣の変化も少なからず影響を与えている「暑さ疲れ」!
「一見元気だけど、どうも食欲がない…」「胃腸が弱っている」etc.そんな状態は“夏バテ”の初期症状かもしれません。食欲不振、全身のだるさ、倦怠感など、また熱帯夜には寝不足になってしまいますから、夏の連鎖に陥ってしまうと大変なことになってしまいます。そんな「暑さ疲れ」や“夏バテ”予防には、‘クエン酸’が良いと聞いたことはありませんか。
‘クエン酸‘が含まれる身近な食材には、梅干しや酢、レモン、柚子、グレープフルーツ等々、いわゆる「酸っぱい系」の食べ物に‘クエン酸’は含まれています。
★‘クエン酸’がカラダにいいとされる理由
①酸っぱさが食欲増進!
「酸っぱい」→「胃が活発になる」→「食欲アップで食事がしっかり取れる」、それで栄養が摂れることでバランスのとれたカラダになる!ということです。
“夏バテ”になってしまわないようにこのサイクルを作ることで、体力や免疫力が落ちにくいカラダとなり、“夏バテ”に陥ってしまうことが防げるのです。
②『‘クエン酸’回路』の働きを助けて疲労回復!
食事で摂った栄養素をエネルギーに変えるための活動を『‘クエン酸’回路』と言うそうです。体内に‘クエン酸’がしっかりとあれば、『‘クエン酸’回路』の働きが正常になります。それによって、食べたものをエネルギーに変える働きが活発となり、疲れが残りにくく、疲労回復の効果が期待できるようです。
近年、問題になっている「熱中症」!「熱中症」の原因のひとつには体内の塩分が不足してしまう事が挙げられます。汗と一緒に体内の水分のみならず、塩分=‘ナトリウム’が出ていってしまい、血が薄くなってしまうのです。そこで、梅干しを食べて塩分を摂るということは、‘クエン酸’以外にもビタミンやミネラルを摂取できるので、「熱中症」の予防にもなるということでベスト!‘クエン酸’=梅干し最強説(!?)です。
でも、‘クエン酸’だけ取っていてもダメ!‘クエン酸’だけ摂っていれば良いというわけではありません。「‘クエン酸’の効果を高める」「夏バテの予防をする」というのであれば、【‘クエン酸’+ビタミンB群】の組み合わせを考えた献立にすると、“夏バテ”予防の効果がアップします。
また、お子様の食欲がない時には、ビタミンB群だけでなく、たんぱく質も食材に取り入れてみましょう!ちなみに、ビタミンB群の代表食材は【豚肉】、そして、たんぱく質には【鶏肉や卵】などが挙げられますね。
‘クエン酸’と疲労回復の関係性を知っていただいたところで、暑い夏休みのランチメニューに、また、食欲がない時でも簡単に食べられ、“夏バテ”“暑さ疲れ”の予防にもなる食事ということで、今回は、栄養満点の【冷しゃぶサラダうどん】はいかがでしょうか!
手作りの【万能☆ゴマドレ】でいただきます~♪

【冷しゃぶサラダうどん】 1人分
・うどん 1玉 (ソーメンやパスタでもOK!)
・豚しゃぶ肉 100g
◎梅干し 1個
◎麺つゆ 50cc
・オクラ、レタス、きゅうり、玉ねぎ、トマト、ブロッコリー、もやし、大葉等々~冷蔵庫にあるものでどうぞ!
- 【万能ゴマドレ】 適量
・すり胡麻&きなこ 大さじ1(きなこのみでもOK!)
・砂糖 大さじ1
・酢 大さじ1
・マヨネーズ 大さじ1
・醤油 大さじ1(麺つゆでもOK!)
①オクラ&もやしをサッと茹でた後、うどんを茹でて水でしめる。~茹でたオクラは細く輪切りにし、もやしは水気を切っておく。
②豚しゃぶ肉も茹でて水でしめておく。~*薄く片栗粉をまぶしてから熱湯に入れ、すぐ火を止めて、余熱で茹で上げるとやわらかいお肉に仕上がりますよ!
③◎の梅干しは種を取り除き、細かくたたいて麺つゆと合わせる。①のオクラも入れて、混ぜ合わせておく。
④【ゴマドレ】は合わせて混ぜるだけ。
⑤サラダの野菜はお好みにカットし、各々を盛り付けて、しっかり冷やしてお召し上がりください!③のつゆはお肉の上からたっぷりと回しかけて、④のゴマドレはお好みでかけながらいただきます。
夏のチャレンジ!★「わらび餅」
今にもカラダが溶けてしまいそうなジリジリ・ムシムシの猛暑の8月!
火を使うのも、キッチンに立つのも億劫になってくるような…私にとっては、一番苦手な季節です~。
それでも3食食事を作り、おまけにおやつも必要なのが夏休み中の母親の常~(!?)
それも暑い時期だから、冷たいものになりがちなのも、母にとってはお悩みの種だったりしますよね。
そこで、火を使わずに、なるべく調理時間も短くて、何なら子供たちにも作れちゃう!(みたいな)暑い季節にぴったりのサッパリ涼やかなデザートのご紹介です。ゼリーやシェイクetc.ではないんです!
フルに体や頭を動かした時、子供たちやお母様のお疲れモードの時、甘いものが食べたかったりしませんか。でも、買い物に行くのも作る手間も面倒!!そんな時にオススメなのがレンジで作る和菓子の【わらび餅】です。【わらび餅】は透明で見た目にも涼しげなので、夏の和菓子の定番の一品です。きな粉や黒蜜をかけて食べるので、リラックス効果や脳内の栄養分としてもバッチリ!

【わらび餅】は、本来わらびの根っこから取れるデンプンの“わらび粉”が使われるのですが、現在の【わらび餅】は、サツマイモやタピオカから取れたデンプンや、葛粉を主原料として作られているものがほとんどなのだとか。でも、そんなもの、家に常備なんてしていませんよね~。なので、片栗粉、砂糖、熱湯と材料はたったの3つ!おまけにレンジで、思い立ったらすぐできる【簡単★わらび餅】はいかがでしょう。~(片栗粉はジャガイモから製造されているデンプンです。)

【レンジで★わらび餅】
・片栗粉 50g
・砂糖 50g
・熱湯 250~300cc
・きな粉、黒蜜など 適量
~今回、きな粉は普通のきな粉と青きな粉を使用!
①片栗粉と砂糖と熱湯を耐熱容器に入れて、なめらかになるまでゴムべらを使て、よく混ぜる。
②①をレンジ500w~600Wで1分加熱!その後、濡れたスプーンでかき混ぜる。これを3~4回繰り返す。
★途中何度かかき混ぜることで、モチモチ食感を引き出すとともに、加熱のムラを防いでくれます。
③加熱3~4回で、全体的に透明でモチモチした感じになります。
④③の状態になったら、さらに濡らしたスプーンで混ぜてから、スプーン等で丸く形を整えながら、冷水に落としていく。
⑤よく冷えたら、水気を切って、お好みできな粉や黒蜜をかけてできあがり!
★熱湯の量は、しっかりめの食感が良ければ250cc、やわらかめの食感が良ければ300ccと、お好みで加減をしてください。(ちなみに、今回の湯量は280ccです!)
★・黒砂糖100g・水100mlを鍋に入れ、中~弱火で混ぜながら煮詰めて作る【黒蜜】をかけても美味しいですよ~♪
【わらび餅】のボウルをレンジから取り出す際に、やけどだけには要注意!です。
そうしたら、お子さんにも作れちゃう、夏休みの自由課題にもなりそうな【わらび餅】です~♪
【ちんすこう】で夏休みのティーブレイク!
もうすぐ夏休み~♪
今年の夏は、コロナ禍も緩和された影響で、夏休みに旅行に行かれるご家族も多くなるのではないでしょうか。
夏の旅行の候補地になりやすい沖縄!
沖縄のお土産として人気の【ちんすこう】をご存じですか(!?)
【ちんすこう】の「すこう」は沖縄の方言で‘お菓子’という意味で、頭に付く「ちん」は‘珍’や‘金’を意味しているそうです。
昔々、琉球王朝時代の沖縄では、【ちんすこう】は王侯の貴族しか食べることのできなかった大変貴重で高価なお菓子だったのだとか。そのことから、庶民にとっては珍しいお菓子だったために、“珍しいお菓子”=【ちんすこう】と呼ばれるようになったそうですよ。
そんな【ちんすこう】の材料は、なんと小麦粉・砂糖・ラード(油)の3つだけ。
ラードが使われているため高カロリー!だけど、脂質がたっぷりな分、とても腹持ちが良く、栄養成分としては炭水化物がもっとも多いため、ちょっとしたカロリーメイト的な働きをしてくれるそうです。
【ちんすこう】のカロリーは100gあたり515kcalで、1個(20g)あたり103kcalになります。カロリーメイト1個が100kcalなので、ほぼ同じになるのだそうですよ!
おまけに、糖分をたっぷりと含んだ甘いおやつは、脳のエネルギー消費量が高いお子様においては、食事だけでなく、とても必要なものとなります。私達が疲れを感じた時、妙に甘い物が食べたくなるのが、まさにコレ!甘い物=糖分は、脳をリラックスさせる働きがあり、リラックスしている時にこそ、集中力が発揮され、集中することで注意力を維持する効果も高くなるということで、受験生にとっての“おやつの効用”、特に「甘いおやつ」と言うところが、ポイント!のひとつかもしれませんね。
なので今回はちょっと軽めに、“ティー・ブレイク”!のレシピです。
【ちんすこう】は簡単な材料で作ることができる超シンプルなお菓子です。ご家庭でも簡単に手作りできるんです~♪
【ちんすこう】は、なぜかクッキーなどと違って、意外と男子にも好きな子が多いように感じます。
夏休みのお疲れ時の甘いおやつorカロリーメイト的なおやつに、ぜひお子様と手作りからチャレンジしてみませんか!
ラードの代わりにショートニングでもOKですし、今回はもっと簡単にサラダ油(キャノーラ油etc.)を使いました。また、砂糖を三温糖や黒糖に代えて作り、ミネラル成分たっぷりにするとさらに栄養面でもGOOD!になりますし、小麦粉の一部の量を抹茶やココアに入れ替えてもバリエーションアップの【ちんすこう】になりますよ~♪


【ちんすこう】 約20個分
・薄力粉 340g
・サラダ油 130g
・三温糖 130g
①ボウルに三温糖と油を入れ、三温糖の粒が見えなくなるまで混ぜる。
②①に小麦粉をふるい入れて、ヘラでさっくりと混ぜ合わせる。
③楕円形に成形(市販のちんすこうのように)して、オーブン(予熱あり)170℃13分~15分で焼いたらできあがり!
※やわらかすぎて成形しにくい時は、30分位冷蔵庫に入れてみてください!
※焼き立て熱々だと、柔らか過ぎて形が崩れますので、しっかり粗熱は取ってくださいね。
『ピュイゼ・メソッド』★【五味】の旨味!
「食べ物の好き嫌いが激しくて~」や、「ファストフードやお菓子なら食べるのに…!」といったこれらの事は世界中の子供たちに共通していることのようです。
この状況というのは、【味の違いがわからない】ことがひとつの要因とのこと!
このように提言されている方は、フランスのピュイゼさんです。
『ピュイゼ・メソッド』というのをご存じですか(!?)
30年前にピュイゼさんが始められた、子供を対象とした食育のひとつである「味覚を目覚めさせる授業」の1コマのことなのです。フランス全土の小学校で実施され、世界中に広まった‘食の授業’を、日本版では<ホテル・ドゥ・ミクニ>のシェフ三國清三さんが広めていらっしゃいます。
【味覚】とは。味わいのこと!
自然の食べ物には、5つの味があり、【五味】で表されており、【五味】とは【甘味・酸味・塩味・苦味・旨味】が基本の味とされています。
『甘味』の中には砂糖だけでなく、野菜が持つやさしい甘味もあります。
『酸味』といっても、酢だけなく梅干しや柑橘類なども含みます。中でも『旨味』は特徴的で‘日本食のかつお節や昆布だし’に代表される味わいで、日本人にのみ備わっている味覚だとも言われます。
実は、【五味】といわれる味覚のひとつに‘旨味’が入っているのは、世界的に日本だけなのだそうですよ!
日本人は昔から、お出汁や味噌、醤油などの発酵食品が持つ‘旨味’に親しんできた背景があります。ですから、‘旨味’は特別なものではなく、基本の味覚として【五味】に加えられているとのことで、フランスやイタリヤなど他の国では、基本の味覚は4つで「四味」なんですって。
‘旨味’は、英語でもそのまま‘umami’と呼ばれているのだとか!これで、味覚の基本が【五味】で形成されているとのことで、日本人の私たちにしたら、驚きです。
“『味覚』を発達させていく”ということは、「五感」=視覚・聴覚・臭覚・触覚・味覚をフルに活用してくことがポイントになるそうですから、子供の好奇心をも目覚めさせてくれることとなりそうです。
頭だけではなく、カラダ全部を使っての好奇心は子供ならではの特徴で、一生懸命に考えようとする秘めたる力にもつながるとも聞きますから、『味覚』を発達させるということは、日々の<脳活トレーニング>にもつながっていき、バッチリ!のトレーニングになるのかもしれません。
少しの暇を見つけては普段の食卓で、かつお節や昆布からダシを取った‘旨味’で<脳活トレーニング>=“我が家のピュイゼ・メソッド”なんて、いかがでしょうか。
なんだか母も頑張っているような気がしてきます~♪
そこで、今回のレシピは、暑くなってきた季節の食欲ダウンの時期でも食べたくなる、『冷やしソーメン』です。これを「塾弁」にしてもOK!の【冷やしソーメン弁当】に仕上げてみましたよ。

まずは‘旨味’をしっかり堪能してもらうために、【簡単ソーメンつゆ】のご紹介から!
【基本のソーメンつゆ】 1000ml
・だし昆布 10㎝幅
・花かつお 40g(大袋の半分量位です)
・水 800ml
・醤油 1カップ
・みりん 1カップ
①鍋に水と昆布を入れて、10分~置いておく。その後、弱火にかけて沸騰直前で昆布を取り出し、沸騰後、かつお節を入れたらそのまま2~3分位火にかける。
②火を止めたらかつお節が全部沈み込むまで放置し、その後静かに濾す。ここで再度800mlになるように水を足して、鍋にもどし、みりんと醤油を入れて火にかけ沸騰後2~3分位グラグラ煮たらできあがり!~※お好みの味加減で調節してください。
お弁当時には少人数分を簡単にレンジで作って、冷たく冷やしておきますよ!~冷凍したものを保冷剤代わりにそのまま持って行き、食べる頃には溶けてきて冷たい状態で美味しく召し上がれます♪

【レンジで★簡単ソーメンつゆ】 2~3人分
- 醤油 1/2カップ
- みりん 1/2カップ
- 水 1カップ
- 砂糖 大さじ2~3 ※お好みで
- 花かつお ひとつかみ
- だしの素 少々 ※味を整えます。
①耐熱ボウルに●を全部入れ、軽くかき混ぜたら、レンジで500w2分加熱!
②かつお節を濾したら、できあがり!~嫌でなければ、かつお節はそのままでもOKです。~たんぱく質が取れますよ♪
【冷やしソーメン弁当】
※ソーメンをお弁当にする時は、しっかり目に茹で上げて、冷水で引きしめるのがポイント!です。時間が経つとダマになりやすいので、フォークで一口大にくるくる巻いてお弁当箱に入れると食べやすいですよ。
※トッピングは、食べやすいように‘くるくるソーメン’の中心に押し込みました。
※トッピング例:「錦糸卵」「牛肉の甘辛煮」「大葉と甘酢生姜の混ぜ合わせたもの」「プチトマト」「アスパラ」「きぬさや」~いつもの冷やしソーメンの具材でOK!です。
チーズの栄養パワー!
毎日の食事で気になることのひとつが、食材等に含まれる栄養素です。
どうせ食べるならば、カラダに良いものを少しでも多く取り込みたいですよね~♪
栄養素には、炭水化物や脂質、塩分など摂取量より多く摂りがちなものと、カルシウムや鉄分など、不足しがちなものがあると言われます。
なかでもカルシウムは、日本人のすべての年代において不足しがちな栄養素!
特に子供たちは丈夫な骨を作るために、カルシウムがたくさん必要になります。(お年寄りは、骨折を防ぐためにカルシウムが必要です。)
カルシウムといえば、小魚や牛乳と思われがちですが、「チーズ」だってカルシウムが豊富です。しかも、小魚や牛乳よりも少量で必要な量を摂ることができるので、毎日食べ続けることができます。
「チーズ」は生乳のたんぱく質を凝固させ水分を絞って作りますが、100gのチーズを作るのに必要な生乳は1000ml=牛乳パックの1本分です。つまり、10倍の量の栄養素がギュッと凝縮されているのが「チーズ」なのです。
カルシウムは、若年時の摂取量が多いほど、高齢になってからも骨密度が高いことがわかっているそうです。
「チーズ」には、塩分も比較的多く含まれているので、食べ過ぎには要注意ですが、良質なたんぱく質も豊富で、貧血予防の効果も大きいのです。また、上記でも触れたように、カルシウムも多く含まれるので、ストレスを沈め、イライラ解消の効果も侮れません。
ちなみに、「チーズ」の食べ過ぎ防止の目安は、三角形の6Pチーズなら、3個!スライスチーズなら、3枚!なんだそうです。
そこで、子供たちのおやつやデザートに「チーズ」を取り入れてみませんか。
おやつは、三度の食事だけでは十分に摂取しにくい栄養素を補う<捕食>として大切な意味を持ちますし、塾から帰宅後の夜食としても同様です。
どうやって毎日のカルシウムを摂るかがポイントになってきますので、簡単におやつ感覚でカルシウム効果が取り込めるように【チーズレシピ】のご紹介です。

【チーズシュー】 2人分
・ベビーチーズ 2個 ~6Pパックや8Pパックのチーズです!
・黒&白胡麻 適量
①ベビーチーズ1個を6等分くらいにカットして胡麻をまぶす。
②クッキングシートにのせて、レンジ600wで2分30秒加熱するだけ!
*ふっくらカリカリ!で、高濃度のカルシウムが摂れる「チーズ×胡麻」です。
*スライスチーズでレンジでチン!すると、“チーズせんべい”になりますよ~♪
なんだか最近、チーズが苦手というお子様の声もチラホラと聞きますので、上記の【チーズシュー】にお好みのジャム等を挟んで“マカロン”に変身させましょう!

【チーズマカロン】
・ベビーチーズ 2個~
・お好みのジャム 適量
~いちご、ブルーベリー、マーマレードetc.
①【チーズシュー】は上記の作り方同様で、プレーンシューを作る。
②しっかりと冷ましたシューとシューの間にお好みのジャムを挟めば完成です。
*チョコレートクリームやバニラアイスなどをはさんでも美味しいですよ~♪
毎日の料理をひと工夫したり、いつもの料理をさらに美味しくするために、また、おやつ
やおつまみ、ほっと一息ティーブレイクにも【チーズ】の栄養パワーをぜひ取り入れてみてくださいね!
食育って!?
毎年6月は「食育月間」!ご存じですか~?!
生涯を通して、健康なカラダと心を育む上で“食べること”は何より大切なことです。
農林水産省では、「食育」とは『生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるもの』と、また文部科学省では、『子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけること』定義されています。
これを基として、「食育」とは、【生活の基礎づくりに役立つ、基本的な食事を学ぶ教育】と捉えられられ、取り上げられるようになりました。
ということで、「食育って」=「さまざまな経験を通じて‘食’に関する知識や、自分で食べ物を選択するチカラを身に付けて、健康的な食生活を実践する、チカラを育むこと」なんだそうですよ。
そして、余談にはなりますが毎月19日は、「いただきますの日」とされていて、家族や地域に暮らすいろいろな人と‘共食’の大切さについて、考えたり語り合う日なんだそうですよ。
ひと言で「食育」は語れない感じですね~!
また、「食育」のテーマの中には、栄養バランス・会食の楽しさ・感謝の心・生活リズムと言ったものだけでなく、その他に食材や調理方法・行事食や郷土食等についても含まれるのだとか。
では、【郷土食】とはどんなものなのかご存じですか~(?!)
【郷土食】は、各地域の産物を上手に活用して風土にあった食べ物として作られ、食べら
れてきた料理です。そして、歴史や文化、あるいは食生活とともに受け継がれて来てい
る料理です。ご当地の名産品等を使いながら、子供や孫たちに代々引き継いでいきたい料
理だということですね。
ちなみに、全国津々浦々たくさんの【郷土食】が存在しているんですよ~。
【ほうとう】:山梨県の太い平麺を使った里芋等たくさんの野菜が入った具だくさんの煮込みうどんです。

【ヒラヤーチー】:沖縄の家庭料理で‘平焼き’のこと、お好み焼きやチヂミの沖縄版!といったところでしょうか。

【ばち汁】:兵庫県播州地方のそうめん(‘揖保の糸’の名で知られています)を使ったそうめん汁です。
【とふめし】:兵庫県丹波地方に伝わる、木綿豆腐にごぼうや人参、油揚げ、隠し味に鯖が入ったものを甘辛く炒めて、熱々のごはんに混ぜ込んだ‘混ぜご飯’です。
【五平餅】:中部地方の山間部(長野県木曽・岐阜県美濃や飛騨地方・愛知県奥三河等)で食べられているご飯に味噌タレを付けて焼いたものです。
広島でいう【郷土食】とは、牡蠣めしやあなごめし、鯛めし、わけぎのぬた、もぶりめしetc.というのがあるそうですが、最近では、‘広島レモン’使ったものがいろいろと考えられているようです。~G7広島サミットでも取り上げられていましたね!そんな【郷土食】を取り上げてみる『塾デリカ』があっても、地理や社会のお勉強になるかもしれませんし、また、それを踏まえて、食事中のお友だちとのコミュニケーションが弾んだとしたら、楽しいかもしれませんね~♪
『塾デリカ』のテーマは、「食べ物からカラダを作りながら、脳を活性化する」こと!食事を取りながらコミュニケーションをとり、栄養バランスも摂れたら最高!~という思いから始まっていますので、しっかりと「食育」が原点となっていますよ。
そこで、今回は、野菜も魚も入る‘混ぜごはん’兵庫県丹波地方の郷土食【とふめし】のご紹介です。
脳のエネルギー源であるごはんに、豆腐の良質なたんぱく質やDHAたっぷりの‘青魚の王様’鯖が入るので、集中力を高める脳活にも持って来いだと思います~!

【とふめし】 2~3人分
・ごはん 2合
・木綿豆腐 1/2丁(つぶす)
・ごぼう 1/2本(ささがき)
・人参 Ⅰ/2本
・油揚げ 1/2枚
・焼さば 切り身1枚(ほぐす)*ツナ缶(1缶)でもOK!です。
・醤油 大さじ1
・みりん 大さじ1
・和風だし 大さじ1/2
①ごはんは炊いておく。
②人参・油揚げは細かめの食べやすい大きさにカットしておく。
③鍋にごぼう・人参・油揚げを入れ、ヒタヒタの水とだしを入れて煮る。
④ひと煮立ちしたところで、つぶした豆腐とほぐしたさばの身、みりんと醤油を入れて、炒りながら煮汁がなくなったらできあがり!
⑤熱々のごはんに混ぜ込んでいただきます。
★‘焼さば’は、お惣菜のものを買ってきてほぐしてOK!です。
【マリトッツォ】をご一緒に!
GWはいかがお過ごしでしたか~♪
気分転換も交えての休日になっていたならば、よかったです!
ここ何年間かはコロナ禍もあり、遠出もままなりませんでしたが、今年は帰省やちょっとした行楽スポットに出かけたご家庭も多かったのではないでしょうか。
そして、また今年の5月は、18日~22日に広島に限ってですが、G7サミットのお休みがある学校や勤務先も多いかと思います。
GWに引き続き、すこ~しのんびり気分のお子様とご一緒にお楽しみ時間を~♪ということで、簡単におやつにもなるフルーツたっぷりの【マリトッツォ】を作ってみませんか。
旬のいちごがたっぷりのフルーツサンドも、春になるとちょっとしたブームになりますよね!それよりも簡単に作れるフルーツサンドのような、フルーツたっぷりの【マリトッツォ】なんですよ。
最近ブームになった【マリトッツォ】のことをご存じですか~?
【マリトッツォ】とは、しっかりと焼き色がついたふんわり食感のパンにたっぷりの生クリームをはさんだスイーツなんです。発祥は、イタリアのローマで、朝食代わりに【マリトッツォ】とカプチーノやエスプレッソをとることが古くから親しまれているそうで、起源は古代ローマにおよぶということで驚きです。
たっぷりの生クリームが栄養補給になることから長年朝食代わりに親しまれているようですが、今回はフルーツもたっぷりいただきたいので、ヨーグルトを使います。そして簡単に作りたいので、ロールパンで【マリトッツォ】を作りますよ!

【フルーツたっぷりマリトッツォ】 4個分
・ロールパン 4個
・プレーンヨーグルト 200g(大1パック)
・クリームチーズ 100g~常温に戻す
・砂糖 20g
・りんご&レーズン 1/4個分くらい
(レーズンは湯戻しをしておく)
☆いちご(3等分カット)2個
☆キウイ(半月切り) 1/2個
①プレーンヨーグルトは、キッチンペーパーを敷いたザルに入れて、ボウルで受けた状態で冷蔵庫内で2~3時間くらい水切りをしておく。(しっかり水分を切っておく方が作りやすいですよ、)
②ボウルに室温に戻したクリームチーズと砂糖を入れて、なめらかになるまで混ぜ、①を加えて混ぜ合わせてしっかりと冷やしておく。
③りんごは皮を剥いて5㎜角に、湯戻ししたレーズンも細かくカットし、いちご&キウイもそれぞれカットして、冷蔵庫でひやしておく。
④ロールパンに切れ込みを入れて、②のクリームにりんご&レーズンを混ぜ合わせてものをたっぷり(クリームの1/4量が目安)とはさみ、いちご&キウイを周りに飾り付けてできあがり!
★作った後、さらに冷やしておいても美味しいです!
レモン効果で‘リフレッシュ’サラダ!
新年度が始まって走り続けてきた4月も終わり、ホッ!と一息のGW:ゴールデンウィークがやってきました。
新年度って、新しい環境がスタートして上手くやっていけるかを確認しながら様々な状況にも慣れていかないといけないし、初めて会う人達も多いかもしれませんし、そしてお勉強も頑張らないといけないetc.‘ストレス’がMAX!~のお子様も多いはずです。
何かと新しいことばかりでやる事も多すぎて、カラダ&心がお疲れ気味~になっていたことでしょう!
そんなお子様や大人の皆様が、少しでも‘リフレッシュできるようなさわやか副菜’のご紹介です。
ところで、‘ストレス’って、どんなものなのでしょうか?
実は、‘ストレス’の由来って、ボールに圧力がかかって歪んだ状態のことから来ているようなのです。‘ストレス’状態を引き起こす要因が加わって、心身に負荷がかかった状態のことを指すのだそうですよ。
‘ストレス’も受け止め方で違ってきて、大きく二つに分かれます。
*『良いストレス』;目標や夢、良い人間関係(ライバル等)など、自分を奮い立たせてくれて、元気にしてくれる刺激やその状態
*『悪いストレス』;過労、悪い人間関係、不安など、自分の体や心が苦しくなったり、嫌な気分になったり、やる気を無くすような刺激やその状態
ということで、「リフレッシュ」できる方法も『良いストレス』状態になれるものが必須!
です。『良いストレス』状態は“リラックス”できていることでもあるのです。
【リラックスできる方法】には、
①好きな音楽を聴いたり、②友達とのおしゃべりだったり、③外に出てお陽さまや風にあたる外気浴=散歩だったり、④ぬるめのお風呂にゆっくりつかってみたり、⑤香りでリラックスできたり、⑥楽しくみんなで食事をし、⑦十分に眠るetc.があるようです。
‘リフレッシュできるようなさわやか副菜’とは、楽しくみんなで食事をし、香りでもリラックスできる‘五感’を使った、気分転換にも使われて疲労回復やストレス解消に活用することができる「アロマ」的な効果もある【春サラダの“コ-ルスロー”】です。香りのみを楽しむだけではなく食べ物を味わうことも効果があり、“コ-ルスロー”に使う【レモン】の香りには、抗うつ作用があり、その爽やかな香りで不安な気持ちや緊張を和らげてHAPPY気分にする効果があるのだとか。広島G7サミットでも、「広島レモン」として、取り上げられている【レモン】ですから、しっかりと摂り込んで‘リフレッシュ’効果に期待ができそうです。
そして、忘れてはいけない受験生の強~い味方の食材のひとつ、DHA等で脳活にもバッチリ!な時短食材の‘ツナ’も使います~♪
“レモン”効果でレフレッシュ!をポイントとする、マヨネーズを使わない【ツナ&柑橘のコールスロー】を考えてみましたよ。

【レモン風味★ツナ&柑橘のコールスロー】 3~4人分
・キャベツ 400g(1/2玉位)
(塩水=水:500ml 塩:大さじ1)
・ツナ缶 1(汁気を切る)
・柑橘類 お好み~八朔を1個使用
- オリーブ油、砂糖 各小さじ2
- レモン汁 大さじ1/2
(1/2個分を絞ったくらい)
①春キャベツは大きめの千切りにし、ビニール袋に切ったキャベツと塩水を入れ、塩もみをして10分位置いておく。
②今回使用の八朔の皮を剥いて、身を取り出して、冷やしておく。
③ボウルに●を混ぜて、ドレッシングを作る。~レモン汁+砂糖を混ぜ溶かしたところに、オリーブ油を少しずつ混ぜていって乳化させる。
④①のキャベツのビニール内の水分を切って、ビニールごと絞ってキャベツの水分をしっかり切ったものを③のボウルに入れ、ツナと八朔も入れて混ぜ合わせて、完成です。
*残っているレモンも切って混ぜ合わせてもOK!ですし、例えば、残っているマーマレードジャムを砂糖の代用で使ってももっと簡単にできますよ!
“基本のダシ”で栄養の積み重ね!
日本人の食事に欠かせない“出汁=ダシ”。
普段の食生活で、何気無く使っているダシですが、毎日のメニューを考える上で、肉や魚、野菜などの食材の栄養バランスは気にしつつも、肝心な出汁の栄養についてはあまり考えていないように感じます。
汁物や鍋などの美味しいスープや、煮物などにも大活躍のダシですが、料理の引き立て役や脇役のように‘影の存在’的な役割です。
しかし、ダシの栄養は吸収も良く、色々な効果が検証されているのですよ。
“ダシ”にも種類があって、‘昆布だし’‘かつおだし’‘いりこだし’‘アゴだし’に昆布&かつおの‘合わせだし(一番だし)’‘椎茸’や‘鶏肉’等々、多種多様な種類がありますね!
そんな豊富な食材から出る“ダシ”の栄養とその効果は、健康になるための秘訣がいっぱいなのです。

【‘昆布だし’の昆布に含まれる主な栄養】
- ミネラル(カルシウム・鉄・ナトリウム・カリウム・ヨウ素)
- 水溶性食物繊維
- 旨味成分
特に、カルシウムは100g中の含有量が、なんと牛乳の
6倍以上にもなるというから、驚きです。
水溶性食物繊維は、糖質や脂質の吸収を抑え、塩分の排出をしてくれる作用があるため、様々な病気の予防になります。旨味成分のグルタミン酸は、胃腸の働きを促し、旨味があることで減塩効果が期待できます。
【‘かつおだし’の主な栄養】
- たんぱく質
- ミネラル
- ビタミン類(ビタミンB1・B2・Detc,)
- 必須脂肪酸(EPA・DHA)
- 旨味成分
鰹節は、約7割がたんぱく質という高タンパクな食材です。そのたんぱく質の中には、必須アミノ酸がバランス良く含まれています。また、鰹節に豊富に含まれるカルシウムは出汁の中にも溶け出すので、カルシウム不足を補うことができますし、アミノ酸は、良質なたんぱく質を体内に取り込むために必要な栄養素です。そして、必須脂肪酸のEPA・DHAは、ご存じ脳の活性化には欠かせない、【受験生の友】!
これが豊富に含まれているとなると、‘かつおだし’侮れませんね~。
また、‘かつおだし’には、脳内の血流が良くなるはたらきが実証されていて、脳や眼の疲労回復改善や精神的な疲労感改善、肩こり改善や記憶力・集中力アップといった、お子様のみならず、ご家族全員で摂りたい効果がたっぷり!
“ダシ”の効果は、身も心も軽々にしてくれて、頭をはっきりスッキリとクリアにしてくれるのです。
そんな素晴らしい栄養効果がある“ダシ”をご家庭でも簡単に取って活用していただけるように、【基本の出汁の取り方】のご紹介です。
和食の基本とも言われる“昆布&かつおの合わせだし”で、失敗の少ないしっかりとした出汁の取れる「煮だし法」をお伝えします!

【基本のダシのとり方】
~一番だし:“昆布&かつおの合わせだし”~
・水 2000ml
・昆布 20g
・花かつお(鰹節) 40g
①昆布の表面を固く絞った濡れ布巾でサッと拭き、
両端に何か所か切り込みを入れる。
②分量の水の中に①を入れ、しばらく置いた後、中~弱火で沸騰直前まで、火にかける。
*沸騰直前の見極め方は、昆布の周辺に小さな泡がたくさん付き、鍋の上に湯気がフワフワと立ち上がりだしたら、もうすぐ沸騰します。
③②の沸騰直前で昆布を取り出し、沸騰したら少量の水を差して沸騰がおさまれば、鰹節を全量一気に加える。
④③がひと煮立ちしたら、すぐに火を止め、アクを取り除く。
⑤鰹節が沈み始め、完全に沈んだら、ザルにキッチンペーパーを敷いたボウル上で静かに濾して、一番だしを取り出します。


【基本のダシ】で、お好みの具材を煮込み、ご家庭のお味噌を溶いて≪お味噌汁≫を、また出汁を使って煮物や蒸し物などに活用して、隠れた素晴らしい栄養をたっぷりと体内に摂り込んでください!
毎日の少しずつの基本の取り組みは、カラダを作るためにも大切です。
カラダも、お勉強の基礎力と同様に毎日の積み重ねということでしょう~♪
旬の食材!★ 春“たまご”
春キャベツや菜の花、アスパラガスや新玉ねぎetc.春が旬の野菜がたくさん出回っています。春の食材の特徴は、野菜であれば繊維がやわらかく、甘味が強いこと。また苦味のある野菜が出回るのもこの季節の特徴です。
山菜の辛味や苦味成分には抗酸化効果があると言われ、季節の変わり目の体調を崩しやすい時期に身体の内部環境を整えてくれる効果があるようです。そして、つら~い花粉症にも効果が期待されている春野菜が多いのも要注目です!
旬の食材には、その時期の人間のカラダに必要な栄養や効果が含まれているものが多い~ということで、不思議です。
ちょっと変わったところで、生命が息吹く春は、“たまご”も旬!なんですって。
植物が芽吹き、虫たちが地中から顔を覗かせる春は、鳥や動物たちにとってもそれらを糧としていることを考えれば、‘なるほど~♪’と頷けます。

ニワトリも暖かくなってくると健康的に活動し始めるワケですから、“たまご”もおいしくなるはずです。(でも、今年は春を迎える前に鳥インフルエンザが流行してしまいました!)
たまごは店頭価格の変動が小さく、また栄養価は高いので、「物価の優等生」「栄養価の優等生」と言われてきましたが、最近では価格高騰が止まりません。おまけに、小玉になっている感じもいなめませんが、やっぱりたまごは、気泡性(メレンゲ・ケーキなど)、乳化性(マヨネーズなど)、凝固性(茹で卵や茶碗蒸しなど)という3つのチカラを発揮して料理の幅を広げ、食卓を楽しませてくれるだけでなく、ハッピーな気分にもしてくれる食材に違いありません。
そんな自然界を生き抜く旬の食材の持つ“パワー&エネルギーをいただけ!”とばかりに、“たまご”の甘味と色味が際立つ、ふわトロッ!とした<スパニッシュオムレツ>のレシピを紹介します。卵だけでも美味しいオムレツですが、たまごの価格が高騰している今だから、具材を何でもたっぷりと入れて、味も見た目もボリュームアップしてみましょう。具材と卵を混ぜて、器に入れ、オーブンで焼けばいいので、夕食やちょっとしたパーティー用のおかずにも便利ですよ。そして、何よりお子様からも美味しいと言ってもらえること間違いなしのレシピになっています!

<スパニッシュオムレツ> 4人分
・卵 5個
・牛乳 50cc
・パセリ 1株(みじん切り)
・木綿豆腐 100g
<具材>
・ジャガイモ 中1個
・玉ねぎ 中1/2個
・ベーコン 2~3枚
・人参 1/3本
・ピーマン 小1個
・ブロッコリー 1/4株
・キャベツ 3枚
・オリーブ油 大さじ1
・塩こしょう 適量
・とろけるチーズ 80g(内半量トッピング)
- ボウルに卵を割り入れ、牛乳とパセリ、チーズを入れて卵液を作っておく。
- 具材を適当な大きさに切り、フライパンにオリーブ油を入れて炒め、塩こしょうをする。
具材がしんなりしてきたら、豆腐を入れて炒め、①の卵液を入れたらサッとかき混ぜて、耐熱容器に流し入れる。
③途中、オーブンに180℃ 18~20分で予熱を入れておいたところに②の容器を入れて、お好みの焼き加減で焼いたら、できあがり!

もちろん、フライパンで焼き上げることもできますが、
私の場合は、オーブンに入れてしまうと手が空くので、オーブン焼きがラクです~♪
卵液に入れる具材は、冷蔵庫内にあるもので何でもOK!です。
ご家庭のお好みの【スパニッシュオムレツ】をぜひ見つけてみてください。
やっぱり!★“塾デリカ”
2023年新年度がスタートしています!
“やっぱり!”、お馴染みとなってきている“塾デリカ”もスタートです。
“塾デリカ”とは、「学びにも体にもよいお食事をお届けすること」をコンセプトに、
『一汁三菜』を基本とした、成長期のお子様に必要な栄養素や学びに必要なビタミンなどの栄養を含む10~15品目の食材を使ったバランスの良い食事&温かいお味噌汁付きでお届けする‘お弁当’です。安心・安全な食材はもちろん、無添加に近い天然素材の調味料にこだわった、カラダにやさしくて頭にも良いものを提供し続けているのが“塾デリカ”なのです。
『一汁』は、こだわりのある出汁(アゴだしや昆布だし等)から作られている‘だしの素’を使い、甘味のでる野菜を煮込んで作るカラダの芯からホッ!とできる一品として提供している人気の味噌汁です。本当にお子様たちは、味噌汁が大好きなんですよ~♪
「お変わりが欲しい人?」って聞いたら、いつも、結構たくさんの手が挙がります。
温かいお汁付きが、“塾デリカ”の人気のひとつかもしれません。
『三菜』は、毎回10~15品目の食材を使用した‘メイン&副菜’で構成されていて、体力&脳力、精神面も強化できることを目指した、塾ならではのこだわりのあるものに仕上がっています。そして、いろいろな野菜を召し上がって欲しいので、野菜が豊富に使われていることは“塾デリカ”ならではの自慢のひとつにもなっています。

1日のメニューコースは、魚や肉がバランス良く組み込まれている『一汁三菜』を基本とした【応援デリカ】、そして、栄養バランスが瞬時に摂り込めて、ガッツリ!と食べていただけるように考えられた丼ものを基本とした【のっけデリカ】となっています。

昨今は、簡単に食べられるデリカメニューが人気のようで、
パンメニューが、充実してきています!
‘チキンバーガー’に‘カツサンド’、‘クロワッサンテリヤチキンサンド’、‘ホットドック’に‘焼きそばパン’等々、
なかなかのラインナップです。
また、単品シリーズとして、こちらもワンハンドで食べられるように‘国産鶏肉’を米油で揚げた【唐揚げ棒】と、【旬の果物】がありますよ。【旬の果物】は‘旬のフルーツ’が基本となりますから、プラスαすることで、免疫力を強化することもできて風邪予防や疲労回復には欠かせない1品となり、人気のヒミツかも!?しれません~♪
そして、毎月1回は、白石学習院専属食育インストラクターの私から受験生の皆さんに向けてのエール(!?)としての、“スペシャルメニュー”を提供させていただいています。
脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けてのゲン担ぎや縁起物など、大神家の子どもたちが喜んで食べたものなどがメインになっている大神さん家のスペシャルメニューとなっていますので、お楽しみに~♡
“塾デリカ”の中でも、長年不動の人気を博しており、栄養がしっかり摂れて、なおかつガッツリといただける【豚肉ののっけごはん】があります。【のっけデリカ】の中でもリクエストが多いので、いつも“塾デリカ”を提供してくださっているハーストーリィーハウスデリキッチンの主婦シェフさんにレシピをお伺いしてみましたので、お家でもチャレンジしてみませんか。きっと、お子様の「おいしい~♪」の声が聞こえてくると思いますよ!

【豚肉ののっけごはん】 2~3人分
・豚バラ肉 500g
・炒め油 適量
- ざらめ 100cc
~無い場合は少しでもコクの出る三温糖・キビ砂糖がいいかも。
- しょうゆ 75cc
- 酒 40cc
- 水 125cc
・生姜 100g~(すりおろし):スーパーで売っている1袋分を全部使います。
①豚肉を炒め、ザルにキッチンペーパーをひいたところに上げて油をしっかり切ります。
②●の調味料を鍋に入れ、グラグラと少しトロミが出るまで煮詰め、そこに生姜と①の豚肉を入れて、サッと火を通してできあがり!
*ごはんの上に茹で野菜(今回は、茹でたほうれん草)等をのせ、豚肉をのせてお好みでマヨネーズの線引きトッピングで召し上がれ~♪
時には、無理のない食卓に!
1月は行ってしまい、2月は逃げて、早いもので3月がやってまいりました!
寒い時があるとは言っても、学校の様子や行事、お子様たち周辺の出来事や、街中のどことない雰囲気は春の気配が漂っています。先日も、お花屋さんの前を通った時、梅や桜の枝ものがたくさんあって、しっかりと春を感じてしました。
それでも、日々にお疲れの私たち。毎日、元気に走り回っているお子様たちだって、お疲れモードの時もしばしばあるんだと思います。そんなお子様のご機嫌を伺いながら、ごはん事をするのもうんざり~の事も、また、疲れて何も作りたくない日~の事も多々あるはずです。
そんな時だからこそ、「無理なく料理をして、後は楽しく食卓につく」「食卓にみんな一緒について、ゆっくり会話をしながら食べる」のはいかがでしょうか。
我が家でもピークで子どもたちが忙しかった当時、そんなお疲れモードの時に、しばしば登場していたのが、ホットプレートを使った鉄板料理です。材料だけ準備して、食卓で、みんなで作るパターンです。焼きそばや瓦そば、ビビンバ、チャーハン、餃子etc.手抜きもいいとこですが、そんな日は子どもたちとのんびり会話ができ、〇○パーティー!~、と楽しんでいた記憶があるんです。
忙し過ぎた1月、2月は終わり、新しいことが始まるこの時期だからこそ、時には少しののんびりムードでお子様と向き合ってみることのちょっとした提案です~♪
そんな時、【タコライス】のメニューは、いかがでしょうか!
【タコライス】とは、メキシコ料理の「タコス」が「ライス」になった沖縄の定番グルメです。ミンチ肉を味付けした『タコミート』とレタスやきゅうり、トマト、チーズなどをごはんにのせたファストフードです。
『タコミート』だけ作って、後は食卓で、ビュッフェスタイルでいただきます~♪
お子様たちも、自分で取って作りながら食べるビュッフェスタイルなので、案外喜んで食べてくれると思いますよ!

【タコライス】 3~4人分
・温かいごはん 3~4杯分
・レタス 1/4個(150g)
・きゅうり 2~3本
・トマト 大1個(150g)
・ピザ用チーズ 適量
★10分で『タコミート』
・豚ミンチ 600g (合挽でもOK!)
・オリーブ油 大さじ1
・塩 3つまみ
・チリパウダー 大さじ1 (カレーパウダーでもOK!)
・粗挽き黒こしょう 適量
・ケチャップ 大さじ2~3
①レタスは細切り、きゅうりは斜めスライスして千切りにする。
②トマトは食べやすい大きさに角切りにして、チーズも含めて各々を器に盛っておく。
③『タコミート』を作ります。
フライパンに、オリーブ油入れて、ミンチを炒める。その時塩をふっていためる。
チリパウダーを加えて炒め、ほんのり香りが出てきたら、黒こしょう、ケチャップを
混ぜ炒めたらできあがり!
ビュッフェスタイルなので、みんな各々で盛り付けて、いただきます!
お好みで、アボカドや玉ねぎスライス、目玉焼きetc.具材はお好みで増やしてOK!です。楽しい食卓にしてみてくださいね~♪
【チョコフォンデュ】でチョコレートパワー
この時期、何かと目にすることの多いチョコレート~♡
目にもココロにもスウィートな幸福感をくれるチョコレート!普段何気無く食べているチョコレートですが、そんなチョコレートには、驚くべき健康効果が続々と報告されていることをご存じですか(!?)

最近では、美味しくてカラダにも良い‘健康チョコレート’というようなものもたくさんお目見えしています。
なぜなら、昔々、チョコレートは薬として重宝されていたのだとか!
実は、チョコレートに含まれるカカオ成分には、傷の回復を早めたり、免疫細胞を活性化させたりと、健康や美容面にも効果があるようです。
元々は「薬」だったチョコレート。そのためか、‘神の食べ物’とされていたそうです。
チョコレートって、甘いお菓子のイメージですが、元々はカカオ豆をすり潰した飲み物だったそうで、その歴史は紀元前の古代文明の頃まで遡るのだとか。チョコレートが伝えられたヨーロッパでも「薬」として利用されていた記録書が残っていて、今のチョコレートとはだいぶ違うものだったようです。それをスウィートな現代のようなチョコレートにするため、カカオから抽出される脂質‘カカオバター’をたっぷり加えることと、糖分をたくさん加えることから、高カロリーな食べ物となりました。
そして、チョコレートにはカラダに嬉しい成分がたくさん含まれています。
ポリフェノール(抗酸化作用、老化防止)、テオプロミン(大脳を刺激して記憶力、集中力を高めて気力をアップ)、ブドウ糖(脳にとって最も効率のよい栄養)、食物繊維(便通改善、肌荒れ防止=元気な腸に!)、ビタミン・ミネラル(身体を安定させてくれます)など!そして、“免疫調節作用”もあるようです。
「疲れた時には、チョコレートが食べたくなる」「チョコレートを食べると落ち着く」などと言われますが本当かもしれませんね。
ということは、【チョコレートは受験生の強~い味方!】になってくれるかもしれません。
<チョコレートのメリット>
★ストレスに強くなる
★チョコレートには集中力・記憶力を高める効果が!
★チョコレートには良質のミネラルが豊富
★チョコレートは体内ですぐにエネルギーにかわるetc.
<チョコレート~オススメの食べ方>
★勉強や仕事の合間に!
★ココロ&カラダが疲れた時。
★健康のために(カカオ比率が高いチョコレートがオススメ!)
★非常食に(持ち運びがしやすく、高エネルギーなので)
★温めると、効果アップ
そこで、ひと手間ですが、チョコレートを温めて、ウイルスに負けない、風邪予防にもなるビタミンC豊富なお好みのフルーツをしっかりカラダに取り込めるように、冬の時期を健康的に乗り切るための【チョコフォンデュでフルーツ】はいかがでしょうか!
キウイにいちご、バナナ、オレンジ、りんごetc.何でもOK!です。フルーツをたっぷりと使って、健康効果がパワーアップする食べ方が、冬に食べたくなる甘いチョコレートと一緒に取ること!冬を元気に乗り超える効果が期待できるという、“ホットチョコ”なんですって。特に、【キウイ】は、冬の時期に栄養満点で美味しくなり、ビタミンCがレモンの4倍、食物繊維がバナナの3倍含まれるそうです。選ぶ時には、やや平べったいものがいいそうで、幹に近い【キウイ】ほど平べったくなり、栄養たっぷりで美味しいということです。

【チョコフォンデュでフルーツ】
・板チョコ 2枚
・牛乳 大さじ4
・お好みのフルーツ 3~4個
~キウイ、いちご、りんごを使いました!
①耐熱ボウルに板チョコを刻んで入れる。
(今回は「DARS」を使ったので、そのままで!)
②①に牛乳を加えて、レンジ600wで40秒加熱する。
③取り出して、よくかき混ぜて、再びレンジ600w40秒加熱して、チョコソースの完成です。
④キウイをしっかり水洗いして、皮付きのまま輪切りにし、耐熱皿にのせてラップをしてレンジ600w40秒加熱する。
*キウイを加熱すると酸味が減り、甘味がアップします!
その他のフルーツは、いつもの食べる状態で提供します。
⑤【チョコフォンデュ】を付けて、お召し上がりください~♪
ご褒美用でお子様が大好きなクッキー、マシュマロetc.を準備して、お子様のテンションも
爆上がり間違いなしにしちゃいましょう♪
元気パワー飯=「小豆がゆ」
月は行ってしまい、早くも2月になりました。
2月3日は節分で、「季節を分ける」ことを意味しています。
いよいよ冬が去り、春の始まりです!
一年の生活が始まる頃、昔は「小豆がゆ」を炊く風習があったのだとか。家族に災いが起こらないようにという願いからだそうです。

‘小豆’は洗って戻さないで、そのまま茹でられる便利な豆です。
‘小豆’には良質なたんぱく質はもちろん、豊富なビタミン類(B1、B2)やカリウム、リン、鉄、食物繊維などが幅広く含まれており、‘小豆’は体調を整えるのに最適と言われています。
これを日本人の主食のお米と炊き合わせることで、糖質の代謝を助けてエネルギーを作り出し、疲労回復に役立ちます。さらに、脳神経を正常に働かせることにも役立ち、ストレスを和らげる働きもします。また、貧血を予防し、抗酸化作用や免疫力を高めるなど最強パワーを発揮してくれるのです。
どうですか~(!?)
邪気払いとしていただくだけの「小豆がゆ」にしておくにはもったいない!と思いませんか。
食べて健康&免疫力アップの「小豆がゆ」は、普段からもっと積極的に食べたい“元気パワー飯”だったんですね。
そこで、普段でも、朝食にも持って来い!で召し上がっていただけるように、‘茹で小豆缶’を使った、簡単な【小豆がゆ】の作り方をご紹介します。小豆の豊かな風味に、ほんのり塩味が効いたお粥です。お餅を入れて仕上げると、腹持ちもいいですよ!お餅を入れると、【ぜんざい】みたいですが、これも先人達の知恵ですね!
ぜひお試しください♪

【小豆がゆ】 1人分
・ごはん お茶碗1杯分(約100g)
・茹で小豆缶 30g ;無糖のもの
・水 200ml
・塩 ふたつまみ
・切り餅 1~2個 ;焼いておきます。
①鍋にごはん、塩、水を入れ強火にかけ、沸騰してきたら弱火にし、茹で小豆を入れて馴染んだら、焼いたお餅も入れてできあがり!
*ごま塩をふりかけたり、三つ葉等青菜をトッピングしてもOK!ですよ。
アレンジお餅でリラックス!
年始の気分も抜け切れない間に、いよいよ受験本番です!
ガッツリのお勉強モードではありですが、心と、そして脳内も少しだけ、ほっこり!リラックスモードで体調を整えていく方にシフトするのもありかもしれません。
つい最近までお正月だった事がウソのようですが、お餅は余っていませんか。
お餅は、お雑煮や焼き餅、きな粉餅だけではありませんよ~。余ったお餅はアレンジ自在、アイデア次第です。アイデアレシピで、受験生のお子様の腹ごしらえになるよう、楽しんでみませんか。

【クリームチーズの磯辺焼き】 4個分
・お餅 4個
・クリームチーズ 2ブロック
・海苔 4枚
- しょうゆ、みりん、砂糖 各大さじ1
①お餅、クリームチーズを横2等分に切っておく。
②オーブントースター(1000w220℃)で4~5分焼く。
③フライパンに●を合わせて、弱火で熱し、②のお餅を入れてひと煮立ちさせて絡める。
④③のお餅を取り出し、クリームチーズをはさんで、海苔で巻いたら完成です。
*クリームチーズでたんぱく質が強化され、海苔で巻くことで塩味も加わり食べやすくなります。(もちろん、ミネラルで体調管理にもOK!です)
おまけに腹持ちもアップします~♪

【切り餅で手作りあられ】
・お餅 適量
~我が家は子供の勉強机にお供えをしたお鏡餅を切って使いました。
・揚げ油 適量
- きな粉 大さじ2
- 砂糖 大さじ2
- 塩 小さじ1/2
①お餅は1㎝角になるように切る。
②揚げ油で、①を180℃3分程度揚げていく。
(やわらかくなってきたら、プク~っと裂けて膨らんできます!)
③②の油を切ったら、ボウルやビニール袋等に合わせておいた●の中に入れていき、
温かい内にまぶしたらできあがり!
*もちろん適量の塩のみでまぶしてもOK!ですが、きな粉を使うことで、やっぱりたんぱく質の強化になりますよ~!
寒い毎日が続きますから、カラダを温めながらリラックスできる、たんぱく質強化のレシ
ピになるよう、紹介してみました。
普段の日常でのほっこりエピソードとともに、お餅のアレンジレシピで心&カラダもリラックスしながら頑張りましょう!
【冬野菜】でカラダを温めよう!
「寒い~っっ!」、そんな毎日が続きす。
まだまだ気の抜けない本番真っ只中の受験生の皆さん!
“寒い、寒い”を我慢してしまうと体温と共に、免疫が下がってしまいます。免疫が下がるとウイルスに対する抵抗力も下がってしまいますから、体調を崩してしまいがちに~。体調を崩すと大変な時期です。
そこで、意識したいのが<何を食べるか!>です。冬はカラダの活動力が落ち、冷えからくる様々なカラダや心の不調を招きやすくなると考えられているため、それを補うために冬の食事で、積極的に取り入れたいのが“カラダを温める”【冬野菜】です。
寒い季節ならではの栄養満点で、“カラダを温める”作用のある【冬野菜】の出番です。
【冬野菜】の中でも、
「温」の野菜=かぼちゃ、白菜、かぶ、ニラ、白ねぎ、etc.
「熱」の野菜=ニンニク、生姜、唐辛子、etc.
特に、上手に使いたいのが、温める作用の強いニンニクや生姜などの「熱」の食材。
調理に少し加えるだけで、美味しいだけでなく、カラダが温まる効果も高まりますよ。
ぜひ、取り入れてみてください~♪
今回は、冷蔵庫に残っていたり、少しの【冬野菜】でも、作って栄養が取り入れられるように、【冬野菜】の代表格である“白菜&かぶ”を使った簡単レシピと、本当に体内からポカポカになる“かぼちゃ”を使ってスープにしてみようと思います。
“白菜&かぶ”には、ビタミンやミネラル、食物繊維などがバランス良く含まれていて、
特に“かぶ”は淡色野菜と緑黄色野菜(葉っぱの部分です)の両方を併せ持つ栄養素のカロテンやカルシウム等が幅広く含まれているため、受験生にはとっても大切な呼吸器系の健康を守る働きや風邪予防、食欲不振や疲労回復にも効果的なのだとか。
そして、“かぼちゃ”は、抗酸化作用がバッチリのカロテンを含みますし、ポタージュにする時に一緒に使う“白ねぎ”には(あっさりと仕上がるんですよ!)抵抗力を強め、風邪予防に最適なビタミンCが豊富に含まれています。
これから、まだまだ厳しい寒さになることが予想されます。
受験当日には衣類などでしっかり防寒対策をすることはもちろん、常日頃からの“カラダを温める”食事で、手抜かりなく乗り切って、『合格』を手中に収めてください!!

【かぶの味噌炒め】 3~4人分
・小かぶ 8個
・しめじ 1/2株(あれば!でOK、砕いておきます。)
・生姜 1片(千切り)
・油 大さじ1
- 味噌 大さじ1と1/2
- 砂糖 大さじ1
- 醤油 大さじ1/2
- みりん 大さじ1/2
- 和風だし 大さじ1/2
・鰹節 1パック(小分け用)
①かぶは洗い皮をむき、串切りで6~8等分にする。葉っぱの部分は食べやすい大きさに 切っておく。
②フライパンに油をひき、千切り生姜を炒めて香りが出てきたら、①を入れて炒める。
*少し焦げ目が付く程度が美味しいですよ!
③●を混ぜ合わせておいて、②に入れて柔らかくなるまで炒め、最後に鰹節を入れてサッと混ぜ合わせたらできあがり!
☆大きなかぶの場合は、少し出汁で煮てから調味し、炒め煮にすると軟らかくなります!

【かぼちゃのポタージュ】 2~3人分
・かぼちゃ 小1/4個(約200g)
・白菜 4~5枚(約200g)
・白ねぎ 1本位(約80~100g)
・にんにく 1片(みじん切り)
・バター 15g
・牛乳 300~400ml(お好みの濃さで!)
・塩こしょう 適量
①かぼちゃは一口大にカットし、レンジ500~600wで8~10分加熱しておく。
②白菜、白ネギは、ザク切りにする。
③鍋にバターとにんにくを入れて香りが出るまで炒め、①②と塩小さじ1/3程度を入れて炒め馴染ませる。
④③に牛乳を半量くらい入れて、やわらかくなるまで弱火で煮たら火を止めて、粗熱を取りミキサーに入れて撹拌する。
⑤④を鍋に戻し、残りの牛乳をミキサーで回し(ミキサーに残っているペーストのお掃除です!)、それも鍋に移して熱していきながら、塩こしょうで味を調整したら完成です。
*盛り付けた後、生クリームでトッピングしたら本格的になりますし、生クリームを煮込みに使ってもポタージュ感が増していきますよ~♪
【松ぼっくり】で気分転換(!?)
12月になると、心もソワソワしてくるようなクリスマスが街中に溢れてきます。
イルミネーションやクリスマスケーキ、サンタクロースにクリスマスプレゼント、お勉強に頑張っている受験生の皆さんには、誘惑がいっぱいです!
そんな時は、少しだけ気分転換をしてみませんか!
普段、何気無く食べているチョコレートですが、疲れている時などに、妙に食べたくなってしまいます。まさに、チョコレートを食べて気分転換です~♪チョコレートを食べて気分転換だけでなく、実は、健康効果にも良いという報告も続々と挙げられています。
チョコレートに含まれるカカオ成分には、傷の回復を早めたり、免疫細胞を活性化させたりと、美容・健康にも効果的なんだそうですよ。
また、カカオ成分には、カルシウムや鉄分、マグネシウム、亜鉛などといったミネラルがバランスよく含まれています。そして、カカオプロテインといわれるものが、‘食物繊維’と同じような働きをしてくれるおかげで、腸内環境が改善され、便秘解消や免疫力の向上にもつながるとか!
それから、ここが一番のポイント!!
チョコレートの甘い香りには、集中力や記憶力を高める効果があるということも、脳波や学習実験から実証済みで、神経を鎮静させる作用やリラックス効果を呼び起こしてくれる作用があるとのことです。
そこで、チョコレートを食べながら気分転換ができ、ちょっぴりクリスマスの気分も味わえるように、チョコパイとチョコフレークを使って、クリスマスのオーナメントに登場する【松ぼっくり】を作ってみませんか~。レンジで簡単にできるので、少しだけクリスマスの準備をした気分が味わえるはずですよ~♪

【クリスマスの“松ぼっくり”ケーキ】 5個分
・チョコパイ(大) 4個
・牛乳 大さじ1
・チョコフレーク 適量
・粉砂糖 お好みで
①レンジ対応のボウルの中に、チョコパイを袋から取り出し、崩していく。
*小さいチョコパイを使った場合、チョコパイ2個で3個の“松ぼっくり”ができます!
②①に牛乳を大さじ1程度加えて、レンジで20秒あたためる。
③ムラが無くなるまで、混ぜ合わせる。~柔らか過ぎたら冷蔵庫に入れ冷やします!)
④【松ぼっくり】の芯を作る!~③の生地を5等分に分けて、ひとつ分をラップに包み、しづく形を作っていく。
⑤④で作った芯に、【松ぼっくり】をイメージして、チョコフレークをさしていくと完成です~♪
お好みで、粉雪に見立てて粉砂糖を振ってもOK!
★チョコパイとチョコフレークですから、美味しいお味は太鼓判!
★ランダムに、チョクフレークをさしていっても、
【松ぼっくり】っぽくなるので、ご心配なく!

楽しく気分転換ができたならば、嬉しいです。
MERRY CHRISTMAS!
“おでん”でパワーアップ!
12月に入り、寒さが増して来ました!
寒~い時期になると、熱々の“おでん”はとても魅力的!
こんにゃく、がんも、大根、ちくわ、厚揚げ、はんぺん、玉子等々、お好みの具材は何ですか?
今年も猛暑が続いた夏でしたが、冷房や冷たい食べ物や飲み物の取り過ぎ等で、今の時期、思いの外カラダだけでなく体内もダメージを受けているのだとか。そんなカラダに“おでん”は食べるべきパワーがたっぷり!らしいのです。夏の疲れは、免疫力の低下としてまだまだ残っているらしいとのこと。免疫力の低下は、受験生にとって大敵のコロナやインフルエンザ、その他ウイルスの感染症等にかかりやすくなってしまいます。
そんなカラダが熱々の“おでん”に「食べたい!」と反応するのは、“おでん”がカラダの防御機能に最適だから~、かもしれません。
実際、コンビニで売られている“おでん”が一番よく売れるのが、11月から12月初旬なんだそうですよ。
ちなみに、“おでん”の人気の具材は、
①大根 ②玉子 ③こんにゃく ④ちくわ ⑤はんぺん&がんもどき!
この他にも厚揚げや餅巾着などがありますが、豆腐を使った具材が多いのが、“おでん”パワーのポイントのようです。
純度の高いたんぱく質の吸収が、ウイルスと戦う免疫力を司る小腸をガードしてくれること、そして、これらの各単品の具材が、“おでん”にすることで、相乗効果からパワーアップし、カラダの防御機能もアップするんだそうです。

そこで、相性の良い具材を食べ合わせてパワーアップ!する、食べて欲しい“おでん”の具材を5位から発表です。
⑤【ちくわ】
魚肉たんぱく質(=スケトウダラ‘白身魚’)はたんぱく質が凝縮されているため、腸からの吸収に優れ、ウイルスと戦う抗体を作ります。
“おでん”で食べ合わせるとより効率良くたんぱく質を吸収できる食材が【じゃがいも】【白米】。ビタミンB群の吸収率をUPさせ、良質なたんぱく質に変化します。
湯通しした後、入れて煮込むと塩分減になりますよ。
④【がんもどき】
良質なたんぱく質に刻んだ野菜‘人参や枝豆、ひじき等’が入っていて、腸の機能を高めるオリゴ糖(腸内の善玉菌を増やす)も含まれるため、ウイルスと戦う力が増すだけでなく、エネルギーに変わり免疫力がアップします。【がんもどき】は鉄分やビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップします。オススメは【ブロッコリー】!ビタミンCが豊富なので血の流れを活性化します。
③【ロールキャベツ】
野菜類が少ないと思われがちな“おでん”の中で、【ロールキャベツ】は免疫細胞活性化の機能を高める「ビタミンの宝庫」。ビタミン類を一気に取れる新食材です。
出汁に溶け出したビタミンCなどが、味の浸み込みやすい栄養素を吸収する具材に混ざり込んでいくようです。オススメの食材は【大根】で、ぜひ一緒に食べたい一品です。
②【昆布】
【昆布】の食物繊維がウイルスから守る小腸をガードします。小腸の粘膜にバリアを張り、ウイルスの増殖を抑えます。“おでん”出汁にはたっぷりの食物繊維が溶け出しているので、その栄養素を吸い込んだ【こんにゃく】や【牛すじ】は食べ合わせたい具材のひとつ!【こんにゃく】はカルシウムやミネラルが効率よく吸収され、【牛すじ】はコラーゲンが豊富なため、骨を丈夫にするパワー(骨量・骨質)に持って来いなのだそうです。
さらにパワーアップさせたい場合は【とろろ昆布】のトッピングがベスト!とろろの酢が栄養吸収の促進に効果的で、より免疫力をアップしてくれるそうですよ。
①【玉子】
“おでん”の【玉子】は多くの栄養素を持ったスーパー食材!脳&血管を活性化するパワーが最強なのだそうです。そんな【玉子】の豊富な栄養素に欠けているものが、ひとつ‘食物繊維’。“おでん”で煮込むことで出汁にもなる【昆布】が補い合い、腸をも守る最強【玉子】に変身します。
冬に“おでん”が食べたくなるのは理に適っているんですね~。
免疫細胞の約70%は小腸に集中しているため、小腸を維持する食材の種類が豊富なだけでなく、“おでん”には様々な栄養素が含まれているということです。
免疫力アップに欠かせない栄養素は、たんぱく質、食物繊維、ミネラル、カルシウム、ビタミン(A・C・E・B2)です。出汁=つゆを介してコトコト煮込み、浸み込んでいくことで、他の食材が吸い込むこれらの栄養素で、どの具材を食べてもいろいろな栄養素がバランス良く取れるということなんです。
“おでん”のお出汁は、ぜひご家庭のお味でどうぞ!
60~70℃の中火でコトコト40~50分煮込むのが美味しい“おでん”の作り方!
沸騰させると栄養素が壊れてしまうので要注意!です。作ったその日に食べた方が栄養素のビタミンCが崩壊されずにきちんと取れるそうですよ。具材はその日に、出汁はそのまま利用するのがベストな“おでん”作りのポイントなんですって。
食べたくなってきました~♪今夜は早速、“おでん”です。(笑)
スナック感覚で~♪【白身魚のフリット】
最近はお天気にも恵まれ、お昼間はしのぎやすい日が続いています。
朝夕は寒くなってきて昼間は暖かい、なんだか今年は秋の季節がしっかりとあるように感じています。
気分転換に、散歩やピクニック等、外で思い切りカラダを動かしてみたいそんな気分にもなってしまいます。でも、せっかくお勉強に頑張っておられるお子様方ですから、そんな誘惑はダメですかね~。
そんな気分だから、今回はスナックぽい【フリット】のレシピを紹介したいと思います。
気分だけでも軽く、スナック感覚でパクパク食べてもらいながらも栄養が摂れる、そんな軽めだけど、脳活にもバッチリな【魚】に焦点を当てた、魚メニューにしてみました。
言わずと知れず、【魚】に含まれる『DHA』=ドコサヘキサエン酸は脳に欠かせない大事な栄養素で【不飽和脂肪酸】のひとつです。これは【魚】にたっぷり含まれ、脳細胞の再生に必要だとも言われており、認知機能の向上、記憶力や学習能力の向上を促進するのに役立つということで、脳のメカニズムを支えると言われています。
【魚】が脳に良い食材=‘ブレインフード’と言われる所以です!
最近では、‘三大栄養素’のたんぱく質・炭水化物・脂質はしっかりと摂取されているとのことですが、問題はそれらが体内でうまく機能していないことだと言われています。
食べ物の栄養素を分解し、必要なものに作り変えて代謝させ、活性化されることで、初めて栄養素が意味を持ってきますから、【魚】が持っている『脳活栄養素』を活性化させるためにも、まずは‘魚料理’をお子様にしっかりと食べてもらうことがポイントとなってきます。
ということで、おつまみやおやつにも嬉しい、おまけにお弁当にもバッチリな、外はカリッと中はふんわりの【白身魚のフリット】のレシピです。白身魚は淡泊な味わいのため、揚げ物にすることでボリューム感が出て、美味しくいただけます!おまけにエネルギー量がアップしますから、これから寒くなってくるカラダにも強~い味方になってくれますね♪

【白身魚のチーズフリット】 2人分
・白身魚の切り身 2切れ
・塩こしょう 適量
・薄力粉 小さじ2
- 薄力粉 20g
- ベーキングパウダー 2g
- パルメザンチーズ 5g
- 溶き卵 1/2個分
- 牛乳 10g
・揚げ油適量
①白身魚は骨なし皮なしのカレイを使いました。1切れを食べやすい大きさにカットし、塩こしょう、薄力粉を塗しておく。
②●をすべてボウルに入れて、フリットの生地を作る。
③揚げ油を170℃くらいに加熱して、②の生地に①の切り身をスプーン2本を使ってくぐらせて、中火位をキープして油で揚げていく。
~*ネットリとした生地なので、付け過ぎに注意です!
④すぐに膨れてくるので、転がしながら中まで火が通るように、色付くまで揚げていく。(4~5分位)
⑤お好みでケチャップ等を付けながらいただきます♪
★薄力粉+ベーキングパウダーの部分をホットケーキミックスに置き換えてもOK!です。(もっとスナックぽい感じになります。)
ほっこり気分!で【あんまん】
11月になった途端、朝晩一気に寒くなってまいりました。
急に冷え込んで来て、あっという間に秋の気配!~と言うよりも、朝夕の寒暖差が大きくて、それにカラダが追い付いていかない感じです。
こんなに寒暖の差が大きいと体調を崩すばかりでなく、「元気が出ない~」「だるい…」と感じる事が多々あります。大人ばかりでなく、お子様だって、集中力が続かない、不安定感が強い等々、「元気が出ない~」精神的にもお疲れモードの時ってあるはずです。
‘集中できない’‘頭が働かない’~などスランプ感もあるような、あと少しの頑張りがとても長く感じられてしまう11月の時期ではないでしょうか(!?)
ずっと頑張っているお子様だからこそ、‘何だか疲れてしまう’のかもしれません。
そんな時のお勉強をスムーズに(?!)進めるためにも、疲労回復&気分転換は大切ですよね。そして、こんな時って、温かくてほっこりできるものが、食べたくなりませんか~♪私だけ~~(!?)
人間のカラダは、冷えや血の不足によっても、このようなことが起こるとされているようで、『秋バテ対策』にも通じるところがあるのですが、冷えを軽減することの“じんわりの温め&リラックス効果”が大切のようです。カラダも精神的にも忙しい、あともう一息の今だから、時には‘ほ~っこりの気分転換’は大切かもしれません!
そこで今回は、お疲れ脳に糖分を与えつつ、ほっこりとしながら食べられるイメージの【あんまん】はいかがでしょうか!
コンビニ等の店舗のレジ前に置いてあったりして、妙に食べたくなってしまいますよね♪私だけ~~(!?)
「元気が出ない~」時こそのエネルギーチャージに持って来い!のカラダ&心も温まる【あんまん】です。簡単にホットケーキミックスで作りますよ~♪

【あんまん】 小8個くらい
- ホットケーキミックス 1パック(200g)
- 水 70~80ml
- サラダ油 大さじ1
・こしあん 100g
①ボウルに●を順番に入れて、手で混ぜながら、粉っぽさがなくなるまでこねてまとめる。
②①のボウルにラップをして、しばらく置いておく。(温かめのところがいいですよ!)
③こしあんを等分に分けておく。(丸める必要はありません)~*こしあんは市販のものでOKです!
④②の生地を等分に切り分けて、丸め、手の平に広げて、③のこしあんをスプーンですくい、生地にのせて包んでいく。(パラフィン紙があればひとつずつのせ、無ければクッキングシートに等間隔に並べていく)
⑤蒸し器でお湯を沸騰させ、④を並べた蒸し器の上段をセットして、フタをしたら中火で約15分加熱する。(水滴が多いとNGなので、フタに布巾で覆う等をするといいですよ!)
⑥生地を指で押して戻ってくるようなハリ感があれば、完成です。
蒸し器は面倒くさい感じですが、ゆったりと立ち上る湯気でこの時期ならではのほっこり感が味わえますよ~!
じんわりの温かさ&リラックスできるほっこり気分で食べることは、やっぱり<元気の源>だな~♪、と感じます。
ハロウィンの塾デリカスペシャルメニュー
『学びにも体にもよい食事をお届けすること』をコンセプトに提供させていただいています『塾デリカ』!お子様のお役に立てていただけていますでしょうか?
『一汁二菜』を基本とした、成長期のお子様にとっての必要な栄養素や、学びに必要なビタミンなどの栄養を含む10~15品目の食材を使ったバランスの良い食事&温かいお味噌汁付きでお届けする‘お弁当’です。
その中に毎月、スペシャルメニューがあるのをご存じですか。
白石学習院専属食育インストラクターである私大神が考えた、特別な1日限りのスペシャルメニューです。脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けての応援メニューなど、大神家の子どもたちが喜んで食べたものなどがメインとなっているスペシャルメニューです。
今月10月のスペシャルメニューは、少し趣向を変えて、お楽しみバージョンの行事食で考えてみました!
“行事食”とは、「お正月」や「七草粥」、「節分」、「おひな祭り」や「子供の日」、「七夕」、「お彼岸」や「お月見」「クリスマス」etc.1年の間にある様々な行事にはコレを食べるよね~!とか、この季節には、これを食べるよね!いった定番になっている食事のことです。
これらの“行事食”には、しっかりとした由来があるものも多く、大人でも意外と知らなかったりしますから、込められた意味を調べてみて、お子様に伝えていくのも楽しいかもしれません♪
さてさて、10月の“行事食”は何でしょうか!?
今では、仮装したり、お菓子をもらったりする風習が根付いてきた感のある「ハロウィン」に注目してみました~♪かぼちゃをくり抜いた‘ジャック・オー・ランタン’や魔女やゴースト、ドラキュラなどが連想されるアメリカのお盆とも言われている「ハロウィン」です。
でも、仮装して、ハロウィンの合言葉の『Trick or Treat』を言ってお菓子をもらい、かぼちゃを食べる事くらいで、コレと言った定番食もない感じなので、ハロウィン限定の【ハッピーハロウィン【魔界めし】】を考案してみました~!
【魔界めし】とはおどろおどろしいネーミングですが、ハロウィンをイメージした黒~い色のいかすみソースを使った野菜たっぷりの【そばめし】なんです。
そこはハッピーハロウィンですから、食べたらきっと美味しい!って言ってもらえるはずです。塾デリカのスペシャルメニューの日は、『Trick or Treat』って言ってみて~♪
おたのしみゼリーも付きますよ!

10月31日の夜はご家庭でもぜひ~♪
ということで、今回は【魔界めし】のレシピを特別にお教えしちゃいます。(笑)
【Happy Halloween★【魔界めし】】 2~3人分
・ごはん 1杯分
・焼きそば麺 1玉分 ~細かく刻んだもの
・ベーコン(豚バラ肉でもOK) 80g
<野菜の具材>
赤パプリカ・たまねぎ・ブロッコリー・しめじ
ニラor青ネギ・キャベツ etc. ~各々みじん切り
・オリーブ油 大さじ1~2
・塩こしょう 少々
・料理酒 大さじ1
<黒いソース>
・焼きそばソース 大さじ2
・いかすみソース 大さじ3
①フライパンにオリーブ油を入れ、みじん切りにした野菜を炒め、料理酒を入れて野菜がしんなりしたら、ベーコンを入れてさらに炒める。
②ごはんと麺を入れ、パラパラになるまで炒めた後、<黒いソース>を混ぜ合わせ、塩こしょうで調味したら、完成です。
*いかすみソースは、‘S&B‘LA BETTOLA“予約でいっぱいの店のいかすみソース’を使用しました。
*ハロウィンといことで、スライスチーズをコウモリ型に抜いたものをトッピングしています~♪
旬の食材で秋バテ対策!
今年の夏のような酷暑が続いた後、朝夕がしのぎ易くなってくるとどっと疲れがでてくるのか、カラダの不調を感じている人はかなりの数になるのだとか!
不調の種類としては、「だるさ、倦怠感」が半数以上で、「疲れがとれない」「疲労感」「冷え」「発汗」「胃腸の不調」「頭痛」「睡眠不調」等、様々のようです。
原因としては、‘暑さ’に続き‘屋内と屋外の気温差’‘冷房による冷え’‘冷たい飲み物や食べ物の摂り過ぎ’が多数で、このように夏以降の不調は猛暑の影響やその回避からの弊害で、“冷え”が一番の問題のようです。
夏の間に冷房や冷たい物の摂り過ぎでカラダを冷やしてしまったことによって、自立神経のバランスが乱れて、秋になって不調が出てきてしまい続いてしまう、ということのようです。いわゆる、これが「秋バテ」!
そして、近年はこの「秋バテ」を訴える人が夏バテ同様に増加しているらしいのです。
猛暑で夏の間バテてしまったカラダを放っておくことで、深刻な「秋バテ」につながってしまいかねないので、要注意です!
「秋バテ」対策は<じんわりの温め&リラックス>♪
① 「秋バテ」対策には、カラダを“じんわり温める”ことで、血のめぐりを良くし、疲れやだるさ、コリの蓄積を防ぐことが大切です。さらに、副交感神経が優位になるような“リラックス”法で心と身体をゆっくりと休ませるのがオススメです。
お風呂もシャワーだけでなく、ぬるめのお湯(38℃~40℃くらい)にゆっくり入り、全身を温め、血のめぐりを良くしましょう。血のめぐりを良くする炭酸入り入浴剤を活用すると身体の芯まで温められます。
② カラダを温める食べ物の食材で「内臓冷え」の緩和
色の黒っぽい食べ物(食材)、濃い食べ物は体を温めると言われています。また、地下でエネルギーを蓄えた食べ物も体を温める働きがあるとも言われます。寒い地方で産出された食べ物=秋~冬が旬の食材には、これらが多く含まれていますから、旬の食材の持つパワーはあなどれません。
やっぱり、旬の食材が持つパワーって、すごい!のですね~♪
「冷え」が原因の、体調不良=「秋バテ」を緩和する働きが<大>なのが、秋が旬の食材=いも類・栗(ナッツ類)・南瓜・根菜類など。身体を温める効果がバツグンに優れているのです。
主成分がでんぷんで、でんぷんの豊富な食物のいも類や穀物ですが、特に栗のでんぷんは、樹上でとれる浄化された貴重なでんぷんで、熱量は一番なのだそうです。
少量で必要な栄養素をとることができ、少量で効率のよいエネルギー補給食品になるようです。また、ミネラル類も豊富なので『元気ミネラル』とも言われるほど。
さらには、受験生には嬉しい★集中力アップ★やる気が出る★イライラ解消etc.の効果もあるそうですよ~♪
そこで、今回は旬の秋の食材「さつま芋」&「栗」を使った、カラダを温めてくれるレシピをご紹介します。
いつもの!?‘栗ごはん’から少しだけ変わった視点でつくる【栗のポタージュスープ】と甘みがあってほっくり味の【さつま芋ごはん】です。ほっこり~♪気分間違いなしのレシピです。

【さつま芋ごはん】 2人分
・米 2合
・さつま芋 中1本
・塩 小さじ1
・黒入りゴマ 小さじ1
①さつま芋はきれいに洗って、皮付きのまま一口大にカットして水にさらした後、しっかり水切り!
②炊飯器に洗ったお米と水量(2合用)を仕かけ、塩を入れて軽く混ぜて、①のさつま芋を仕かけたお米の上にのせたら、スイッチON!
③炊き上がったら、黒ゴマを混ぜてできあがり。簡単~♪

【栗のポタージュスープ】 4人分
・栗(皮をむいた正味量) 150g
・玉ねぎ&白ネギ(合わせて) 150g
・水 2カップ
・コンソメ固形 1個
・牛乳(生クリームでもOK!) 1カップ
・塩・こしょう 適量
・オリーブ油 大さじ1
①玉ねぎ・白ネギは繊維を断ち切るように薄くスライス、栗は皮をむきます。
②鍋に、オリーブ油を入れ、ネギ類を入れて、しんなり、少し茶色く色付くまで炒める。この時、塩をひとつまみ入れて炒めると焦げないでしんなりします。
③ネギ類が色付いてきたら、栗を入れて軽く炒め、水とコンソメを入れて中~弱火で栗が柔らくなるまで煮詰めていきます。(10分~位)
④その後、粗熱を取ってミキサーに入れ、なめらかになるまで撹拌していきます。
⑤④を鍋に戻し、牛乳を加えて温めます。味をみて、塩・こしょうをしてできあがり!
*牛乳が入ったら、煮立てないようにするのがポイント!
*玉ねぎのみでもOK!ですが、2種のネギ類を入れると旨味が倍増します。
パワーフードの‘お米’を使って!
‘お米’はパワーフード!
そろそろ新米のシーズンです~♪
‘お米’は炭水化物や糖質というイメージが強いですが、実はその他の栄養素も豊富です。
炭水化物が一番多い割合ですが、ビタミンやミネラル、食物繊維、たんぱく質も含まれていて、同じ炭水化物のパン類よりも脂質が少なく、たんぱく質が豊富なため、たんぱく質源としてよく働くという利用効率が高いんです。さらに、持続力が発揮できる炭水化物の食品ということで、長い時間の運動やお勉強など、カラダや頭を使う時のエネルギー源として働くのが得意なのです。
私達が思っている以上に“お米の栄養”は優れていますので、やっぱり<何といっても日本人は‘お米’!>ということでしょう!
カラダと脳のエネルギー源としての‘お米’ということですが、皆様もご存じのとおり、人間の脳は糖質しかエネルギーとして利用することができません。いわゆるブドウ糖です。
糖質を摂らなければエネルギーが供給されず、脳は活発に活動することができなくなります。おまけに、なんと人間のカラダに必要なエネルギーの50%~70%程度は炭水化物から摂ることが理想とされているそうです。
そして、‘お米’は粒食のため、「しっかり噛める」というメリットがあります。よく噛むということは、前回のコラムでも紹介したとおり、脳を刺激して脳機能をアップし、自律神経のコントロールを促すことはもちろん、唾液がよく出て消化吸収率が上がるので、胃腸をしっかり鍛えて動かしてもくれます。
‘お米’は、カラダと心と脳を活性化させて、持続力と集中力アップにつなげるためには持って来い!の【受験生のパワーフード】です。
そんな‘お米’のパワーを見逃すわけにはいきません。
毎日のご飯で食べていれば良いのかもしれませんが、お子様にも喜んで楽しく、美味しく食べてもらいたいので、“お米のパワー”をフル活用するために、おやつにもご飯(残りご飯でOK!です)を使って、【みたらし団子】を作ってみませんか~♪
9月は、‘中秋の名月’(2022年は9月10日でした~)もあり、これまたパワーをもらえそうなお月様を愛でるには最高の季節です。
お月様の不思議なパワーを、昔の人のように感じながら、【お月見】で日々の感謝を表して心身のパワーもいただいていてみる、そんなお供にも、【ごはんでみたらし団子】はいかがでしょうか。
ご飯さえあれば、素早く作って食べられて、パワーorエネルギーチャージにもなる【みたらし団子】です。

【ごはんで★みたらし団子】
・ご飯 茶碗1杯 ~約15個位のお団子ができます!
(・片栗粉:水 各大さじ1)
<みたらしのタレ>
- 醤油 大さじ2
- 砂糖 大さじ3
- みりん 大さじ2
- 片栗粉 大さじ1
- 水 80~100cc
①タレの●を鍋に入れて火にかけ、よくかき混ぜる。トロミがついたらOK!
*レンジ600wで1分20秒くらい加熱でもOK!ですが、固まるので途中でかき混ぜな
ら行ってください。
②ご飯を温めてボウルに入れ、水で濡らした麺棒でつく。ひと塊になるようにこねる。
*多少潰したら、(水と片栗粉)を入れて、さらについて粒が無くなるようにこねると、綺麗なお団子になりますよ!
③手を濡らして、丸めて団子を作り、タレをかけたら完成です。
*(水と片栗粉)を入れた場合は、沸騰したお湯に入れて浮いてきたら水に取り上げてください。
④③の工程までで、十分【みたらし団子】ですが、テフロン加工のフライパンで、丸めた
お団子に焼き目をつけたら、本格的なお団子になりますよ~♪
★簡単に手抜きでOKならば、‘ご飯をついて丸め、タレをかけるだけ’で、時短で美味しい【みたらし団子】ができあがります。~*は、綺麗により本格的なお団子になる工程です♪
見直したい★噛むこと!
朝夕が、少ししのぎ易くなって来ました~!
しのぎ易くなってくると、今までの怠惰な食生活が頭をもたげてきて、ため息が出てきます。‘ツルツル、ゴクコク’と喉越しの良いものが食べやすかった、猛暑の夏でした!
その所為か、最近、お子様たちが食事の時に、噛んで食べていないような感じが見受けられ、気になっています。
「噛むこと」は、カラダに食べ物を取り入れるだけでなく、全身の健康に大切な働きをしています。例えば、子どもの成長、肥満防止、虫歯予防etc.とカラダに嬉しい効果がたくさんあります。また、「噛むこと」は子どもの顎の発達や歯並びに大きく影響していることが知られている一方で、「噛むこと」によって脳が刺激されて記憶力のアップにもつながっていることも昨今多く報告されています。
実際、子どもの顎の発達や歯並びが大きく影響し、機能的な理由から、咀嚼や嚥下に関わる口腔発達の未発達からくるであろう、‘食材を上手に噛めない、上手に飲み込めない’という、食に偏りがあるお子様を見たことがあります。食べられないもの、あるいは食べないものが多くなる、という【食べない】ということが、ダメな事のように扱われてしまいがちです。
そんな毎日の欠かせない食習慣からくる、当たり前過ぎて意識することの少ない「噛むこと」。見直してみませんか~!
それでもまだ、意識的によく噛んで食べるという人は少数なのが現実なのは、「噛む」という行為が呼吸と同じくらい当たり前のことになっているからなのかもしれません。
よく「噛むこと」は、食べ物を咀嚼してカラダに取り入れるためだけではなく、全身を活性化させるためにも、大変重要な働きをしています。
また、「噛むこと」でさらに注目したいのは“唾液”の存在です。
“唾液”にはデンプンやたんぱく質を分解する消化酵素が含まれていて、しっかり「噛むこと」で食物とよく混ざり、胃や腸での消化を助けます。また、消化液の分泌を促し胃腸の働きも促進します。そして、口の中を流れている“唾液”には、自浄作用によって虫歯や歯周病を防ぎ、歯を保護する働きもあります。
「噛むこと」と同じように、普段あまり意識しない“唾液”ですが、食べ物とカラダとを密接に結ぶ重要な存在なのですね。
「噛むこと」で“唾液”分泌も活発になるため、やはり「噛むこと」が大切な理由となってきます。
「噛むこと」の効能には、味覚の発達も挙げられます。
また、よく噛んで食べることで、心理的な満足感も得られ、精神的にも安定するそうなのです。ちょっとイライラする時などは、硬いおせんべいやナッツ類などを食べるのもオススメなんですって~♪
猛暑だけではない、最近の‘軟食’傾向により、さほど噛まなくても食べられるメニューが増え、お子様のみならず私達大人の噛む回数も確実に減って来ています。
再度「噛むこと」の重要性を踏まえて、日々の食事によく「噛むこと」のためのちょっとした工夫を取り入れてみましょう。
例えば、やわらかな食材に歯ごたえのある食材を組み合わせたり、噛みごたえのある乾物などの食材をあえて使ってみるetc.です。
噛む回数を、食材選びや料理法の工夫で自然に増やしてみる作戦で、見直してみませんか。

【切り昆布と豚肉の煮物】 3~4人分
・切り昆布 30g(1袋)~5分位水につけて戻す
・豚バラ薄切り肉 200g ~7~8㎜幅にカット
・パプリカ等 1個 ~千切り
- 砂糖 大さじ1
- 酒 大さじ2
- 醤油 大さじ2
①豚肉をじっくりと炒め、豚肉の油で昆布とパプリカを炒める。
②●の調味料を上から順番に1つずつ入れて炒め、蓋をして弱火で5分煮たらできあがり!

【カレー風味☆ツナしらす煮豆】 4人分
・水煮のミックス豆 100g
・人参 Ⅰ/2本
・こんにゃく Ⅰ/2枚
・しらす(いりこでもOK!) ひとつかみ
- 水 200cc
- だしの素 小さじ1
・ツナ缶(小) 1缶 ~油を切っておく
・しょうゆ 小さじ1 ~調整分
・カレー粉(ルウの場合は砕いて) 大さじ1
① 人参、こんにゃくはサイコロ状にカットし、こんにゃくはサッと下茹でをしておく。
② 鍋に炒め油(適量)を入れて熱し、水煮の豆・人参・下処理済みのこんにゃく、しらすを入れて炒め●を入れる。
③ 煮立ってきたら、ツナを入れ、人参がやわらかくなるまで煮る。
④ 一度火を止め、カレー粉を加えよく溶かす。弱火で5分位煮て、味見をし、しょうゆを加え、味見をしてできあがり!後は鍋止めで味を含ませる。
体の中からクールダウン!
とにかく毎日暑い~~!皆様、いかがお過ごしでしょうか?
「朝からカラダがだるい!」「食欲がない~」「胃腸が弱っている」などといった、夏バテ様の症状はありませんか?!
~何を隠そう、この私自身がこの状態なんです(泣)。
・汗をたくさんかく事で、体内の水分が不足する上に汗と一緒に失われるミネラルも不足してしまうケース。
・暑さで胃の消化機能が低下し、体に必要な栄養素の吸収が悪くなり、食欲不振を起こすケース。また、冷たい飲み物ばかりを飲み、胃腸が冷えて胃の働きが低下し、食欲がなくなるケース。
・冷房の効いた室内から暑い屋外に出ることで、体温調節している自立神経が気温の変化に対応しきれなくなるケース。
等々、これらは夏バテ、暑さ疲れの原因として考えられる症状のケースなのだそうです。
人は体温が36~37度の時が一番スムーズに活動できると言われています。火照ったカラダは、この体温に保つため、汗をかくことで体温調節をするわけですが、夏の旬の野菜はもちろん、旬の果物にも、火照ったカラダを冷ます効果があるようです。
この効果のポイントは「カリウム」という成分で、これがカラダを冷やすのに一役買っているのです。この「カリウム」は尿の排出を促して、カラダの余分な熱を逃がす働きをします。また、夏野菜や果物には水分をたっぷりと含むものが多く、水分とともにカラダの余分な熱を対外に放出して、カラダをクールダウンさせる効果もあるそうです。
★夏が旬の果物は、桃、メロン、すいか、葡萄、ブルーベリー、オレンジ、パイナップル、マンゴー、パパイヤ、キウイフルーツetc.があります。
中でも南国系の果物、バナナやメロン、すいか、パイナップル、キウイフルーツ等はカラダを冷やす効果があると言われています~!
冷た~く冷やした‘カットフルーツ’が無性に食べたくなるのもその所為でしょうか~♪
ただ今、夏休みの真っ最中です。クールダウンのできそうなフルーツを使って、お子様でも簡単に手作りできる【ピーチ・ラッシー】を作ってみませんか~♪
“ラッシー”は、インドの定番のドリンクで、スパイシーなカレー等の料理で熱くなったカラダを冷やしてくれる、いわゆる「飲むヨーグルト」です。まさに、“ラッシー”は、カラダの中からクールダウンのできる飲み物なんですね!
今回は、簡単に無理なく作れるように、桃でも‘桃の缶詰’を使いました。甘味も間違いなくあるので、美味しくいただけますよ~♪

【ピーチ・ラッシー】 4人分
・桃の缶詰(黄桃) 1缶(240g)
・プレーンヨーグルト 400g
・牛乳 2カップ
・桃の缶詰のシロップ 大さじ5~
①桃の果肉は薄切りにして、ジッパー付の袋(Lサイズ)に入れて、冷蔵庫で冷たく冷やします。(少し凍らせてもOK!)
②①のジッパー付袋の上から、手でもむようにして、桃の果肉をつぶします。
③②の袋の中に、ヨーグルト、牛乳、シロップを入れてさらに袋を閉め、揉むようにして全体を混ぜ合わせます。
④グラスに注いで、できあがりです!
★ミキサーを使えば、もちろんもっと簡単にできますよ~♪
秘めたパワー!の夏野菜キーマカレー
夏休みがやって来ました!
暑い夏の時期には、人のカラダが必要とする効果の期待できる野菜が多く出回ります。
季節と野菜は、‘素晴らしく、もの凄いバランスで構成されている’と、旬の野菜を見るたびにつくづくと感じます。トマト・なすび・ピーマン・パプリカ・きゅうり・南瓜・冬瓜・とうもろこし・ゴーヤ・アスパラガス・枝豆・ニラ・オクラなど、夏に収穫して、夏に食べる野菜だから、「夏野菜」と言います。
夏は暑いです。そのため、カラダは火照り、熱がこもってしまいます。
ですから、水分をしっかり摂らなかったら熱中症、脱水症状を引き起こします。
昨今の急激で、かつ過酷な猛暑では、非常に心配が大きいところです!
そんな夏にできる「夏野菜」は、水分を供給してくれる野菜が多く、火照ったカラダを冷やしてくれて、利尿作用に効果を発揮するカリウムなども多く、カラダの循環が非常に高まります。
四季の中で、最も代謝が高まる季節ですから、水分を摂り、カラダの循環作用を高め、体内の毒素を排出するのはとても大切なことなのです。
これは室内に入ると涼しい環境が整っている現代では、体温調整としても効果があるため非常に重要なのだそうですよ!
それを担ってくれるのが、「夏野菜」なんですね~♪
その他にも、「夏野菜」には、
1食物繊維:カラダが綺麗になると代謝が上がり、血行が良くなることで栄養が全身に行き渡り、健康にも美容にも効果的とされています。
2ビタミンC:抗酸化作用が高く、活性酸素の過剰発生を防ぎ、健康な肌細胞を守る働きがあります。その為、紫外線からのダメージを抑制してくれます。
3ビタミンE:体内の器官や各部位、細胞の老化を防ぐことから、各器官の働きが向上し、病気知らずの健康体となり、キープすることができます。
4カロテン:抗酸化ビタミンの一種です。
5カリウム:血圧を安定させ、筋肉の働きを良くします。夏場は汗とともに一緒に外に放出されてしまうので、夏バテの原因とされています。
といった栄養効果があるのだそうです!
そんな「夏野菜」の栄養効果をたっぷりと摂取するためには、「夏野菜」をしっかり食べること!ということで、お子様とご一緒に、簡単にレンジで作れる【キーマカレー】のご紹介です。
暑い夏は、どうしても食欲が減退してしまいます。“しっかりごはんを食べて栄養満点になってほしいから~!”みんなが大好きなカレーに「夏野菜」をふんだんに使って、厚い最中だからこそ、火を使わずにレンジで簡単にできるので重宝すること間違いなしだと思います。

【「夏野菜」たっぷりキーマカレー】 2人分
・冬瓜 1/4個
・人参・玉ねぎ 各1/4個
・ピーマン・パプリカ 各1/2個
・ズッキーニ、茄子etc. 各1/2個
~すべての野菜をサイコロ状にカットします!
・合挽ミンチ 80g
・ニンニク&生姜 各1片(すりおろし)
・オリーブ油 大さじ1
(・オクラ(固めに下茹で) 4本 ~斜めに3等分位にカット)
★トマト 大1個 ~崩す様にみじん切りにし、水を足して水分量を約320mlに調節する。
- カレールウ 1/2箱:約70g(お好みのもの)
- 醤油、ケチャップ 各小さじ1
- 塩こしょう 適量
①大きめの耐熱ボウルにミンチ、ニンニク&生姜を入れ、★と●を加えて、箸で全体をよく混ぜ、絡める。さらに、カットした野菜を入れ、オリーブ油を加えて箸で混ぜる。
②中央をへこませて、ふんわりラップをかけて、レンジ600wで5分かける。
③いったん取り出して、全体を混ぜ、また再度ふんわりラップをかけ、さらに1~2分加熱し、2~3分余熱で蒸らす。
*カレールウは、あらかじめ砕いておくとやりやすいですよ!
*クミンシード(ドライハーブ)を小1/2程度入れて作ると、ちょっぴり本格的になりますよ♪
いつも使っているじゃがいもを‘冬瓜’に変えて~、トロンとやわらかく煮た食感のカレーで、より一層マイルドになりますから、「夏野菜」たっぷりでも、お子様にしっかりと食べてもらえると思いますよ~!
“暑さ疲れ”に★丸ごとトマト~♪
毎日、本当に暑~い!うだるような暑さでそろそろ夏バテ気味(!?)、暑さ疲れのお子様方も多いかもしれません。でも、まだ7月なんですよね~~。
“夏バテ”や“暑さ疲れ”は、私たち大人だけのものではありません。
“夏バテ”や“暑さ疲れ”が、お子様たちには無関係なんてことはありません。
お子様の“夏バテ”や“暑さ疲れ”対策は今や常識なんです!
お子様の状態で、「一見元気だけど、どうも食欲がない…」。そんな状態は“夏バテ”の初期症状かもしれません。食欲不振、全身のだるさ、倦怠感etc.…、しかも日中の猛烈な暑さに加えて、熱帯夜による寝不足になってしまうと、‘夏の疲れの連鎖’に陥ってしまい、大変なことになってしまいます。
熱中症対策で、水分補給は必須ですが、やはりしっかり食べることはもっと大切です。
“夏バテ”予防の食事には、‘クエン酸’が良いとよく言われますよね~!
‘クエン酸‘が含まれる身近な食材には、食酢はもちろん、梅干し、レモン、柚子、グレープフルーツ等々、いわゆる、「酸っぱい系」の食べ物に‘クエン酸’は含まれていますが、とにかく暑い時期には、「酸っぱい系」のあっさりとした物が食べたくなるんです。
「酸っぱい系」が食欲増進!の理由は、<酸っぱい→胃が活発になる→食欲アップで食事がしっかり取れる→栄養満点に!>というサイクルが作られること。このサイクルが作られることで、体力や免疫力を低下させないで、“夏バテ”を防げるのです。
また、食事で摂った栄養素をエネルギーに変えるために、体内に‘クエン酸’がしっかりとあれば、食べたものをエネルギーに変える働きが活発になり、疲れが残りにくい疲労回復の効果が期待できるようになるそうです。
暑い時期には、「酸っぱい系」の物が食べたくなるのは、人の本能なのかも(!?)しれませんね。
今回は、私の本能のままに、暑い時期に、暑さで疲れてきた時に、いつも食べたくなる『トマト料理』を紹介してみたいと思います。
夏野菜の代表選手でもある『トマト』ですが、赤色の食材は薬膳では夏の色とされており、“夏バテ=「冷房病」”には持って来い!の食材の色なんだそうです。血液の循環機能や精神活動をコントロールする場所の機能を高める赤色といわれていて、夏は高温や汗で血液が濃縮されることによって体がだるかったり、ボーッとしたり、イライラしたりするそうで、そんな症状を抑えてくれるのだそうです。
『トマト』は夏が旬の野菜なので、スーパーなどでたくさん買えたり、いただいたり、家のお庭等でもどんどんできたり…することもあるかもしれませんね。
そんな時にはぜひ、丸ごと『トマト』を冷やした【丸ごとトマトのサラダ】はいかがでしょうか。
昨今、何かと‘丸ごと’がちょっとしたブームになっていますから、食卓に出したら家族みんなの歓声が聞こえてくるかもしれませんよ~♪

【丸ごとトマトのサラダ】 2人分
・トマト 大2玉
- 酢・オリーブ油 各大さじ2
- 白だし・砂糖 各大さじ1
- 粗挽き黒こしょう 適量
*マヨネーズ、ケチャップ 各小さじ1
・トッピング用 大葉(千切り)
①鍋に湯を沸かし、ヘタをくり抜いたトマトをくぐらせて、皮に日々が入ってきたら冷水に取って、皮を剥く。(湯むきです)
②ヘタの部分を下にしてバットに並べ、良く混ぜ合わせておいた●を回しかける。何回か繰り返したら、表面にピッタリとラップをかけて、冷蔵庫で冷やす。
③②のトマトを器に盛り付け、バットの残った●のドレッシングに*のマヨネーズとケチャップをプラスして混ぜ合わせたものを回しかけて、大葉をトッピングしてできあがりです!
★とにかく、冷たくして召し上がれ~♪美味しくいただけますよ。
疲れないカラダをつくる
7月になったばかりだというのに、毎日本当に暑い~~ですね。
早速、暑さ疲れの私ですが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか(!?)
猛烈な暑さで、「熱中症警戒アラート」が出たり、“熱中症”の厳重警戒もさることながら、熱中症対策での水分補給ばかりが、叫ばれているように感じますが、夏は暑さのせいで(特に猛暑の中では)食事量が少なくなる上に、代謝が上がることで、より発汗するため、普段よりも「たんぱく質」が不足する傾向にあるそうです。
前回のコラムでも紹介した実はとっても大事な「たんぱく質」です。
「たんぱく質」は、カラダを作っている細胞や臓器、組織や筋肉や皮膚、髪の毛などの成分で、発育には欠かすことのできない栄養素で、エネルギー源としてだけではなく、カラダ構成の成分として、また代謝に必要な酵素やホルモンなどの材料にもなるので、実際「たんぱく質」は『元気の源』なのです。
「たんぱく質」不足になると、内臓の働きも衰え、疲労や夏バテにつながるため、夏の暑い時期は、特に「たんぱく質」の摂取を心掛けないといけません。
また、受験生のお子様にとっては、食事から摂取した「たんぱく質」がアミノ酸に分解されて吸収され、脳で伝達物質としても利用されますから、幸福感をもたらしたり、やる気を起こさせたり、疲労回復効果にも期待が持てる最大に活用したい栄養素です。
なので、夏こそ、「たんぱく質」不足に気をつけて、「疲れないカラダをつくること」が大切です!
良質な「たんぱく質」を摂取することの大切さを知っていただいたところで、暑いキッチンでもお鍋ひとつでできる時短メニューで、なおかつサッと食べられて「たんぱく質」もしっかり取れるレシピ【豚しゃぶのぶっかけ麺】を紹介します。
とかく、暑い日はあっさりと麺類が食べたくなりませんか(!?)それ程、食欲が低下しているのかもしれませんね~。だけど、このメニューだと、豚肉に納豆の「たんぱく質」食材がふんだんに摂取でき、豚肉に含まれるビタミンB1の吸収を高めるニラも入るので、「疲れないカラダをつくる」効果がバッチリなんですよ!
今回はそばで作りましたが、うどんでもソーメンでもOKで、‘麺類’なので驚くほどしっかりと食べられてしまいますから、ご家族みんなに喜んでいただけると思います。

【豚しゃぶのぶっかけ麺】 2人分
・乾麺=そば 180g
(うどん・ソーメンでもOK)
・豚ももしゃぶしゃぶ肉 120g
・ニラ 1束 (4~5㎝幅にカット)
・ひきわり納豆 2パック
- めんつゆ(ストレート) 大さじ5
- オリーブ油 大さじ1
・トッピング みょうが(小口切り)、きゅうり(千切り)、梅肉 適量
①たっぷりの熱湯で乾麺を袋の表示時間どおりに茹でる。茹で上がり30秒前にニラを加えて湯がき、一緒にザルに上げて、冷水で洗って水分をしっかり切る。
②①の湯を3カップほど残し、豚肉を弱火で茹でてザルに取る。
③器に①と②を盛り付け、納豆と●の麺つゆを混ぜたものをかけてトッピングをお好みでのせて完成です。
*納豆に味付けをすることで、麺つゆの量を減らせるそうです。また、納豆にオリーブ油を加えることで、腸内環境にもプラスの効果があるようです!
元気の源★たんぱく質
「たんぱく質」。
栄養と言えば、必ず挙がってくるワードですよね!
「たんぱく質」は、カラダを作っている細胞や臓器、組織や筋肉や皮膚、髪の毛などの成分で、発育には欠かすことのできない栄養素です。エネルギー源としてだけではなく、カラダ構成の成分として、また代謝に必要な酵素やホルモン等としての材料にもなります。
また、食事から摂取した「たんぱく質」はアミノ酸に分解されて吸収され、脳で伝達物質としても利用されます。幸福感をもたらしたり、やる気を起こさせたりするのもアミノ酸が原料となるようなので、アミノ酸の不足は伝達物質の不足にもつながり、気分低下や疲労感をももたらします。実際、「たんぱく質」不足は、脳の認知機能や免疫力が低い!という研究報告もあるということで、「たんぱく質」は『元気の源』という訳です。
「たんぱく質」はカラダの組織の構成成分となるという点で重要なので、不足がないように摂りたい栄養素だという事はわかりました。
では、上手な「たんぱく質」の摂取方法とはどのようなものなのでしょうか?!
「たんぱく質」の摂取量が足りていても、エネルギーの摂取量が不足すると「たんぱく質」の一部がエネルギーの方へ使われてしまうので、糖質や脂質の摂取量とのバランスも大事になるようですが、上手な「たんぱく質」の摂取方法は、良質な「たんぱく質」を含んでいる【肉・魚・卵・乳・乳製品・大豆・大豆製品】のいずれかを毎回の食事に取り入れると良いそうです。
そこで、ちょっとおもしろそうな『たんぱく質チェック点数』というのを見つけました。
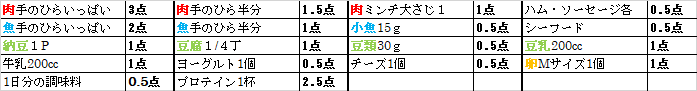
*肉手のひらいっぱい=100g *肉ミンチ大さじ1=30~40g
*魚手のひらいっぱい=60~80g *シーフード=30~50g
(参考:「食事バランスガイド みんなの食育」 農林水産省)
この点数チェックで、1食4点を意識して1日12点を目指すと良いそうです。
先日の私自身の食事の「たんぱく質」の点数は1.5点と目も当てられないような点数で愕然としてしまいました~~。
是非、参考にしてみてください。
食事の主菜や副菜で、しっかり「たんぱく質」が取れることがポイントではありますが、
ごはんごはんしているものを取り上げても、お子様もイマイチだと思いますので、今回はテンションアップの【照り焼きチキンサンド】を紹介してみます。それもレンジで簡単に作れる【照り焼きチキンサンド】で、「たんぱく質」の点数は、肉・チーズ・卵で4.5点、それに牛乳やヨーグルトも添えて、点数アップが可能な一品です。もちろん、パンサンドにしますから、糖質、脂質ともバランスOK!です。

【照り焼きチキンサンド】 1人分
| ・お好みのサンド用パン | 2切れ |
| ・パンに塗る用 | お好みで適量 ~バターやマヨネーズ、マスタード |
| ・チーズ(お好みのもの) | 1枚 |
| ・レタスや玉ねぎスライスetc. | 適量 |
<レンジで☆照り焼きチキン>
| ・鶏もも肉 | 1枚(200g~) |
| ●しょうゆ | 大さじ2 |
| ●砂糖 | 大さじ1 |
| ●みりん | 大さじ1 |
①もも肉の水分や油分を取り、皮目にフォークで穴を開ける。ビニール袋に●の調味料ともも肉を入れてまんべんなく揉み込み、10分~置いておく。
②耐熱皿にクックシートを敷いて、その上にお肉をのせ、タレも少しかける。
③ラップをかけてレンジ500wで4分加熱。ラップを外して上下をひっくり返し、さらに500wで2分~加熱してできあがり!
その間に、スクランブルエッグの準備をします。レンジで作る方法をお伝えしますが、
フライパンで作ると、
<スクランブルエッグ> 1人分
| ・卵 | 1個 |
| ・マヨネーズ | 小さじ1 |
| ・牛乳 | 大さじ1 |
| ・塩・こしょう | 少々(無くてもOK) |
| ・バター | 1片 |
①ボウルに卵、マヨネーズ、牛乳と塩こしょう入れて混ぜ合わせる。
②フライパンにバターを入れて熱々になったところで、①を流し入れて大きく撹拌するように混ぜながら、火を通してできあがりです。
★もちろんレンジでもOKで、①にラップをしないでレンジ500wで1分加熱し、空気を含ませるようによく混ぜて、再度20~30秒加熱します。さらに10秒位ずつをお好みのトロミ加減ができるまで2~3回繰り返したら、レンジでスクランブルエッグのできあがりです。
仕上げは、これらをバターやマヨネーズ、マスタードを塗ったパンに、野菜やチーズと共にはさむだけ!
お子様とも楽しく作って、元気の源=「たんぱく質」強化で、美味しく召し上がれ~♪
“リフレッシュ”~ストレスを減らして免疫力UP!
コロナ禍の生活が始まって約二年!
「リバウンド警戒期間」も終了して、行動の制限や生活の変化も少しずつ緩和されているニュースが流れていますが、今までの生活で知らず知らずのうちにストレスが溜まっている可能性が大きいです。なので、そんな今こそ、意識的に“リフレッシュ”する習慣をつくることが大切になるそうです。どうして“リフレッシュ”が必要なのかと言うと、『ストレスと免疫力はつながっている』からなのです。
‘ストレス’は昨今、とても身近な言葉になっていますよね!
‘ストレス’が溜まると良くないと言われますが、なぜ良くないのかというと免疫力が下がるからなのです。免疫力=ウイルスと戦う力です。免疫には、自然免疫と獲得免疫の2段階があって、そのうちの自然免疫はカラダに入ってきたウイルスと最初に戦うもので、その自然免疫の代表がNK(ナチュラルキラー)細胞なんですって。このNK細胞は常に全身をくまなくパトロールしてウイルスが体内に入ってきた時、真っ先に戦ってくれるもの!通常、カラダも心も元気であれば、しっかり働いてくれるのですが、‘ストレス’で働きが弱ることから、ストレスを溜めないように“リフレッシュ”する習慣を持つことが大切になってくるのです。
NK細胞は、‘ストレス’に瞬時に反応し、その反対も同じで“リフレッシュ”すれば、すぐに細胞の働きがアップするのだそうです!
みんなが少しでもリラックスできるように、“リフレッシュ”方法を探してみました。
【“リフレッシュ”するための方法】
1.好きな音楽を聴いて、ぼんやり過ごしてみる。
楽しいことを思い出させてくれるような音楽がいいようです。(30分程度)
2.外に出ておひさまや風に当たって、植物や花などと触れ合ってみる。
日光は人間の精神状態にとても大きく関係していて、脳内神経伝達の物質の分泌量が増えるそうで、不安や憂うつが解消しやすくなるのだそうです。植物の緑色は安心・安定の色とされ、触れ合うことで芳香を通して神経をリラックスさせて、“リフレシュ”できます。森林浴ですね~!
3.散歩やウォーキングでOK!適度な運動をする。
適度な運動でNK細胞が活性化します。運動や深呼吸やストレッチをすることで、自律神経のバランスを整えるための一番の近道=「腹式深呼吸」が行えます。おまけに運動中は悩めません!だから“リフレッシュ”できるんです~♪そして体温アップで免疫力もアップです。
4.人との関わりやおしゃべりの効果
気の合う仲間とおしゃべりすることで、言葉のキャッチボールが脳をフル回転させるため、良い刺激となり、NK細胞が活性化されます。声を出すということが自然と「腹式呼吸」にも繋がり、ストレス解消にもなるようですし、笑うことや泣くことも“リフレッシュ”になるようですよ!
5.ぬるめのお風呂にゆっくりつかる。
ぬるいお湯は自律神経系に作用して、身体がリラックス状態になり、“リフレッシュ”につながるようです。シャワー浴だけでなく、湯船につかることで効果アップです。
6.香りでリラックス=“リフレッシュ”する。
五感の中でも嗅ぐという感覚は気分転換によく使われ、疲労回復やストレス解消に活用することが、ご存じ、アロマセラピーです。
7.十分に眠る。
睡眠は身体の休息はもちろん、身体をコントロールする脳を休息させるための大切な時間です。精神的な疲労を回復させる大切な営みで“リフレッシュ”です。
8.バランスの良い食事をする。
‘ストレス’が溜まっている時こそ、カラダが喜ぶ食事、つまり栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。良い食生活を続けることで‘ストレス’が溜まりづらくなります。【ビタミンC+たんぱく質】【体温を上げる食材】でも免疫力アップです。
今回は、“リフレッシュ”効果のある栄養バランスの良い【レモン風味のまぐろステーキ】のご紹介です。
香りでリラックス~♪するために、ハーブの「レモンバーム」を使ってみました。
「レモンバーム」は、ヨーロッパ南部に広く分布するシソ科のハーブで、名前の通り葉をこするとレモンのような爽やかな芳香を放ちます。
「レモンバーム」には、抗うつ作用があり、その爽やかな香りで不安な気持ちや緊張を和らげて幸せ気分にする効果があるんですって。【ビタミンC+たんぱく質】としてマグロとレモンを使いました!

【レモン風味★まぐろステーキ】 2人分
・マグロの切り身(無ければ鮭でもOK) 2切れ
・タイム(フレッシュ)~刻みます。 2枝
・薄力粉(刻んだタイムと混ぜておく) 大さじ2
・塩・こしょう 少々
・オリーブ油 適量
・ベビーリーフ(サラダ用) 適量
<レモンソース用>
- レモン Ⅰ/2個分を絞った果汁
- マヨネーズ 大さじ1
- レモンバーム 5~6枚(刻む)
①マグロに塩こしょうをし、刻んだタイムと薄力粉を合わせたものをまぶしておく。
②熱したフライパンにオリーブ油を入れ、①を両面こんがりと焼く。
③●をボウルに合わせて、よく混ぜて、ソースを作る。
④お皿にベビーリーフとレモンバーム、②を盛り付けて、レモンソースをかけて完成。
*塩こしょう、薄力粉をまぶしたら、早めに焼くことがオススメ!水分が出てきます。
*レモンバームの香りがさわやかで、あっさりと食べられます。コクを出したい時は、バターで焼くといいですよ!
マグロは受験生の強~い味方の食材のひとつ。脳活にもバッチリで、“リフレッシュ”効果でHappy気分にもなれるメニューです!
お手軽「シリアルバー」
今や受験生の強い味方になりつつある「シリアルバー」!
‘カロリーメイト’や‘SOYジョイ’など、オーツ麦やグラノーラ、コーンフレーク、大豆、玄米etc.を使った「シリアルバー」は、ヘルシーで食物繊維が豊富です。おまけに栄養バランスも良く、手軽に片手でつまめるバータイプの食べ物なので、お菓子のような手軽さもあり、ちょっとした腹ごしらえや食事と食事の間の栄養補給に食べられる『補食』としても食べたりします。
この「シリアルバー」は、戦国時代の‘懐中食’に着想を得て現代風にアレンジされた食べ物とも言われていますから驚きです!忙しい朝や少ない休憩時間、塾の合間や夜食など、目まぐるしい生活でゆっくりと食事ができないというのが、いつ戦が始まっていつ食の供給路が絶たれるかと気をもむ戦国時代の武将たちと重なったのかもしれません。武将たちがその時手元に運んでいたのが‘懐中食’で、長期戦での栄養不足を補う栄養補給と携帯性に優れ、命綱としての役目を果たしていたとのことで、不安で眠れない時のための「安らぎ」や落ち着く効果も期待しつつの食事であったという逸話もあり、何だか頑張る受験生と同じような気がして、どこか親しみすら感じます。(笑)
「シリアルバー」が塾の合間や夜食などにバッチリ!だと思われるポイントはこちらです。
1.頭を使うと糖質が失われるため、その補給に。グラノーラやオーツ麦等の穀類は糖質をメインとし、脂質は控えめです。
2.血糖値を上げ過ぎない。糖質を摂ると言っても、血糖値が急激に上がり(その時は良いのですが)、その後一気に下がる糖質はグッタリとしてしまうことがあります。
3.‘噛むこと’で脳が活性化する。‘噛むこと’による脳の活性化は周知の事実で、たくさん噛む食べ物を選ぶだけでも記憶力に良い影響を与えると言われています。
4.腹持ちがよいシリアルは消化がゆっくりであるため腹持ちが良いとされ、満足感が実感できるはずです。
5.バランスのよい栄養で体調管理にGood!バランス栄養食のシリアル、グラノーラですから、補食で食べても栄養のバランスをサポートします。乳酸菌や食物繊維、ミネラルを多く含むため免疫力もUPです。
1日の食事を朝昼晩の三食だけではなく何度かに分けて取ることで、1日分のトータル栄養量を効率良く、無理なくそして無駄なく摂る事ができる「シリアルバー」です。
今回は、フルーツグラノーラを使って「シリアルバー」を簡単に手作りしてみましょう!フルーツ入りを使うことで、見た目も可愛らしく、ビタミンも加わってさらに毎日の健康をサポートできますよ。

【フルーツグラノーラバー】 約8個分
・フルーツグラノーラ 100g
・マシュマロ 20g(大5個位)
・牛乳 大さじ1/2
①耐熱のボウルにグラノーラを入れ、マシュマロを3~4等分にちぎって加え、軽く混ぜ合わせる。
(今回は日清の『ごろグラ彩り果実』を使いました)
②①の上から牛乳を回しかけて、ラップをせずに
500wのレンジで1分加熱し、熱いうちに全体を混ぜる。
③オーブンシートの上にお好みの厚さに広げて形を整えて、粗熱が取れるまで冷ましてカットして、できあがり!
*スプーン2本で丸めながらボール状にしてもかわいいですよ~♪
もうひとつ、「シリアルバー」のご紹介です。ホットケーキミックスと豆腐を使って、お手軽に“ソイバー”を作ります。 大豆製品の豆腐を使うので“ソイバー”です。バナナ&レーズンを入れました!

【ソイバー★バナナ&レーズン】 約8本分
・ホットケーキミックス 100g
・絹豆腐 50g
・オリーブ油(サラダ油でもOK) 大さじ2
・バナナ(小さめにカット) 1本
・レーズン(きざむ) お好みで
①オリーブ油と崩した豆腐をホイッパーで混ぜ合わせ、ホットケーキミックスを入れて混ぜ合わせる。
(粉を入れてからは、スケッパーや手を使うとやりやすいです!)
②バナナとレーズンを入れて混ぜ合わせたら、バットにオーブンシートを敷いた上に取り出してお好みの厚みで平らに広げ、しばらくアイスボックスにして冷やし固める。
③180℃のオーブン予熱後、②をバー状にカットして天板にオーブンシートを敷いた上に並べて、10~15分で焼成して完成です。
*どちらも、熱々で食べても美味しいんですよ!
少しずつ手軽に食べられる事がポイントの「シリアルバー」を召し上がれ~♪
気分もUP!のポップコーン
GWはいかがお過ごしでしたか~♪
気分転換も交えての休日になったのではないでしょうか。
まだまだコロナ禍もあり、遠出もままなりませんが、ちょっとした行楽スポットで必ずと言っていいほど目にする「ポップコーン」!「ポップコーン」の専門店などが、注目されていたこともある程です。
そんな「ポップコーン」は三大穀物(米・小麦・トウモロコシ)のひとつのトウモロコシで作ります。なので、カラダにもよい身近なスナックなんですよ!
トウモロコシには、たんぱく質・糖質・脂質の栄養素が含まれ、また、トウモロコシのたんぱく質には必須アミノ酸やビタミンB群、カリウム、マグネシウム、鉄分などの各種のミネラル等をバランスよく含んでいるので、<疲労回復>にも良いとされている食物のひとつです。おまけに、食物繊維も含まれていて便秘解消にもGood!
スナックとして、お子様に与えるには栄養効果もBESTな「ポップコーン」です。

「ポップコーン」でいただくトウモロコシは、小粒で皮は硬く、あまりおいしく食べられそうにない‘ポップ種’と呼ばれる乾燥トウモロコシ=“ポップコーン種”に熱を加えて作ります。元々は硬い皮のトウモロコシなので、よく噛む効果も生まれますし、“噛む”という食行動=「咀嚼効果」は脳を活性化させて、脳を働き物にするとも言われていますから、フワフワでやわらかそうに見える「ポップコーン」ですが、しっかり噛まないと種皮の部分が口に残るためになかなか飲み込めません。しっかり噛むことで消化も良くなり、頭を良くするだけでなく、カラダの免疫力も高まりますので、これが「ポップコーン」のすごい!ところかもしれませんね。
熱を加えるだけで軽くておいしいスナックになる「ポップコーン」の加熱はお家のレンジで簡単にできますよ!
お家ポップコーンを作るためには、前述した“ポップコーン種”を準備します。~“ポップコーン種”はスーパー等で簡単に手に入ります。(即、レンジで作れるパックになったものなど様々なタイプがありますよ。)“ポップコーン種”を購入したら、耐熱容器や紙袋に入れてレンジで加熱するだけで!
お家にいながら、ほんの少しのお楽しみ~♪ということで、お子様と「ポップコーン」作りをして、気分もハッピーにUP!させてみませんか。

【基本のレンジでポップコーン】 ~大皿に山盛り1杯
・ポップコーン種 50g
①大き目の耐熱ボウルにコーン種を入れ、ラップを二重にふんわりとかける。(空気の抜け目を作っておくくらいのふんわり感で~)
②レンジで600w3~4分かけ、一旦取り出してはじけたコーンは別容器にとり、はじけてないコーンはもう一度ラップしてレンジで3分くらい、はじけるまで加熱する。
③塩を適量ふったらナチュラルポップコーン~♪バターを混ぜ合わせてもOKです。
*ボウルが熱くなるので、取扱いには注意しましょう。
*紙袋を使用するともっと簡単ですよ!紙袋の口はしっかりと閉じておくのがポイントです。

【キャラメル☆ポップコーン】 ~基本のポップコーン量
・ブラウンシュガー(砂糖でもOK)
大さじ4~5(50g)
・生クリーム 大さじ3~4
・バター 10g
①鍋に材料をすべて入れて混ぜながらフツフツと少し色付くまで火にかけ、火を止めてポップコーンを絡めてできあがり!
*レンジでもできますよ。~耐熱ボウルに材料を全部入れ、ラップをせずにレンジ600wで3分~くらい、こんがりキャラメル色に色付くまで加熱し、ポップコーンを絡めたら完成です。
*熱くなっているので、取扱いには要注意です。
ポップコーン専門店では、キャラメル味が人気なのだとか。
これで、今日から我が家もポップコーン専門店ですね~♪
【いちご】はスーパーフルーツ!
お子様から大人まで誰もが大好きな「いちご」!
ただ今、旬の真っ盛りの「いちご」~、春ですね~~♪
「いちご」はビタミンやミネラルなどが豊富に含まれており、“ビタミンCの王様”と言われるほど、‘ビタミンC’が多く、グレープフルーツやみかんの約2倍も含まれており、果物の中でもトップクラスの‘ビタミンC’なのだそうです。

‘ビタミンC’には抗酸化作用があるため、皮膚や血管の老化を防いだり、ストレスや風邪に対する抵抗力を強める働きがあります。中サイズの「いちご」を約13粒食べることで1日に必要な‘ビタミンC’が摂取できるということです。また、体内の余分な塩分を尿中に排出する働きがあり、むくみや高血圧の予防効果や、疲れにくいカラダをつくる鉄も含まれているため貧血の予防効果も期待ができる「いちご」です。また、貧血に効果的な赤血球の生産を助ける働きがあるビタミンB群の葉酸も含まれているとのことで、小さな可愛らしい見た目からは想像をはるかに超えるスーパーフルーツでした!
「いちご」に含まれている豊富な‘ビタミンC’を活かすには、生で食べるのが一番!‘ビタミンC’が熱に弱いからですが、生食でも、「いちご」を洗う前にヘタを取ると‘ビタミンC’や葉酸などの水溶性ビタミンが流れ出てしまい、味も水っぽくなるのでNGで、ヘタを付けたまま流水で手早く洗って、ヘタを取ってパクッ!と食べるがBest(笑)です。
今回は、そんな「いちご」の栄養効果は残しつつ、少しだけ手を加えた和風スイーツ【いちご大福】のご紹介です!
大福の求肥(皮)をレンジで簡単に作り、さらに簡単にするためにあんこを丸めて求肥に包む大福を作った後、「いちご」を後入れしていきますから「いちご」を包む手間も省けるやり方ですよ~。

【いちご大福】 小さめ6個分
・白玉粉 80g
・砂糖 40g
・水 90ml
・あんこ 180g
・片栗粉 適量
・いちご 6粒
①あんこ(黒・白お好みで)6等分にして丸めておく。
②白玉粉と砂糖を耐熱ボウルに入れて混ぜ合わせ、さらに水を入れて粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜ合わせる。
③②にラップをかけて、600wのレンジで約2分加熱し、それを取り出してゴムヘラで全体をサックリと混ぜ合わせてラップをし、さらに600wのレンジで1分30秒加熱を続ける。
④③を取り出し、全体しっかり混ぜ合わせたら、片栗粉適量をふったバットに取り出して6等分にして、少し広げながら①のあんこを包んで大福を作る。
⑤大福の中央をキッチンバサミで十文字に切り込みを入れ、洗ってヘタを取った「いちご」を尖った方を上にして差し込むようにのせたらできあがり!
【いちご大福】を持ってお花見やピクニックに行くのも、気分転換にはなんだか素敵~♪な気がしませんか~!
【鯛めし】で、春のお祝い飯
Spring has come!
桜も満開で、何かとお祝い事の多い“春”のシーズンです。
このウキウキする気持ちをお家の食事でも反映できて、ちょっぴり普段よりは豪華だけど簡単にできるご飯は、~~(!?)と考えました。
春の旬の食材である「鯛」!
昔から縁起のよい食べ物として、塩焼きや姿煮etc.いろんな場面で食卓に上ることも多いかもしれませんが、やっぱり心華やぐ“お祝い飯”には「鯛」かな~(!?)と思います。
そんな「鯛」を使って、炊飯器で簡単に作れる【鯛めし】はいかがでしょうか。
【鯛めし】は愛媛県に伝わる郷土料理のひとつです。
鯛は瀬戸内海近海等で漁獲され、『魚の王様』とも呼ばれる高級魚!
また、‘めでタイ’とも言われるように、おめでたいお祝いの席に登場することも多い、縁起の良い魚です。また、「鯛」の栄養は、ご存じのDHAやEPAの効果で、血液をサラサラにする働きがあることから脳の活性化にもバッチリで、たんぱく質が多く含まれる魚介類なので免疫機能を正常に保つ働きがあると言われていて要注目!の食材でもあります。
こんな「鯛」を使った【鯛めし】の栄養は、お茶碗一杯でも、炭水化物・タンパク質はもちろんのこと、ビタミンAやB、食物繊維やミネラルの中でもカリウムが多く含まれますので、エネルギーの維持や疲労回復、疲れ目や夜間の視力低下を防ぎ、おまけに便秘にもよいという、まさにお勉強に頑張っているお子供様にはバッチリ!のご飯なんですよ~♪
【鯛めし】と聞くと、焼き上げた鯛を一匹丸ごと土鍋に入れて、ご飯と一緒に蒸し上げる料亭のイメージで、‘なんだかな~~’、と思われるかもしれません。
でも、あくまでそこはお家ごはん~!です。もっと簡単に「鯛」の切り身を使って、炊飯器で炊き上げて、【鯛めし】の栄養効果のみをふんだんに取り込みましょう。
そして、春の気分とお祝いの気持ちとともに、これからの更なるエール!にもなる、【鯛めし】に思いを馳せてみませんか。
いつもの炊き込みごはんの延長で、気持ちも楽~に、【鯛めし】をどうぞ!

【鯛めし】 2~3人分
・真鯛の切り身 6切
・塩 適量
・酒 大さじ1
・米 2合
●生姜(千切り) 1片
●麺つゆ 大さじ1~2(味見加減で) ~しょうゆ・酒 各大さじ2でもOK!
●みりん 大さじ1
・だし昆布 約10㎝
・三葉・刻みネギ 適量(トッピング用)
①フライパンにホイルを敷いて熱したところに、塩をしておいた鯛の切り身を並べて、焼き色を付けるように焼く。焼き色が付いたところで酒を振り入れて、フタをして蒸し焼きにし、身がふっくらとしたらOK!
★塩をした後の鯛は、しっかりと水分を拭き取ると臭みが無くなります。
②炊飯器に研いだ米と●の調味料を入れ、2合の水分量まで水を加えたら、だし昆布と①の鯛をのせて、スイッチON!
③炊き上がったら、昆布を取り出してさっくりと混ぜ、茶碗によそって、三葉(茹でて結び三葉にしておく)やネギをトッピングしてできあがりです。
★もっともっと栄養価を加えたい場合は、人参やごぼう、油揚げ等を加えてもいいですよ。
★木の芽があれば、トッピングに木の芽を使うともっと格式アップです。
“塾デリカ”のヒミツ!★2022年
3月になりました。新年度“塾デリカ”のスタートです!
“塾デリカ”とは、「学びにも体にもよい食事をお届けすること」をコンセプトに、『一汁二菜』を基本とした、成長期のお子様にとっての必要な栄養素や、学びに必要なビタミンなどの栄養を含む10~15品目の食材を使ったバランスの良い食事&温かいお味噌汁付きでお届けする‘お弁当’です。安心・安全な食材はもちろん、無添加に近い天然素材の調味料にこだわった、カラダにやさしくて頭にも良いものを提供し続けているのが“塾デリカ”なのです。
『一汁』は、こだわりのある出汁(アゴだしや昆布だし等)から作られている‘だし’を使い、甘味のでる野菜を煮込んで作るカラダの芯からホッ!とできる一品として提供している人気のお味噌汁やスープです。お味噌汁の人気のヒミツは、味噌に国内産の大麦こうじと有機大豆から作られている‘麦味噌’を使っている大豆いっぱいのこだわりの「田舎味噌」を使用していること!
『二菜』は、毎回10~15品目の食材を使用した‘メイン&副菜’で構成されていて、体力&脳力、精神面にも強化できることを目指した、塾ならではのこだわりのあるものに仕上がっています。そして、いろいろな野菜を召し上がって欲しいので、野菜が豊富に使われていることは“塾デリカ”ならではの自慢のひとつにもなっています。
1日のメニューコースは、魚や肉がバランス良く組み込まれている『一汁二菜』を基本とした日替わりの【応援デリカ】、そして、栄養バランスが瞬時に摂り込めて、ガッツリ!と食べていただけるように考えられた丼ものを基本とした【のっけデリカ】となっています。

★どちらもお味噌汁付きですよ~♪また、単品メニューとして、ワンハンドで食べられるように‘国産鶏肉’を米油で揚げた【オリジナル唐揚げ棒】と、プチ贅沢感が売りの【季節の果物】があり、人気です。【季節の果物】は‘旬のフルーツ’が基本となりますから、プラスαすることで、免疫力を強化することもできて風邪予防や疲労回復には欠かせない1品ですね~♪
そして、毎月1回、白石学習院専属食育インストラクターの私から受験生の皆さんに向けてのエール(!?)として、スペシャルメニューを提供させていただいています。脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けてのゲン担ぎとなる縁起物など、大神家の子どもたちが喜んで食べたものなどがメインになっているスペシャルメニューです。普通の家庭料理ですが(笑)、楽しみにしてみてくださいね~♡
“塾デリカ”の中でも、今回、特筆すべきものが、塾デリカ定番の人気の温かいお汁物が【とっておき具だくさんお汁】となって、ゴロットと具材が入り、パワーアップすることです。お味噌汁だけでなく、パンメニューの日には洋風スープで登場します。そして、そのパンメニューが手軽に食べられて、なおかつ栄養がしっかりと摂れるということで
お子様たちからご好評をいただきまして、“パンメニュー”の登場が増えていきます~♪
2月に実施させていただきました【大人気メニューお試し塾デリカ】は、ご試食いただけましたでしょうか(!?)
【鶏肉唐揚げ&ミートスパゲッティ】【ナンカレー】【照焼きバーガー】でした!
最近、あちこちに「唐揚げ屋さん」ができていて、ちょっとした食べ比べもできてブームになっていますよね。【唐揚げ】は、我が家でも人気で、時々無性に食べたくなる一品です。
そこで、やっぱり無性に食べたくなったので、我が家の【唐揚げ】をご紹介~♪です。
たぶん、皆様の【唐揚げ】と大した違いはないと思いますが…笑

【我が家の唐揚げ】
・鶏むね肉 2枚
<漬けタレ>
- 醤油・みりん・酒 各大さじ2
- 砂糖 大さじ1~2(甘めが好きなら大さじ2)
- すりおろし生姜&ニンニク 各大さじ1位
- 黒こしょう 適量(少し多めが好きです)
<衣>・片栗粉+コンスターチ 適量(半々位)
①鶏肉は皮を除いて、大きめにカットし、合わせておいた●に時間の許す限りしっかりと漬け込む。
②合わせておいた<衣>を付けて、揚げていく。
*ポイントは、2度揚げていくことで、一度目は170℃(揚げ油に付けた菜箸の先から泡がゆっくりと出てくる)で揚げ、取り出して2分位放置し、二度目は190℃位(菜箸の泡が勢いよく出る)の高めで、色目がしっかりと付き、カリッとする感じまで揚げること!~高温なのですぐ!ですよ。
*<衣>はコンスターチ=とうもろこしの粉を混ぜること。無ければ片栗粉だけでもできますが、我が家は唐揚げ用にコンスターチを常備です。
★いつもいつもこの【唐揚げ】ばかりではなく、使いかけの「キムチの素」や「焼肉のタレ」があれば、それを漬け混ぜて<衣>を付けて揚げたりもしていますよ~♪
お気に入りの水菜!
最近、我が家ではコロナ禍ということもあり、ひとり鍋がチョットしたブームになっています。簡単に野菜やお肉、魚などのたんぱく質がしっかり取れて、何だかホッとできる一品です。そして、私のお気に入りの食材が“水菜”!

しゃぶしゃぶや寄せ鍋に“水菜”を入れる、と言う方も少なくないと思います。“水菜”は今の時期が旬。
水分が多く、一見か細い感じがする“水菜”ですが、実は栄養面では優れた野菜なのですよ。
“水菜”は『京菜』とも呼ばれ、江戸時代の初め頃から京都で栽培されていた日本伝統の京野菜なのだそうです。
“水菜”の名前の由来は、無肥料で水と土だけで栽培されていたからとも、水分がたっぷりだからとも言われています。
今ではハウス栽培も普及して一年中出回っていますが、今の時期は味のよい露地栽培の“水菜”が出回ります。
京都では、『水菜が並び始めると冬本番』と言われ、“水菜”を入れた鍋を楽しみにするそうです。~少々、時期がズレてしまった感じではありますが…笑。
“水菜”は、鍋物等に入れると魚や肉の臭みを消してくれるので、鍋物等にはピッタリ!の野菜です。“水菜”は歯ごたえがシャキシャキとしてよいものの、茎や葉が細くて、小松菜やほうれん草などに比べると頼りない感じがしますが、見た目とは違って栄養面は抜群!確かに水分が90%以上ですが、意外にも栄養価は高い野菜なのです。
例えば、抗酸化作用があり、美肌効果や免疫力を高める効果がビタミンCは100gあたり55㎎含まれていて、これはレモンの1/2個分以上に当たるということで、驚きです。
また、骨の生成を促したり、体内の余分な塩分を排出して血圧の上昇を抑える効果があるようです。さらに、カルシウムも100gあたり210㎎と、牛乳の約2倍も含まれているということで、野菜では抜群に多いそうですよ。
“水菜”の栄養は、茹でると流出してしまうため、鍋物にする場合は、最後にご飯やうどん等を入れて、優れた栄養を逃さないようにスープと一緒に食べるのがGood!です。
ビタミンCを意識するならば、生食のサラダがオススメ!油との相性が良いのでサラダであれば、オリーブ油やごま油等をかけたり、またサッと油炒めにするのがベスト!
豊富なカルシウムを効率よく摂るには、カルシウムを吸収しやすくする効果を持つビタミンDを含むシラスや鮭などの魚類やきのこ類を合わせるようにするといいでしょう。
今の時期の“水菜”は、味が濃くて風味が強い露地栽培物が店舗に並びます。茎がしっかりしていて全体に量感があり、緑色が濃いものをみつけたら露地栽培物で美味しい“水菜”かもしれません。
そこで、少しでも簡単な“水菜”を使ったメニューをお知らせしたいので、今回はスープ&パスタにしてみました。もちろん、お鍋はご家庭のお味で召し上がれ~♪
今回の我が家のお鍋は、【水菜のはりはり鍋】です。

【水菜のはりはり鍋】 ~一人鍋です!
・だし 2カップ
・薄口醤油 大さじ1/2
・豚バラ肉、人参、大根、えのき、“水菜”

【水菜のパスタ】 2人分
・パスタ 2人分(160g~)
・合挽ミンチ 50g
・“水菜” 1/2束(約50g)~ざく切り
・人参・玉ねぎ 1/4程度 ~千切り
・しめじ 1/2パック
・バター 小さじ1(5g)
・和風だしの素 小さじ1/3
・醤油 大さじ4/3
・砂糖 大さじ1
①パスタを茹でている間に、バターでミンチ、人参、玉ねぎ等を炒め、食材が1/4程度浸る水で煮ながら、調味料で味を付ける。
②水分が無くなったところで、茹でたパスタと水菜を入れてサッと炒め合わせたら、完成!
★パサつくようであれば、水溶き片栗粉でトロミを付けても美味しいですよ!

【水菜のふわふわスープ】 2人分
・コンソメスープ 水500ml+コンソメ小さじ1
・醤油 小さじ1
・塩 小さじ1/3
・絹豆腐 1/4丁
・溶き卵 1個分
・“水菜” 1/2束 ~ざく切り
①コンソメスープで食材に火を入れて、最後に溶き卵を溶かし入れたら、できあがり!
【ぜんざい】はパワーフード!?
まだまだ寒~~い日々が続いています。
だけど、気分は春めいて~♪明るい気分がやって来ているでしょうか!
なぜかこの時期、寒さ疲れのせいなのか、それとも春めくような気分だからか、私はあんこや小豆系のものが食べたくなります。
あんこのこしあん、粒あんは、共々“小豆”!
“小豆”は、良質のタンパク質はもちろん、豊富なビタミン類やカリウム、リン、鉄、食物繊維等のミネラルなど、栄養バランスの良い栄養的にもとても優れた食品です。
糖質の代謝を助けてエネルギーを作り出し疲労回復に役立つビタミンB1や、細胞の新陳代謝を促進し、皮膚や粘膜の機能維持や成長に役立つビタミンB2、また脳神経を正常に働かせるのに役立つと言われているナイアシンやビタミンB6、またストレスを和らげる働きのあると言われるパントテン酸や、貧血を予防し、細胞の生まれ変わりに欠かせない葉酸を含んでおり、抗酸化作用や脳の活性化、また免疫力も高めてくれ、高血圧の予防にも役立つ等々と栄養はバッチリ含まれています。
お祝い事や特別の行事によく用いられる【お赤飯】に“小豆”を用いるのは、“小豆”に薬効があるからとのこと。昔の人は“小豆”にこれらのような栄養効果があるのを知っていたのでしょうね~。
「元気パワーのサプリ」=“小豆”なのかもし れません。

そこで、今回は、今私自身が食べたい気分なので、【ぜんざい】のレシピにしました!
【ぜんざい】は、出雲地方が発祥とも言われている、私にとっての【縁結びパワーフード】です。出雲地方は、「神在」と書いて【ぜんざい】と方言で発音する、【ぜんざい】の発祥の地のようです。そうです、「出雲ぜんざい」です!
島根県出雲地方には出雲大社があり、ご存じのように出雲大社は『縁結び』の神様として有名です。『縁』というのは、男女の仲だけではなくすべての事が幸福でうまく廻って行くための『縁』で結ばれることを指していると言われています。
そのため、お勉強に頑張っておられるお子様とっては、幸福な人生に向かっての「良い進路へとご縁が繋がっていきますように!」という願いがこもっての【縁結びパワーフード】という訳です。
体力が落ちたり、気力が下がった時に食べたくなるのは、その所為もあるのかもしれませんね。(笑)
“小豆”からコトコト炊き込んでいく【ぜんざい】も美味しいですが、今すぐ食べたい私にとっての茹で小豆を使った、チャチャッと作る時短の【ぜんざい】です~♪

【ぜんざい】
・茹で小豆(砂糖入り) 1缶(1袋)
・水 200ml(茹で小豆と同量で)
・塩 ひとつまみ
・お餅、白玉団子等 お好みで
①鍋に茹で小豆と水を入れて、火にかけてひと煮立ちする。(アクが出るようであれば取る)
②弱火にして塩で味を調味する。~甘味はお好みで砂糖を入れて調整してください!
③お餅やお団子は焼いたり、茹でたりをお好みで!器に盛り付けてできあがりです。
お餅や白玉団子に用いられる、お米=もち米は、頭=脳の唯一のエネルギー源で、【頭の良くなる食材】のひとつ!そして、ぜんざいやあんこの“小豆”は、糖質をエネルギーに変える作用が【最強の食材】なので、頭脳をフル回転させてくれる【ぜんざい】は、【縁結びパワーフード】はもちろん、【元気パワーのパワーフード】でもあるのです~♪
【節分豆】は“福豆”!
2月3日の【節分】の日には、‘豆まき’をされたご家庭を多かったかもしれません。
【節分】という「季節の変わり目」は、旧暦で言われる【立春】を“新しい年を迎える大切な節目”としていたために、お祓いをする習慣から豆や米などをまいていたとされているそうです。昔々は、季節の変わり目(丑寅の方角)に鬼がやって来て、病気や災いをもたらすと信じられていたようで、豆や米には不思議な力があるとされており、‘豆’を鬼の目である「魔目」にめがけて投じれば、魔が滅する=「魔滅」という意味から、“豆をまく”と鬼を追い払うことができるという由来なのだそうですよ。ちなみに、“鬼”は丑寅の方角から連想されて、鬼の角は‘牛の角’でトラ柄のパンツをはいているのは‘寅’からきているのだって!(何だか、怖い“鬼”がかわいくなってきませんか~)この由来から、一年の大きな節目に当たる【節分】に豆をまき、その後一年間無病息災に過ごせるよう、歳の数だけ豆を食べると良いという習慣になったということです。
そのため、“節分豆”は“福豆”とも呼ばれます!
‘豆まき’の豆の主流は大豆!
大豆には、あなどれないほどの健康効果があるのは皆さんもご承知のことと思います。
「畑の肉」とも呼ばれることも多い大豆は、たんぱく質が豆類の中で一番多いだけでなく、動物性たんぱく質に非常によく似た性質を持つ、とても優れた栄養食品です。
また、お勉強に頑張る子供たちには嬉しい、頭を活性化させる「ブレインフード」でもあるのです。大豆には、脳の働きをサポートし、脳の神経細胞を構成するのを担う<大豆レシチン>が多く含まれていて、脳内でのスムーズな情報伝達を促進することができる働きをしてくれます。
‘豆まき’が終わった後、一年の健康を祈って歳の数だけ“福豆”を食べることには、健康面での裏付けもあったのですね。
でも、意外と‘節分’の後、豆が余ったりしていませんか。
せっかく、栄養面でも優秀で「ブレインフード」でもある“福豆”ですから、余ってしまった豆を処分するのはもったいない!
そこで早速、“福豆”のリメイクです。
今回は『きなこ』にしてみました。『きなこ』は大豆を砕いたもの~♪
『きなこ』にしておけば、お正月から余ってしまっているお餅やパンなどと一緒に、ちょっとしたおやつにもなりますから!

【福豆きなこ】
・節分豆(炒り大豆) 適量(残った分)
・砂糖 きなこの1/2量位
・塩 ひとつまみ
①節分豆(大豆)をフライパンで乾煎りする。(炒ってある大豆ですが、さらに炒った方が香ばしく仕上がります。)
②少し香ばしい香りがただよって来て、大豆が温まる程度で火からおろして、ミルサーにかける。
③ミルサーによっては、粒が残ってしまうことも多々ありますが、気になれば取り除く。~粗い目のきなこもポリポリしておいしいです!
④③に砂糖と塩を混ぜて、“きな粉餅”や“きなこトースト”に変身~です!

白石学習院特製の【合格ひじき】
【合格ひじき】をご存じですか~(?!)
受験にむけて、“お子様の食を通じてカラダに優しく、頑張るお子様方が簡単に食べられ、応援することができる食べ物”として考えました。
薄味に煮たひじきに、五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて、各自各々で作る“ウエットタイプのひじきのふりかけ”です。
白石学習院の専属食育インストラクターとなって、初めての「食育イベント」で、紹介した【合格ひじき】が私の原点です。1月になり、いよいよ入試のスタートです。
そして、この【合格ひじき】のシーズンがやって来ましたよ!

この白石学習院特製【合格ひじき】の基礎案となっているのが、今でこそ、広島のデパートや通販でもお見かけするようになった『十二堂えとやの“梅の実ひじき”』です。
福岡の合格祈願・学問の神様でも有名な「太宰府天満宮」に位置する『えとや』さんのふりかけで、大宰府の名産品のカリカリ梅の実が入ったあっさりとしたひじきがメインのふりかけです。
我が家の子供たちの受験期に「太宰府天満宮」のお守りと一緒に“梅の実ひじき”をいただいたことがきっかけで、ひじきを薄味に煮たものに、カリカリ梅をはじめ、五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて、各自各々で作る【合格ひじき】が白石学習院特製として誕生しました!~熱々のごはんにのせていただくと、とっても美味しくて食が進みます♪
五色の食材とは「赤・白・黄・緑・黒」色の見た目の判断でOK!のすべての食材が対象で考えます。五色になるように食材をなんでも取り入れて作ると、不思議とカラダに必要な栄養がほぼバランス良く揃う!という、塾デリカのメニュー構成やお弁当作り、また日々の食事作りにも率先して取り入れ、提案をしているひとつの方法です。
五色の食材の栄養素はもちろんですが、五色の色のパワーもじつは侮れません。
*赤色の効用として、活力を与えてバイタリティーを高めます。血となり肉となる食材が豊富です。
*白色の効用として、心を落ち着かせます。“カラダの素となる”エネルギーを作り出す食材が豊富です。~ごはんのイメージです!
*黄色の効用として、脳を刺激して希望につなげるパワーになります。頭&カラダを働かせる原動力となります。
*緑色の効用として、ストレスを和らげてココロの安定効果があります。カラダの調子を整える、野菜や果物に多いイメージです!
*黒色の効用として、安心感や強さ、自信を与えます。カラダ&頭の健康維持に必要な食材が豊富です。
専門的に立証されていることではありますが、専門的に考えながら食事を作る毎日も疲れてしまいますので、ザックリと大まかに捉えて作る【合格ひじき】が白石学習院特製なのです。
これからとても大切な時期に入るお子様のために、ぜひ、お母様特製の“我が家の”【合格ひじき】を手作りして、応援していきましょう!

【基本の【合格ひじき】】
・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で約100g位
・だし汁 120cc ~ひじきがヒタヒタに浸かる位です。
(水120cc+和風だしの素 小さじ1)
・醤油 大さじ2
・砂糖 大さじ1
・みりん 大さじ3
・昆布茶 小さじ2~3(*隠し味になります!)
- トッピングはお好みで
赤:カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老など
白:白ゴマ・タラの身・ちりめん・かつお節・大豆の水煮など
黄:柚子の皮(細く千切りしたもの)・炒り卵など
緑:あおさ海苔・いんげん・枝豆・パセリなど
黒:黒ゴマ・刻みのりなど
①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水で戻します。(約10分~)
約8~9倍に増量します。
②①の水切りをしたひじきを鍋に入れ、だし汁と調味料をすべて混ぜ合わせて煮ます。
③汁気が無くなるまで、時々混ぜながら煮たら【合格ひじき】の素=“ひじき”の完成!
*少し乾煎りするようにしっかりと水分を飛ばしながら煮ることがポイント。
*お好みのトッピングを適量混ぜ合わせたら【合格ひじき】のできあがりです~♪
【合格ひじき】のアレンジとして、『和風オムライス』を紹介します。
このオムライスで、お母様のエールを送ってみませんか!

【簡単★和風オムライス】
・合格ひじき 適量
・ごはん 適量
・卵 2~3個
- 甘酢あん 1人分
・だし汁 水150ml+和風だしの素 小さじ1
・砂糖、醤油 各小さじ2
・酒 小さじ1
・酢 小さじ1/2
・片栗粉 大さじ1
①ごはんに【合格ひじき】を混ぜ、卵を巻いてオムライスを作る。
②●をすべて鍋に合わせて火を入れ、トロミが付けばOK!
*簡単にポン酢+だし汁にトロミを付けても美味しいですよ。
一年を元気に!★【七草粥】
2022年の始まりです!
受験生のお子様方はこれからが本番です。
カラダも頭も心も疲れないように、ほっこりする食事で気分も穏やかに、そして元気に保っていきたいところです。
昔ながらの行事食で1月7日は【七草粥】ですね。お正月のおせち料理に食べ疲れた胃をゆっくり休めることや、これを食べて一年間の無病息災を願うという言い伝えのある
“おまじないのごはん”です!
“春の七草”の種類は、
【セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ】

七草はいわば日本のハーブ! そのハーブを胃腸の負担が少ないお粥で食べることが、正月疲れの出始めた胃腸の回復にはちょうどよく、また、いずれもみずみずしい緑の草ですから、ビタミンやミネラルがたっぷり含まれているため、風邪予防や免疫力アップ、健胃効果や食欲増進効果にも最適で、元気なカラダを保つためには持って来い!という訳です。
カラダが元気であればお勉強にも頑張れますし、きっと心も落ち着いて来るはずです~♪
ちなみに、『春の七草』に込められた1種1種の意味をご存じですか(!?)
案外、これから本番を迎える受験生のお子様に食べてもらいたい“ゲン担ぎ”食材としてもバッチリ!のような謂れがありましたよ~!
*セリ(芹):競り勝つ
*ナズナ(薺):撫でて汚れを払う
*ゴギョウ(御形):仏体
*ハコベラ(繁縷):繁栄がはびこる
*ホトケノザ(仏の座):仏の安座
*スズナ(菘):神を呼ぶ鈴
*スズシロ(蘿蔔):汚れのない純白
緑の野菜が不足しがちな寒い時期だからこその滋養豊かな七草を、お子様と確認しながら【七草粥】で召し上がってみるのも、少しの安らぎタイムになるかもしれませんね。

【簡単☆七草粥】
・七草粥のパック 1~2p
(我が家はしっかり食べさせたいので2pです)
・ごはん お好みで
~サッと水洗いをしてヌメリを取っておく!
・出汁 (1ℓの水に対して、和風だし小さじ2位)
・醤油、塩 適量
~醤油を入れると青臭さが緩和されます。
①お鍋に、出汁を入れて、七草の中の少し硬いところから炊き始める。
②軟らかくなったら、ごはんと残りの七草、塩、醤油で調味して炊き込んだらできあがり!
*ごはんを使うので、あっという間にできあがります。
ご家庭のお好みの味で【七草粥】をぜひお楽しみくださいね~♡
「たこ」は<クイックエネルギー食>!
「たこ」は、高たんぱく低カロリーの健康食材!だということをご存知ですか。
「たこ」には驚くほどの栄養素がギッシリなんですよ!
「たこ」に含まれる成分のビタミンB12は、神経及び血液細胞を健康に保つことを助けてくれるため、何てたって集中力アップに最適で、おまけに元気で健康にいられる栄養素なのです。植物性の食物には、ほとんどといっていいほど含まれていない成分なので、「たこ」を食べて積極的に摂取したいと考えて、今回のテーマに「たこ」を取り上げてみました。
さらに、「たこ」には体内の酸化を防ぎ肌や粘膜等を活性化する役割のあるビタミンEや、疲労回復や眼病予防になるタウリン、カラダのデトックス効果や持久力の向上効果、そして脳機能を活性化する効果が豊富なアミノ酸、体内総エネルギーの素、活力の素!の亜鉛等、スゴイ栄養がたっぷりなのです。
「たこ」は、実は、<クイックエネルギー食>のひとつと言われています。
<クイックエネルギー食>とは、オリンピックに出場するようなアスリート達が、試合前の食事を摂る時のもののことを言うのだそうです。即効に、エネルギー源となって、力を発揮することのできる食物ということです。
「たこ」には、先述したようにタウリンという成分を含んでいますが、これには受験生に最適の即効で脳を活性化する効果もあるそうです。栄養ドリンク等に多く含まれるおり、飲むと即効に眼も頭も冴え渡ってくるような効果のあるタウリンのことです。
いわゆる、受験生の<クイックエネルギー食>という訳ですね。
今回は、このタウリンを最大限に活用できそうな「たこ」をお家でも食べていただきたくて、【たこ飯】レシピを紹介してみますが、その前に、「たこ」の話題をひとつ!
瀬戸内の「たこ」の町として有名な三原では、【たこ飯】がご当地名物として知られています。【たこ飯】ツアーなるものもあるそうですよ。
そして、「たこ」は英語でOctopus;(オクトパス)。“置くとパス!”すると言われているゲン担ぎのひとつ(!?)としてもご存じの方も多いのではないでしょうか!JR三原駅では、「たこ」の町ということもあってか、受験の時期になると『タコの絵馬』を配布しているそうですよ。“置くとパス!”するゲン担ぎの‘合格のお守り’となっているようです。~だんだんとそんな時期になってまいりましたね~
そこで、少々早いですが、ゲン担ぎも含めて(笑)、<クイックエネルギー食>の「たこ」を使った一品、お家で食べる【たこ飯】レシピという訳なのです!
<クイックエネルギー食>の「たこ」を、日本の伝統的な脳のエネルギー源となる‘ごはん’と一緒にいただくことで、『即効☆脳チャージ』の【たこ飯】になると思うのですが、いかがでしょう~(!?)

【たこの炊き込みごはん】 2~3人分
・米 2合
・茹でたこ 200g(足で2~3本分)
・生姜 2片(みじん切り)
・人参 1/3本(みじん切り)
・油揚げ 1/3枚(みじん切り)
・長ネギ 1/3本(みじん切り)
- 昆布茶 大さじ1
- 料理酒 大さじ2
- 塩 小さじ2
①たこは、お好みで薄切り、ぶつ切りにしておく。
②米は研いで水気を切り、炊飯器に入れます。
③●の調味料を入れて、2合の目盛まで水を加えて、生姜、人参、揚げを入れ、薄切りにしたタコをのせて、スイッチON!
④炊き上がったら、ネギのみじん切りを入れ、全体をさっくりと混ぜたらできあがり!
⑤器に盛り、結び三つ葉をのせてもOKです。
*たこは、冷凍して使うと軟らかくいただけるそうですよ。
今回は、薄切りにしていますので、軟らかくいただけますが、ぶつ切りにしたい時はこの方法を取り入れてみてください♪
頭にいい味噌(=脳みそ!?)
「“ネギ”を食べると頭が良くなる」、昔からよく言われる言葉です。
昔の人たちがどういう根拠でそう言ったかはわかりませんが、まるっきり迷信という訳でもないようです。
“ネギ”の栄養は、ビタミンAとC、カルシウム、カロテンなどが含まれています。
“ネギ”の最も個性的なポイントといえば、独特な匂い。独特な匂いを作り出しているアリシンという成分(玉ねぎにも含まれています)は、血行を良くしてカラダを温める働きがあり、ビタミンB1の吸収を助けてくれるので疲労回復に役立つと言われています。
この“ネギ”や玉ねぎに含まれる独特な匂いに関わっている成分のひとつが、記憶力の向上に大きく関係するようなのです。ただし、短期の記憶で、数秒間だけ保持されるのだとか。長期的な記憶は、短期的な記憶の反復によって獲得されるとも言われていますので、記憶力に自信がなくなった時には、「“ネギ”を繰り返し(!?)食べる」というのもあり!ではないのかな、と思います。
おまけに、“ネギ”は、今が旬の『冬野菜』です。
特に、“白ネギ(長ネギ)”は旬のピークを迎え、栄養価も豊富な時期なんです。
血行を良くして冷えたカラダを温め、疲労回復に効果のある野菜でもあり、「“ネギ”をたくさん食べると風邪をひかない!」とも言われます!
このような様々な効果が見込める旬野菜の“ネギ”を使って、これから追い込みの時期を迎える受験生のお子様に繰り返し食べてもらえるように、【ネギ味噌】の提案です。
“ネギ”だけではなく、受験生の味方の『ツナ』も使いますよ。
「魚を食べると頭が良くなる」のもご存じもことと思います。
魚に多く含まれる必須脂肪酸のDHA=ドコサヘキサエン酸は、脳の神経細胞の主な成分となって神経伝達をスムーズに行い、記憶や学習などの脳の働きを高めると言われていますから、お手軽にツナ缶を使って、脳活ポイントのW効果を狙います~♪
アツアツのごはんのお供やおにぎりの具、茹で野菜等とともに‘ねぎあん’で食べることもでき、使い用途はたっぷりの【ネギ味噌】なので、題して【頭にいい味噌】=‘脳みそ’です。(笑)
繰り返し【頭にいい味噌】を食べて、短期的な記憶の反復で記憶力のアップを目指しましょう!

【頭にいい味噌】 3~4人分
・青ネギ 300g(2袋)
~白ネギでもOK!
・ツナ缶 210g(3缶)
・しいたけ 100g(1パック)
・すりごま 大さじ2
●味噌 大さじ1
●みりん 大さじ1
(●を合わせておく。)
・醤油 少々
①ネギ、ツナ、しいたけをサッと炒めて、●を少々の水と共に入れて炒め合わせる。
②すりごまと少々の醤油で味見をして完成です。
“さつまいも”を召し上がれ~!
ちょうど今が旬の「さつまいも」!
お子様によっては、『お芋掘り』等で、「さつまいも」を持って帰って来られることもあるのではないでしょうか。
「さつまいも」には、食物繊維が豊富!ということはご存じだと思います。
そのため、「さつまいも」は腸活に有効で、便秘に悩む人は積極的に取った方がいい野菜だという認識もバッチリ~♪
でも、「さつまいも」の効能は便秘解消だけじゃないのですよ。
なんと、脳にとっても、良い野菜で脳の活性効果があるんですって。
「さつまいも」には、食物繊維だけではなく、糖脂質の成分が豊富に含まれているそうです。糖脂質の成分は、高等動物や植物の細胞膜の成分でもあり、脳や神経組織にも多く含まれる神経機能や細胞膜が営む様々な機能に関与する成分とのことです。
難しい言葉が並んでいますが、脳のためにも大切な成分だということが読み取れます。
そして、この成分をたくさん含む野菜が「さつまいも」なのです。
ちなみに、ジャガイモにも含まれているようですが、「さつまいも」には、なんとジャガイモの500倍以上が含まれているということですから驚きです!
(ちなみに‘ガングリオシド’という成分だそうです。)
この成分には具体的にどんな働きがあるのかと言いますと、脳の神経細胞のネットワークを広げて、情報伝達をスムーズにする働きです。脳の情報伝達が素早くできたり、記憶力も上昇するということですから、気になりますね~!
また、「さつまいも」はビタミンCが豊富で、加熱しても壊れにくいだけでなく、ビタミンB1もたくさん含まれています。ビタミンB1も脳に必要な栄養成分で、ビタミンB1は脳にとってのエネルギー源であるブドウ糖の代謝(エネルギーに変わること)に欠かせないビタミンなので、疲労回復にはもちろん、イライラや食欲低下を防いでくれます。
先述したとおり、「さつまいも」は食物繊維が多いので、整腸作用があり、腸内環境を整えます。腸内環境を整えるということは、免疫力を強化することにもつながるので、免疫力がアップされると、今の時期には大敵の風邪などのウイルスにも負けないカラダになるということですから、積極的に食べたくなる~♪「さつまいも」です。
そこで、今回のご紹介レシピは【大学芋】!
簡単レシピで、ポイントさえ押さえたら、カリッカリの【大学芋】ができあがります。
オーブンを使いますから、気負いなく作れますよ。
最近、このレシピをお伝えした友人宅で、流行りまくっている人気の【大学芋】なんだそうです~♡

【オーブンで大学芋】2~3人分
・さつまいも 2~3本分(700g位)
・サラダ油 大さじ2~3
- 砂糖 40g
- 水 30g
・黒ごま 大さじ2~
①さつまいもは、お好みの形で食べやすい大きさに
切り、水にさらす。(アク抜きです)
②①をザルに上げて水を切ったら、キッチンペーパーでよく水分を拭き取る。
ビニール袋にサラダ油と共に入れてしっかり混ぜ合わせたら、オーブンの天板に並べる。
③オーブンは250℃で予熱を入れて、15分~20分で火を通す。
④フライパンに●を入れ、中~弱火でヘラを使って混ぜながら加熱する。
★沸々と沸騰させ、ヘラの道筋ができるまで、しっかりと水分を飛ばすのがポイントです。
⑤④の中に、③で焼き上げたさつまいもを入れてサッと絡めて、黒ごまを混ぜ合わせたらできあがりです。
★のポイントの水分が飛んでいないと、お芋がしんなりとしてしまいますから、要注意ですよ~♪
カラダ&心がポッカポカ!【茶碗蒸し】
急に冷え込んで来て、あっという間に秋の気配!と、言うよりも朝夕の寒暖差が大きくて~~、の日が続いているように感じます。こんなに寒暖の差が大きいと体調を崩すばかりでなく、「元気が出ない~」…と感じる事が多々ありますよね。
大人ばかりでなく、お子様だって、集中力が続かない、不安感が強い等々、そんな「元気が出ない~」精神的にもお疲れモードの時ってあるはずです。
食べることに興味も持てず~、おまけに食欲が落ちてしまっても大変です~!
漢方の世界では、血の不足や冷えによって、このようなことが起こるとされているようですよ。このような症状を感じていたりする場合は、食事内容を見直してみるのも、ひとつの方法としてはとても良いようです。
では、元気を出す食材には、どんなものがあるのでしょうか?
血の不足によって、精神的にも不安定になったりするということなので、「血を補う食材」を積極的に摂るようにするのは良い方法だと思います。
薬膳では、食材の組み合わせも重要とされるので、「血の巡りを良くする食材」と組み合わせるのがオススメ!なんですって。
*『血を補う食材』
・豚肉・牛乳・卵・干しぶどう・ナツメやプルーン・人参・黒ゴマ・黒砂糖etc.
*『血の巡りを良くする食材』
アーモンド・栗やぎんなん・ブルーベリー・黒砂糖・酢・酒etc.
料理を作る際に、組み合わせて取り入れてみてくださいね!
そして、『秋バテ対策』にも通じるところがあるのですが、冷えを軽減することの“じんわりの温め&リラックス”効果が大切のようです。
- カラダを“じんわり温める”ことで、血の巡りを良くする。
血の巡りを良くすることで、カラダの疲れやだるさ、コリの蓄積を防ぐことができます。さらに、副交感神経が優位になるような“リラックス”法で心とカラダをゆっくりと休ませるのがオススメなので、ぬるめのお湯(38℃~40℃くらい)にゆっくりとつかり、全身を温め、血の巡りを良くしましょう。~‘炭酸入り入浴剤’を活用することもカラダの芯まで温められます。
- カラダを温める食べ物の食材で「内臓冷え」の緩和をする。
色の黒っぽい食べ物(食材)、濃い食べ物は体を温めると言われています。また、地下でエネルギーを蓄えた食べ物も体を温めるとも言われます。寒い地方で産出された食べ物=秋~冬が旬の食材には、これらが多く含まれていますから、旬の食材にも要注目です。
そんな「元気が出ない~」時こそ、しっかりと栄養がありつつも喉越しよくツルッと食べられるメニューで、おすすめしたい【ほっこり★茶碗蒸し】はいかがでしょうか。
エネルギー強化のたんぱく質がふんだんに摂取でき、中に入れる具材によっては、如何様にも栄養満点になれる【茶碗蒸し】です。
わざわざ蒸し器で蒸さないといけないという面倒なイメージは抜きにして、レンジやフライパンで手軽に作れる【茶碗蒸し】です。卵と出汁を混ぜ合わせた卵液を容器に注いで、軽く茹でたお好みの食材を加え、レンジでチン!のレンジで作る【茶碗蒸し】なんですよ~♪

【ほっこり★茶碗蒸し】 2~3人分
・卵 2個
・出汁 390ml(和風だしの場合は小さじ1.5杯)
(卵液の基本は、卵1個に対して、出汁が150ml)
・薄口醤油 小さじ1
・みりん 小さじ1
・塩 小さじ1/3~
*お好みの具=鶏肉・人参・しめじ・椎茸・ほうれん草・栗・里芋・ちくわを入れました。
- 下味用 醤油 小さじ1、 酒 小さじ1
①お好みの具で、鶏肉・人参・しめじ・椎茸・栗・里芋等、先に火を入れておきたいものには、下味を付けてラップをかけ、レンジで火が通るまでチン!(量にもよりますが、5分位です)
②卵液を作る。卵を溶き、出汁と調味料を加えたものとを合わせて、ザルなどで濾しながら、ちょうど400mlにしておく。
③耐熱容器に具を入れ、卵液を流し入れてラップをかけ、レンジ200wで15分~、卵液が固まればできあがり!
また、上記のレシピと同様に、卵液と具材を容器に移して、フライパンに半分位の湯を沸騰させ、容器を置いて容器の蓋&フライパンの蓋をして、中火位で20~30分待つだけ!【フライパンで☆茶碗蒸し】です。
<ポイント>は、
・フライパンにキッチンペーパーを敷くこと(クッションになります!)。
・容器の蓋がない場合は、アルミホイルで代用できます。
・フライパンの湯は、最初グツグツに沸騰させておきます。
できあがりポイントは、中央部分に竹串を刺して、透明な液が出てくればOK!です。
やっぱり、食べることは<元気の源>ですから、「元気が出ない~」時こそのエネルギーチャージに持って来い!カラダ&心も温まる【茶碗蒸し】です~♪
『元気ミネラル』たっぷり!の栗
旬の食材が持つパワーってやっぱりスゴ~イ!んです。
しのぎやすい秋になると、案外カラダの不調を感じる人はかなりの人数に上るのだとか。
これは「冷え」が原因の、最近では体調不良=「秋バテ」と言われています。
この体調不良を緩和する働きが<大>の食材が、“秋が旬~♪の食材”=いも類・栗(ナッツ類)・根菜類など。カラダを温める効果がバツグンに優れているんですって。
中でも特に、「栗」!

「栗」の主成分はでんぷんです。でんぷんの豊富な食物というといも類や穀物ですが、「栗」のでんぷんは、樹上で収穫される浄化された貴重なでんぷんで、熱量は一番!少量で必要な栄養素をとることができ、少量で効率のよいエネルギーが補給できる食物なのだそうです。また、ミネラル類も豊富で『元気ミネラル』と言われるほどのようです。
『ミネラル』が豊富だと、
*頭、直感が冴える
*疲れにくい
*疲れ目が楽になる
*免疫アップ
*肩こり、腰痛、頭痛が楽になるetc.
さらには、受験生には嬉しい
★集中力アップ ★やる気が出る ★イライラ解消等の効果があるそうです。
そこで、今回は旬の「栗」を使ったレシピをご紹介します。
いつもの!?‘栗ごはん’から少しだけ変わった視点でつくるレシピです。
秋の旬の食材がたっぷりの炊飯器だけで作る簡単ピラフです!
『元気ミネラル』をたっぷりと召し上がれ~♪

<栗&きのこのピラフ> 3~4人分
・米 2合
・白ワイン 大さじ2
・固形コンソメ 1個
・塩 小さじ3/4
・こしょう 少々
・栗 100g(皮をむいた正味量)
・きのこ(しめじ・舞茸等 )100g~石づきをとってほぐしておく。
・玉ねぎ(みじん切り) 中1/4個
・人参(擦りおろし) Ⅰ/4本
・バター 小さじ1(1片分) ・パルメザンチーズ 大さじ1
・パセリ(みじん切り) 適量
①炊飯器に洗った米を入れて白ワインを加え、水を2合の目盛に合わせて加えます。
②コンソメ、塩・こしょうを入れて軽く混ぜ、きのこ・玉ねぎ・人参・栗・パルメザンチーズとバターを上にのせて、スイッチON!
(★コンソメは軽く砕き顆粒状にして、混ぜるのは調味料のみ!具材は上にのせるだけで混ぜません。)
③炊き上がったら、さっくりと全体をまぜて盛り付け、パセリをトッピングします。
脳の即効エネルギー源=【羊羹】
お勉強や仕事にとって一番大切なのは「脳」の働きです。
「脳」が疲れると集中力が落ち、思考や判断力も鈍ってしまいます。“午後になると甘いものが欲しくなってくる~~”というのはそのためかも知れません。
そんな「脳」をしっかり働かせるには、脳の栄養である‘糖分’の補給が必要なのです。
前回のコラムでもお話をさせていただきました『食事と食事の間に取る食べ物=“補食”』!小中高生、特にスポーツを頑張るお子様や脳の活性化が必須の受験生にとっては、朝昼晩の三食では摂取しきれない必要な栄養を補う食事だと捉えます。
『補食選びのポイント』は、
・低脂肪
・必要な栄養素が摂取できること
・手軽さ、携帯性
「脳」への栄養補給やリフレッシュ目的なら、なんと【羊羹】!が良いのだそうですよ。
【羊羹】は、一般的に小豆を主体とした餡を型に流し込み、寒天で固めた和菓子です。
寒天の添加量が多く、しっかりとした固さの‘練り羊羹’と、寒天が少なく柔らかい‘水羊羹’があります。寒天は、天草という海藻からできていて、植物性でノンカロリーなので、デザートやおやつに用いるには最適なのだとか。
【羊羹】の材料は大半が砂糖と小豆です!材料の多くが砂糖でできているということは、効率よく糖分の補給ができると言えるので、【羊羹】を食べて30分もすれば、リフレッシュできるそうですよ。
また、【羊羹】の主体である小豆には、糖質をエネルギーとして利用するのが早い特徴があり、疲労回復といった症状を改善してくれる効能があるということで、豚肉や鰤といった食品にも含まれるビタミンB1を多く含んでいるそうです。
そして、【羊羹】には、ドーナツやパンなどとは違い、油分がほとんど入っていないため、食べても太りにくいのだとか。
【羊羹】は「即効的なエネルギー源」で、疲れた際に摂取する食品として、栄養面から考えてもBEST!な食べ物なのです。
東京オリンピックの折にも‘コンビニ’が重宝されたという話題がありましたが、‘コンビニ’で売っている【羊羹】は「最高のガソリン!」という外国人のファンも多かったのだそうです~♪
そんな、【羊羹】の効能が手軽に得られるように、今回は、ご家庭でも簡単に手作りできる【水ようかん】のレシピをご紹介します。お子様にも手軽に栄養を補給してもらい『脳の即効エネルギー源』として取り込んでもらえるように選びました!

【水ようかん】 4~5人分
・こしあん 200g
・粉寒天 3g
・水 300g
・塩 少々(小さじ1/10程度)
①鍋に水と粉寒天を入れて、よく混ぜ溶かし、火にかけて沸騰したら、さらに中~弱火で1分混ぜながら煮る。
②火からおろして、こしあんと塩を入れ、よくかき混ぜる。(粗熱が取れるまで)
③あんが沈まなくなったら(あっという間ですよ!)、型に流し入れ、冷蔵庫で1~2時間冷たく冷やしてできあがり。
あっさりしていて、ひんやりとしているので、あんこが苦手なお子様でも美味しく食べてもらえそうです~♪頭もすっきり&シャッキリ!して、頭&カラダの栄養になること間違いなしです。
補食の活用~♪
食事と食事の間に取る食べ物を『間食=おやつ』と連想しがちですが、小中高生、特にスポーツを頑張るお子様にとっては『間食=補食』になります。朝昼晩の三食では摂取しきれない必要な栄養を補う食事だと捉えます。この事は、もちろんスポーツのみに限らず脳のトレーニングが必須の受験生にとっても適応すると思います。
『補食選びのポイント』
・低脂肪
・必要な栄養素が摂取できること
・手軽さ、携帯性
たくさん食べることは、カラダを大きくするためやエネルギーの補給には確かに有効です。
だからと言って、一度に闇雲に食べれば良いかというと、そうではありません。
人は一度に消化できる量が決まっており、たくさん食べればそれが全てカラダのために使われる訳ではありません。それどころか消化できずに体調を崩してしまったり、食べる事が億劫になってしまうお子様も…。これでは、せっかく頑張って食べた物も無駄になってしまうと言うものです。
では、どうすれば食べた物を無駄にせずに食事を楽しむ事ができるのでしょうか?
ここで『補食』の活用です。
1日の食事を朝昼晩の三食ではなく、何度かに分けて取ること。一食ではなく、1日分のトータルで栄養を考える事で、効率良く、無理なく無駄なく栄養を摂る事ができます。
一食で食べ切れないほどのごはんを無理して食べるのではなく、下校後の塾に行く前の小腹が空いた時に、おにぎりやパン等を食べたりする事で、1日に必要なごはん分の栄養を無理なく、効率良く摂ることができるようにします。それが『補食』なんですね~♪
おにぎり、パン、バナナ、羊羹やカステラ等の“エネルギー源(糖質)”を取ると良いと言われています。少しずつ手軽に食べられる事がポイントです。
ちなみに、我が家のBoysが受験生だった頃は、おにぎりを食べたり、冷凍うどんをチンして、卵と麺つゆを絡めて食べたり、食パンやバケットにシラス&チーズを乗せてトーストして食べたりしていました~(笑)。
スナック菓子や甘いケーキ、菓子パンなどもNGではなく、食事に影響のない量を時々食べる程度であれば、「心の栄養」と捉えて、楽しんで良いのでは~、と私は思っています。
あくまでも「心の栄養」なので、夕食はしっかり取る事が原則ですが~♪
お腹が空いているともっともっと食べたくなるものですが、栄養のある『補食』をお子様の適量を取らせてあげる事が『補食』の理想です。受験生のお子様は育ち盛りでもありますから、思いのままにお腹を満たすだけではなく、栄養のことも考えながら『補食』を上手に活用してみてください!
今回のレシピは、先程もお話させていただきました、お子様でもひとりで簡単に作れる我が家の(!?)【シラス&チーズのブルスケッタ】です。言わずと知れずの脳活栄養素でもあるシラス&チーズを使った、カラダのためにも必要な栄養をたっぷりと含んでいます。

【シラス&チーズのブルスケッタ】 1人分
・食パン 1枚
(カットしたバケットでもOK!)
・シラス 約50g
(・おろしニンニク1片分・醤油小さじ1)
・オリーブ油 大さじ1
・スライスチーズ 1枚
・黒こしょう&パセリ 適量
①食パンにシラスをのせてオリーブ油を垂らし、チーズをのせた上から黒こしょう&パセリをトッピングする。
②オーブントースターで焼成し、チーズが溶けたらできあがり!
★時間があって少し本格的にしたい場合=フライパンにオリーブ油を入れ、にんにくを炒め、香りが出たらシラス、醤油を加えてサッと炒めてみてください!それを食パンやバケットにのせて、チーズと黒こしょう&パセリをトッピングしてトーストすると美味しいですよ~♪
★パセリの代わりに、青ネギや大葉でもOK!です。
カラダの調子を整える!鍋のススメ
長い長いコロナ禍の生活に、またひとつお子様にとっても重大なデルタ株が加わっての新学期スタートです。
気分転換もできないまま、やる気がでなかったり疲れやすくなったり、また食欲不振やカラダのだるさなど覚える方も多いことでしょう。コロナに負けないためにもカラダの調子を整えて免疫力をアップさせることは、大きなポイント!のように感じています。
それでもなく、残暑だったり気温変動の大きいこの時期は、“体調を崩す鬼門”です。
さてさて、どのような事に気をつけたら良いのでしょうか。
疲労感やストレスの蓄積が、その結果アレルギー反応や自律神経の乱れなどを起こすと言われていますので、冷たい物を取り過ぎてカラダが冷えると新陳代謝の機能が低下し、また自律神経の失調により急激な気温の変化に対応できずに体調に悪い症状が出てしまうとのことです。と言うことは、対策としては、カラダの温度差をなくす事~(!?)。
食品面でのカラダの冷え対策も重要ですから、対策のひとつとして‘熱~い【ちゃんこ鍋】’をオススメします。
【鍋】は、一般的には冬の食べ物のイメージですが、大相撲の力士は季節に関係なく一年中食べています。アスリートは試合やトレーニングなどにより、カラダだけでなく内臓も疲れている場合があり、また冷えによる血行不良から胃の吸収力が低下して栄養不足になりがちなのだとか。【鍋】にすることで、カラダが温まって血行がよくなり、野菜等を生で食べるより消化が良くなります。
さらに、カラダの調子を整えるのに必要な栄養素はビタミンですから、【鍋】にしてたっぷりの野菜や肉等の食材を食べられるということは、たくさんの栄養をバランス良く摂り込むことができるということです。【鍋】に入れる食材によっては、栄養&効果は群を抜いて変わって来ますから、冷蔵庫内の余った食材をアレコレ考えながら使い回すのもちょっぴり楽しい感じもします。
そこで、今回は『今日の【ちゃんこ鍋】』と題しまして、まずは、【ちゃんこ鍋】に使った食材の栄養&効果を説明します。
*鶏のささみ=たんぱく質の他、肌のハリや艶を保つコラーゲンを多く含むので、肌乾燥の予防効果があります。季節の変わり目の“カイカイ”が減って気分も落ち着くはずです。
*ほうれん草、人参=ビタミンAが含まれ、皮膚や喉、鼻などの粘膜を守り、風邪の予防にも役立ちます。(現在、ほうれん草等葉野菜が高騰しているので、冷凍野菜です)
*キャベツ=ビタミンCが多く、風邪予防をはじめ、疲労回復効果があります。
*エノキ茸=きのこ類全般ですが、ビタミンB1、B2、食物繊維を多く含み、冷え症やダイエットにも効果があります。
*木綿豆腐=不足しがちなカルシウムを多く含み、たんぱく質強化でエネルギーUP&持久力をUPします。
*出汁は“しょうが白湯”=‘鍋の素’を使いました。(簡単にできるのがお鍋の良いところです)そこに生姜の千切りをたっぷりと入れて、発汗作用でカラダをポカポカにしながら代謝をアップします。
*白ごま=たっぷりと振りかけて、ビタミンの吸収を高めるミネラル効果を発揮します。
野菜を加熱することで、ビタミンB1が水に溶けやすくなるので、鍋の出汁ごと食べることで、栄養成分がカラダに取り入れやすくなるのが、【ちゃんこ鍋】の良いところですね!

『今日の【ちゃんこ鍋】』
・鍋の素のポーション 適量
・今日の食材 適量
鶏のささみ、ほうれん草、人参、キャベツ、
エノキ茸、木綿豆腐、生姜、白ごま
【ちゃんこ鍋】がなぜオススメなのか、少しわかっていただけたでしょうか(!?)
【ちゃんこ鍋】は栄養バランスが良く、低カロリーで良質なたんぱく質も取れるので、風邪予防にもアスリートのようなエネルギー強化にも優れた料理です。お相撲さんが一年中元気で闘えて、またお肌も美しい~♪のは、【ちゃんこ鍋】でカラダを温めながら汗もかきかき体調を整えているからなのだな~、と私は思います。
【台湾肉味噌】で食欲UP!
毎日うだるような暑さが続くと、食欲も落ち、冷たいものやあっさりしたものしか食べられないというのも仕方がないことかもしれません。でも、こんな食事が続いてしまうと、カラダに‘疲れ’と‘だるさ’を感じてしまい、「集中力が低下する」という悪循環が起こってしまいます。これは、いわゆる『夏バテ』の主な症状なんだとか~。
夏の暑さが原因で、汗が蒸発するときの気化熱がカラダのエネルギーを奪って行き、その負荷が原因で、カラダが疲労してしまうらしいのです。また、夜中も暑くて熟睡できなかったり、冷房で屋内と屋外の温度差が激しくなったりすることが原因で、自律神経系の乱れも大きくなってしまうとのことです。そんな症状に見舞われないためには、『体力の回復』が必須です。そのためには、バランス良く食事をすることが大切です。
そこで、夏休みのお子様に食べさせたい‘食欲の出る食事は~(!?)’と考えて、いろいろな物にアレンジの効く【台湾肉味噌】に注目してみました。最近、何かと“台湾グルメ”や“台湾スイーツ”というワードを耳にすることが多いように感じます。台湾料理は台湾の風土や食材を活かしつつ、独自に発展した食文化だそうですが、中華料理や韓国料理よりも比較的、味付けがあっさりしたものが多いことから、日本人の口にも合いやすい味になるのだとか。醤油をベースとしている味なので、どこか食べ慣れた懐かしさも感じられるのが魅力的なのかもしれません。【台湾肉味噌】は、そんな台湾グルメの食べやすい味付けながら、パンチの効いたピリ辛ミンチで、麺やごはん、豆腐に乗せたり、混ぜたり和えたり、野菜で包んで、サンドイッチや焼きそばに~、と格別に美味しい食べ方がいろいろです!お家時間で、暇な時間がある時にでも作り置きをしておけば重宝すること間違いなしです。疲労回復に欠かせないビタミンB1がたっぷりの豚ミンチに、ニラや白ネギ、生姜やにんにくを多めに入れて作りますから、いろいろなアレンジ自在の食べ方で、食欲不振なんて吹っ飛んでしまうはずですよ~♪

【台湾風肉味噌】 2~3人分
・豚ミンチ 200g
・ニラ 1束(小口切り)
・長ネギ 1/2本(みじん切り)
・にんにく、生姜 各1片(みじん切り)
- 豆板醤 大さじ1
- オイスターソース 大さじ2
- コチュジャン 大さじ1
- 砂糖 小さじ1
- 鶏ガラスープの素 小さじ1/2
- 料理酒 大さじ2
・ごま油 小さじ2
*お好みで花椒or五香粉 小さじ1
①●の調味料をボウルに合わせておく。
②フライパンにごま油を入れ、にんにく・生姜・長ネギを炒め、豚ミンチを入れてパラパラになるまで火を通す。
③②に①の●を入れて、水気がとぶまで炒め合わせる。最後にお好みで、*を足し入れる。

今日の我が家のランチは【台湾風混ぜそば】!
【台湾風混ぜそば】はうどんを茹でて、ミンチ肉のピリ辛味を少し緩和させるために、茹でたもやしとチンゲン菜、温泉卵をのせました。汁なしだと、スパイシーになるので、温泉卵をトッピングするのがポイントですよ!
ラーメンに乗せたら、名古屋名物の【台湾ラーメン】!汁ありのソーメンやうどんにミンチ肉をのせた方がスパイシーさは薄れて、ピリ辛の苦手なお子様には食べやすいかもしれません。
【夏野菜】の秘められたパワー!
毎日、うだるような暑さで早くも夏疲れ気味のお子様方も多いかもしれません。
夏休みとは言え、ここ数年の異常な暑さは大人だけでなく、お子様だって“夏バテ対策”や“夏疲れ回復対策”は今や常識です。コロナ禍の生活習慣の変化も原因のひとつで少なからず影響を与えているようですが、そんな夏休みを元気に過ごし、受験期の後半戦に向けて頑張れる夏休みにするためにも、毎日の食生活は大切にしたいものです!
そんな夏には、人のカラダが必要とする効能効果の期待できる【夏野菜】が多く出回ります。夏はとても暑いです。そのため、カラダは火照り、熱がこもってしまいます。
なので、水分をしっかり取らなかったら熱中症、脱水症状を引き起こします。
“熱中症対策”も、毎年非常に心配が大きいところですよね。
夏に大きく育つ「夏野菜」には、水分を供給してくれる野菜が多く、火照ったカラダを冷やしてくれて利尿作用に効果を発揮して、カラダの循環を非常に高めてくれるパワーを秘めています。
四季の中で、最も代謝が高まる季節ですから、水分を摂り、カラダの循環作用を高め、体内の毒素を排出するのはとても大切なことです。
これは室内に入ると涼しい環境が整っている現代では、体温調整としても効果があるため非常に重要なのだそうですよ。
それを担ってくれるのが、【夏野菜】なんですね~♪
夏に収穫して夏に食べる野菜だから、【夏野菜】と言われるのですが、季節と野菜は、本当にもの凄いバランスで構成されているな~!とつくづく感心させられてしまう瞬間です。
ちなみに【夏野菜】には、トマト・茄子・きゅうり・かぼちゃ・冬瓜・とうもろこし・ゴーヤ・枝豆・インゲン・ニラ・オクラなどがありますよ。

<【夏野菜】の秘められた5つのパワー>
1食物繊維:カラダが綺麗になると代謝が上がり、血行が良くなることで栄養が全身に行き渡り、健康にも美容にも効果的とされています。
2ビタミンC:抗酸化作用が高く、活性酸素の過剰発生を防ぎ、健康な肌細胞を守る働きがあります。その為、紫外線からのダメージを抑制してくれます。
3ビタミンE:体内の器官や各部位、細胞の老化を防ぐことから、各器官の働きが向上し、病気知らずの健康体となり、キープすることができます。
4カロテン:抗酸化ビタミンの一種です。
5カリウム:血圧を安定させ、筋肉の働きを良くします。夏場は汗とともに一緒に外に放出されてしまうので、夏バテの原因とされているので、摂取が必要です。
とにかく【夏野菜】は栄養満点!旬の【夏野菜】は味が濃くて香りも良く、夏バテ予防や胃腸対策、紫外線対策にも効果的なものがたっぷりです。そこで、【夏野菜】の栄養を効果的に摂取するための方法をご紹介!それは、【夏野菜】をしっかりと食べること(笑)!!
暑い夏は、どうしても食欲が減退してしまいますから、「しっかりごはんを食べてほしい!」ので、お子様みんなが大好きなカレーに【夏野菜】をふんだんに取り込んだ栄養満点のレシピにしてみました。ポイントは、いつも使っているじゃがいもを‘冬瓜’に変えて、トロンとやわらかい食感のカレーになったこと!より一層マイルドな【夏野菜】たっぷりのカレーは、お子様にもしっかりと食べてもらえること、間違いなし!です。

【「夏野菜」たっぷりカレー】 4人分
- 冬瓜 1/4個~食べやすい大きさにカット
- 人参 Ⅰ/2本~乱切り
- パプリカ Ⅰ/2個~食べやすい大きさにカット
- 玉ねぎ 小1個 ~くし型切り
- ズッキーニ、なすび、トマトetc. 各1/2個 ~サイコロ状にカット
- 合挽きミンチ 200g
・ニンニク&生姜 各1片(みじん切り)
・オリーブ油 適量
(・クミンシード 小1/2~お好みですが、ちょっぴり本格的になりますよ♪)
・オクラ(固めに下茹で) 4本 ~斜めに3等分位にカット
・水 600~700cc
・和風だし 小さじ1
・カレールー 1/2箱:約70g(お好みのもの)
①鍋にオリーブ油とニンニク、生姜、あればクミンシードを弱火で炒め、香りが出てきたらミンチを入れて炒め、色が変わったところで●をすべて入れて炒める。
②野菜がしんなりしてきたら、水と和風だしを入れて煮込み、カレールーを入れてできあがり。=ご家庭のカレーの作り方でOK!
*ごはんにコーンを入れてコーンライスや、バターライスにしても美味しいです。
*いつものカレーですが、野菜がやわらかく、あっさりといただけますよ!
*うどんやソーメン、パスタとともに、つけ麺風のカレーバージョンにしてもお子様に受けること間違いなし!です。
“夏バテ”対策!のサラダ麺
むし暑い日が多くなって来ました!
胃腸の調子が悪くなったり、ダルさが出てきたり、食欲も落ちてきたりと、そろそろ“夏バテ”が心配になってくる季節です。
「子供に“夏バテ”は無関係」なんて、思っていませんか。
子供の“夏バテ”対策も今や常識!
ここ数年の異常な暑さも原因のひとつのようですが、生活習慣の変化も少なからず影響を与えているようです。
「一見元気だけど、どうも食欲がない…」。
そんな状態は“夏バテ”の初期症状かもしれません。
食欲不振が全身のダルさや倦怠感などにもつながって、しかも熱帯夜には寝不足になったりしますから、夏の連鎖に陥ってしまっていわゆる“夏バテ”になってしまうようです。
そんな“夏バテ”予防には、「酸っぱいもの」=‘クエン酸’が良いと聞いたことはありませんか。
‘クエン酸‘が含まれる身近な食材には、梅干し、酢、レモン、柚子やグレープフルーツ等々の柑橘類、「酸っぱい系」の食べ物に‘クエン酸’は含まれていますよ。
★‘クエン酸’がカラダにいい理由
①酸っぱさが食欲増進!
酸っぱい→胃が活発になる→食欲アップで食事がしっかり取れる→栄養満点に!
“夏バテ”になってしまう前から、このサイクルを作ることで、体力や免疫力が落ちたとしても“夏バテ”に陥ってしまうことを防げます。
②「‘クエン酸’回路」の働きを助けて疲労回復!
食事で摂った栄養素をエネルギーに変えるための活動を「‘クエン酸’回路」と言うそうです。体内に‘クエン酸’がしっかりとあれば、「‘クエン酸’回路」の働きが正常になり、それによって、食べたものをエネルギーに変える働きが活発になり、疲れが残りにくくなって、疲労回復の効果が期待できるそうです。
★‘クエン酸’=梅干し最強説(!?)
むし暑くなってくると心配になる「熱中症」。
「熱中症」の原因のひとつには体内の塩分が不足してしまう事が挙げられます。汗と一緒に体内の塩分‘ナトリウム’が出ていってしまい、血が薄くなってしまいます。そこで、梅干しを食べて塩分を摂るということは、‘クエン酸’以外にもビタミンやミネラルを摂取できるので、「熱中症」の予防にもなるということでベスト!
でも、‘クエン酸’だけ取っていてもダメ!
「‘クエン酸’の効果を高める」「“夏バテ”予防をする」というのであれば、【‘クエン酸’+ビタミンB群】の組み合わせを考えた献立にすると、“夏バテ”予防の効果がアップするそうです。‘クエン酸’だけ摂っていれば良いというわけではないんですね~。
また、お子様の食欲不振の時には、ビタミンB群だけを取り入れるのでなく、たんぱく質も食材に加えるといいようです。
ちなみに、ビタミンB群の疲労回復の代表食材は豚肉、たんぱく質には鶏肉や卵などが挙げられます。
‘クエン酸’と疲労回復の関係性を知っていただいたところで、これから始まる長くて暑~い夏休みのランチメニューに、また、食欲がない時でも簡単に食べられて“夏バテ”予防の対策として食事に取り入れていただけそうな、栄養満点の【サラダ麺】のご紹介です。手作りの【万能☆ゴマだれ】も添えてみました~♪

【サラダ麺】 1人分
・今回はうどん 1玉(ソーメンやパスタでもOK!)
・豚しゃぶ肉 150g
*梅干し 1個
*麺つゆ 50~100cc
・オクラ、茹でキャベツ、ブロッコリー、トマト、
玉ねぎスライス、貝割れ、大葉、白髪ねぎetc.

- 【万能ゴマだれ】 適量
・すり胡麻 大さじ1
・マヨネーズ 大さじ1
~この2つは胡麻ドレッシングで代用OK!
・ぽん酢 大さじ2
・麺つゆ 大さじ1(醤油でもOK!)
・ごま油&食べるラー油はお好みで!
①オクラをサッと茹でた後、細く斜め切りにしておく。
うどんも茹でて水でしめて冷やしておく。キャベツ、ブロッコリーは食べやすい大きさに切って、お好みの硬さに茹でておく。
②豚しゃぶ肉も茹でて水でしめておく。
~*薄く片栗粉をまぶしてから熱湯に入れてすぐに火を止めて、余熱で茹で上げると
やわらかいお肉に仕上がりますよ!
③梅干しは種を取り除き、細かくたたいて*の麺つゆと合わせる。
④【ゴマだれ】はすべてを混ぜ合わせるだけ。
⑤その他の野菜はお好みにカットし、①のうどん共々、キャベツ等と盛り付けて、しっかり冷やしてお召し上がりください!③のつゆはお肉の上からたっぷりと回しかけても、つけつゆにしてもOK!④のゴマだれもお好みで回しかけながら、または浸けながらいただきます。~★広島風つけ麺のようなお味ですよ!
頭の良くなる食材!?=【ツナ缶】
普段のストック食材として、または、イザっ!と言う時の非常食や簡単時短料理の便利食材として、家庭で常備している缶詰のトップランキングに常に上がってくる【ツナ缶】!
【ツナ缶】は青魚のサラサラ成分として注目されているEPAやDHAを豊富に含むことで知られています。カラダの健康だけでなく、脳の健康(=脳活)のための働きにも意外とオススメなのが【ツナ缶】なのです。
お勉強に頑張る受験生には積極的に取ってもらいたい“頭の良くなる食材”のひとつです。
そんな【ツナ缶】ですが、マグロやカツオなどいろんな種類があることをご存じですか!?
“ツナ”とは、まぐろのことで、「【ツナ缶】といえばマグロ」というイメージを持っている方も多いはずです。確かに、【ツナ缶】の原料として長らくマグロが使われて来ましたが、マグロの世界的な高騰により、現在ではマグロを使った缶詰だけでなく、カツオを使った【ツナ缶】の流通が多くなっているそうです。ご存じのとおりマグロにはEPAとDHAという成分がたくさん含まれています。~<塾デリカ>でも頭の良くなる食材としてよく登場する魚に多く含まれるEPAとDHAです!
EPAには体内の過剰な免疫反応や炎症などを抑制する効果がある成分で、DHAには‘脳に良い’というイメージのとおり、記憶や感情、行動といった精神活動に深く関わっている成分と言われています。
マグロが使われていないカツオの【ツナ缶】でもEPAやDHAはOKなのでしょうか(!?)
なんと、文部科学省『日本食品標準成分表2015年版』の成分表によると、マグロはマグロでも‘キハダマグロ’だと、DHAの含有量は“カツオ”の方が5倍近く多くなっています。
これが‘ビンナガマグロ’だと“カツオ”よりも多いので変わってくるし、EPAの量もまた違うので一概には言えないのかもしれませんが、とにかくEPAやDHAの含有量の多い食材と考えると【ツナ缶】はマグロでもカツオでも“頭の良くなる食材”のひとつとしてやっぱりポイントのようです。
缶詰になってもEPAとDHAは失われず塩分もとても低いですし、【ツナ缶】の主流は「油漬」タイプなのですが、ヘルシーで健康志向の方向けには「水煮」(ノンオイル)タイプも作られています。ちなみに、「油漬」は調味料の半分以上が油で、オリーブオイルやアマニ油などを使ったものも登場していますが、一般的には大豆油を使ったもののようです。また、「水煮」は油の代わりにマグロやカツオ、野菜エキスなどを使用することで風味を損なわずにカロリーを抑える工夫がされているようです。
ということで、手軽にEPAやDHAが摂取できる【ツナ缶】!【ツナ缶】は子供から大人まで万人受けする食材ですし、とても便利で使い易い万能選手!使い方を工夫すれば、サラダはもちろん、煮物や和え物、炒め物等なんにでも使えてアレンジの幅が無限大~~。時短料理かつ受験生の母にとっても最高のパートナーとなってくれそうですね~♪
そんな‘スーパー食材’の【ツナ缶】レシピをいくつか紹介してみましょう!
チャッチャ!と作れて、なおかつ栄養価の高い【ツナ缶】を食事として、腹ごしらえやお弁当の一品に登場させてみませんか。

【ツナマヨパスタ】 2~3人分
・お好みのパスタ 200g
・ツナ缶(小) 2缶
・玉ねぎ、人参 1/2個
・ピーマン 1個
・炒め油 大さじ1
- マヨネーズ 大さじ1~2
- 醤油 大さじ1~1.5
①野菜はお好みサイズでカットし、ツナは油分を切っておく。
*我が家は野菜は千切りにし、ツナの油も炒め油に足して使います!
②●をボウルに合わせ、パスタを茹でる。
*パスタの茹で汁に分量外の醤油を垂らして茹でると、しっかり味のあるパスタに!
③フライパンに炒め油を入れて、野菜を炒める。
④野菜に火が入ったら、●を加えてサットと混ぜたら火を止め、茹で上がったパスタの水を切り、混ぜ合わせたら完成です。

【ゴーヤ&ツナサラダ】 2~3人分
・ゴーヤ 1/2本
・ツナ缶(小) 1缶 ~オイルをきっておく。
・玉ねぎ 1/2個 ~薄切りにして水にさらしておく。
・にんじん 1/4本(千切り)
・塩こしょう 少々
・マヨネーズ 大さじ2
・醤油 適量(調整分)
①ゴーヤは種とワタを取り出し、薄切りにして塩もみをし、サッと熱湯で湯がく。*ゴーヤの苦味取りの方法です!
②この時、にんじんも一緒にサッと茹でてザルに取り、しっかり水気を切っておく。
③水切りした玉ねぎ・にんじん、ゴーヤをボウルに入れて塩こしょうし、マヨネーズで和える。味見をして醤油で調整してできあがり!
★余った時のアレンジとして、サッと油で炒めてから卵で炒め絡めると、【簡単ゴーヤチャンプル】です。

★他にも、ご家庭の味の「肉じゃが」の肉をツナに代えて、【ツナじゃが】!

★「炊き込みご飯」の具材を塩昆布&ツナで、【ツナ&塩昆布のごはん】*おにぎりにしても美味しいです!
【バナナ】のお話
最近街中などでよく見かけるようになった「バナナジュースの専門店」。
以前から「フルーツジューススタンド」はありましたが、バナナジュースに特化したお店は最近のブームのようです。
実際に【バナナ】は。腹持ちが良い食品で、皮も簡単に剥けるので、衛生的な取り扱いも簡単です。そんな【バナナ】の歴史は古く、仏典にも【バナナ】の果汁が薬用の飲料として記載されているのだとか。昔から滋養強壮の果物とされ、栄養面から見ても優れた特性を持っている【バナナ】です。
たんぱく質、カロリーはじゃがいもに匹敵し、ビタミン、カロテンやカリウム、食物繊維などを豊富に含んでいます。エネルギー補給だけではなく、疲労回復やパワーチャージにもバッチリ!で、コロナ禍の紛らわしい風邪対策や免疫力アップにも期待が持て、【バナナ】の持つマグネシウムのマル秘パワーが、ウイルスと戦う免疫細胞の働きを強化するとも言われているようです。しかし、マグネシウムは汗と流れ出やすいものなので、これから益々暑くなる夏に向けてはマグネシウムが必要になるので、【バナナ】を1日1本(約120g)食べると良いそうですよ。食べるタイミングとしては、いつでもOK!で、ジュースなど手を加えても【バナナ】の栄養は変わらないそうです。
また、おもしろいな~と興味を持った【バナナ】の記事を発見しました。
それは【バナナ】の熟度によって、効能効果があるということ!
『茶色いバナナ=免疫や腸内環境』、『黄色いバナナ=アンチエイジング』とも言われているようで、~知りませんでした。
【バナナ】は熱帯性のフルーツなので、保存する時は必ず室温で保存し、冷蔵は禁物です。
接地面から黒くなっていくので、接地面が少なくなるように保存をしてみてください。
そんなメリットがいっぱいで、みんな大好きな【バナナ】を使って、今回は簡単に、ひんやりふわふわスイーツに変身させてしまいました~♪
もちろんバナナジュースも良いのですが、せっかくなので、【バナナプリン】にしてみましたよ。【バナナ】と牛乳があれば、ひと手間のゼラチンなしでも‘プリン’ができるんです。←実験感覚ですね!

【バナナプリン】 カップ3~4個分
・バナナ 大きめ2本 ~約200g
(斑点があるものが◎!)
・牛乳 100cc
・レモン汁 大さじ1
①バナナは皮を剥いて、レンジで600w2分くらいチン!する。
~この時、バナナからジュクジュクと小さな泡が出て、とろけている感じです。
②牛乳と①のバナナ、レモン汁を入れて、ミキサーにかけ、水で濡らしたカップに注いで、
冷蔵庫で冷やし固める。(3時間~半日程度)
*カップから外してもOK!ですし、器のままでももちろんOK!~♪
*きな粉やココアを小さじ2プラスして、プリンのアレンジもできますよ。
『黄色いバナナ』はそのままで、『黒くなったバナナ』は、完熟バナナの救済にも役立てて(笑)、免疫アップを計るとともに、ぜひ【バナナプリン】で召し上がってみてください。
鶏ムネ肉でパワーチャージ!
食べないなんてもったいない!‘鶏ムネ肉’の意外な効果をご存じですか。
‘鶏ムネ肉’は高タンパクなのに、低カロリーで低脂肪、良質なアミノ酸もバランス良く含まれているので、アスリートやダイエッターにもお馴染みの‘鶏ムネ肉’です。
もちろん今年1年間、お勉強に邁進するお子様にもバッチリ!で、いろいろな料理の場面であえて‘鶏ムネ肉’を使うことで、パワーフードになっていきます。
なぜ‘鶏ムネ肉’が受験生の最強のパワーフードになり得るのかという理由ですが、闘い(!?)につきものの「肉体と精神の疲労に持って来い!」の食材だからなのです。
『なぜ、渡り鳥は休まずに何千キロも飛び続けられるのか?』
普通に考えて、何千キロも飛び続けるなんてスゴイことですよね。
実は、渡り鳥がずっと飛び続けていられるのは、彼らの体の中に含まれる抗疲労成分=「イミダペプチド」が影響しているということらしいのです。
「イミダペプチド」は、疲労回復や運動能力のアップを助けるアミノ酸として効果が期待されていて、健康予防医療産業振興プロジェクトが渡り鳥の生態を分析し続けた結果、鳥の羽を動かす周辺にこの成分が多く含まれていることが分かったということです。
羽を動かすのに最も力を使うムネ周辺に疲労を感じずに居続けられることで、渡り鳥が休まずに長距離を飛び続けられるパワーが備わっているということらしいですよ。
これは、お子様にもパワーフードとして、日々の食事で取り込まない手はありません!
1日100gの‘鶏ムネ肉’を摂取することで体内に発生した活性酸素を除去し、日常の疲れを防止することができるとされています。さらに脳の活性化にも効果があるらしく、疲労回復のみならず、持続力=集中力、記憶力にもバッチリ!となると、‘鶏ムネ肉’でパワーチャージをしたくなりますね。
‘鶏ムネ肉’はパサパサ感が気になると言われる方がいらっしゃるかもしれませんが、筋繊維を崩すようにそぎ切りにしたり、塩水(1~2%の濃度)やヨーグルトに漬けたり、片栗粉をまぶして調理する等、ひと手間を加えるとふっくら柔らかい食感に仕上げられます。
今回は、スーパーやコンビニなどで最近良く見かける【サラダチキン】のレシピのご紹介です。~今更かもしれませんが(笑)
一度作っておくと、手軽にそのまま食べられるだけでなく、料理にも使えるので便利ですよね♪

【炊飯器で!チキンサラダ】
・鶏ムネ肉 1~2枚
・料理酒 大さじ1
・マジックソルト 大さじ2~
(ハーブの入った塩ですが、ない場合は普通の塩+鶏ガラスープの素で代用できます)
①皮をはがし、筋繊維を崩すようにフォークで適度に差し込んでおく。
②料理酒とマジックソルトを片面ずつまぶす。(ソルトは全体がザラザラになる程度に!)
③ジップロックの袋に②を入れて、
密封して空気を抜く。
④袋ごと炊飯器に入れ、熱湯を袋が浸かるくらい注ぐ。
⑤炊飯器の“保温スイッチ”ON!で、1時間程度保温で放置したら完成です。
★我が家の炊飯器は、保温放置ができなかったので、“パン発酵スイッチ”ON!でやってみました。~40分程度で完成しました!
鶏ムネ肉でもう一品!お弁当や一口おつまみにもOK!の簡単な【マヨ焼き鳥】です。
【マヨ焼き鳥】 2~3人分

・鶏ムネ肉 1~2枚
<下味>・塩こしょう 少々 ・酒 少々
・マヨネーズ 大さじ1
・片栗粉 大さじ1
・醤油、 少々(仕上げ用)
・長ネギ 食べやすい大きさで適量(付け合せ用)
・塩 少々(トッピング用)
①ムネ肉は皮を取って、食べやすい大きさに削ぎ切りにしていく。
②ビニール袋に①と下味を入れて揉み込む。片栗粉も入れて馴染ませる。
③フライパンに油をひき、②を並べて焼いていく。下側に焼き色が付いたら、ひっくり返して、弱火にしフタをして、お肉に火を通す。(2分位~)
★楊枝に②のお肉をバランスよく刺して、間に長ネギを刺してもOK!
④火が通ったら余分な油を拭き取り、醤油を回し入れて、お肉にサッと絡めてできあがり!
★お皿に盛ったら、塩をふるのがポイント!です。
お好みで、マヨネース&七味唐辛子、青のり、すり胡麻等をつけていただきます。
★フタをして焼くのが、パサつかず、ふっくらとやわらかく仕上がるコツですよ♪
疲労回復に最適★アスパラガス!
春から夏にかけて味わえる旬の“アスパラガス”が出回る季節になりました。
“アスパラガス”はハウス栽培のものと露地栽培のものがあり、含まれる栄養分も違ってくるそうです。この時期の“アスパラガス”は緑鮮やかで丸々と太っている露地栽培のものが圧倒的に出回ります。
この季節の“アスパラガス”を逃すともったいない理由が~~。
“アスパラガス”は元々、栄養価が高いのですが、春の日差しを浴びて育つこの時期の“アスパラガス”は、1日に5~10㎝も生長するほどパワフルなんですって。
この露地栽培ものは、ハウス栽培ものとは見た目はそれほど変わりませんが、栄養分は格段に優れています。“アスパラガス”は、葉っぱや枝が出る前の成長細胞の若芽を食用として楽しむ緑黄色野菜で、若芽というだけあって、粘膜を保護し、免疫力を高める働きのあるβカロテンやビタミンC、カリウム等がたっぷり含まれていて、穂先には、抗酸化力のあるポリフェノールの一種が含まれているため、血管を丈夫にするとされています。また、新陳代謝を活発にし、疲労回復に役立つアスパラギン酸も含まれています。
アスパラギン酸は名前のとおり“アスパラガス”の細胞から見つかった栄養素なんですよ。「疲労回復に~!」の栄養ドリンク等に入っているのをよく目にする、あのアスパラギン酸です!
また、受験生に嬉しい栄養も、た~っぷり~♪
“アスパラガス”から抽出されるアスパラガスエキスには、GABAが多く含まれているのです。GABAには、血圧を正常に保つ働きがあるので、精神的にも落ち着かせてくれて、集中力もアップする働きがあります。
せっかくの栄養分ですが、調理法によっては流失してしまうこともあるようですから、できるだけ逃さないようにすることが鉄則。栄養成分を効率的に摂るには、加熱しすぎはNGです。今の“アスパラガス”は甘味も強く柔らかいので、サッと茹でるかレンジで蒸すようにします。茹でる際には、ピーラーなどで根元の硬い部分の皮をむくと茹で上がりが早くなります。皮をむいたら大きめの鍋にたっぷりのお湯で切らずに根元の部分から一呼吸をおきながら、1分半から2分位を目安に茹でていきます。
レンジの場合は、ラップをして2分程度加熱します。火が通ったらすぐに冷たい水に取って熱が入り過ぎないようにするといいですよ。
“アスパラガス”は鮮度が命!美味しさと鮮度が比例するため、買ったその日に食べるのがベストです。鮮やかな緑色が、料理に彩りを添えてくれて、お弁当の添え野菜にも重宝しますし、スープにすれば逃げた栄養成分もそっくりそのまま摂れるので、おすすめです。
そんな“アスパラガス”を使ったおすすめレシピをご紹介しましょう。
【アスパラガスの肉巻き】です。“アスパラガス”のアスパラギン酸と、豚肉のビタミンB1で疲労回復にばっちりのメニューです!
忙しい時には、豚バラ肉で巻いたものを焼く(オイスターソース小さじ1程度で絡めます)だけで手早くできますが、今回のレシピは、豚ミンチでつくね風にしてみました~♪

【アスパラガスの肉巻き★つくね風】 2~3人分
・アスパラガス 1束(5~6本)
・胡麻油 大さじ1
<つくねの材料>
・豚ミンチ 200g
・白ネギ(ニラでもOK!)1/2本 ~みじん切り
・しめじ Ⅰ/3パック ~みじん切り
・生姜 1片 ~みじん切り
・溶き卵 Ⅰ/2個分 ・醤油 小さじ2
・片栗粉 大さじ1~
●醤油、酒、みりん 各大さじ2
●砂糖 小さじ2
①アスパラガスの下処理をしておく。 ●の調味料を合わせておく。
②つくねの材料をボウルに入れて、粘りが出るまで混ぜる。
③アスパラガス1本づつに、②をそのまま巻いていく。(やわらかいので手でムニュ~と言った感じで簡単に巻きつけられますよ!)
④フライパンに胡麻油を入れ、③を並べて焼き固めていく。焼き色が付いたところで料理酒(分量外)を少々ふりかけてフタをして、しばらく蒸し焼きにする。(Ⅰ~2分程度でOK。)
⑤つくねに火が通ったら、●の合わせておいた調味料を入れ、照りがついたらできあがり!
*ちょっぴり居酒屋風になるので、子どもたちやパパにもウケの良い一品になりますよ♪
“しらす”の魅力
春が旬の“しらす”!
GWの時期になるとニュース映像で、新鮮な“しらす”の【しらす丼】を求めて多くの人が行列している場面をよく見かけたものです。しかし、昨年に続き今年のGWもコロナ禍によるステイホームが叫ばれているものですから、現地に赴いて【しらす丼】を食べる~というのは、まだまだ厳しい感じです。
美味しい“しらす”などの小魚には、豊富な栄養が含まれていることは周知の事実~。
そこで、今回は“しらす”についてのお話です。
そもそも“しらす”とは、特定の魚ではなく主にカタクチイワシやマイワシ等の稚魚のことです。“しらす”は足が早いためスーパーなどで出回っているものは、水揚げした後すぐに茹でた「釜揚げしらす」が多い傾向です。一方で、乾燥させた“しらす”は「しらす干し」「ちりめん」といったように、乾燥の度合によって呼び方が変わります。
また、“しらす”は、骨を含む本体を丸ごと食べられるので、カルシウムをたくさん摂取できる食材です。油分が少なくあっさりとした味わいで、クセがなく食べやすいのも“しらす”の特徴と言えますし、“しらす”は栄養価が高く、食べることで様々な効果効能が期待できるのも魅力のひとつになっています。
<“しらす”に期待できる効能効果>
“しらす”に多く含まれるカルシウムは、骨や歯を作る成分です。
カルシウムを摂取することで、骨粗しょう症の予防やお子様の成長にも役立ちますし、受験生にはポイントとなる、集中力向上に欠かせない栄養素となってきます。
ちなみに、カルシウムの含有は“しらす”よりも、乾燥させたちりめんの方が多いということですが、“しらす”には、ビタミンDも豊富に含まれていて、ビタミンDにはカルシウムの吸収を助ける働きを持っているため、ともに摂取できるということでより一層カルシウムの強化が期待できるそうですよ。
また、“しらす”には、ビタミンB12という栄養素も多く含まれていて、脳神経や脳細胞の再生を促す効果があるそうです。“しらす”を食べることで自律神経を穏やかにし、不眠症や失調症などの症状をやわらげることが期待でき、その他にもカラダの疲労や体力の低下を引き起こす貧血を予防する効果もあるそうです。
どうですか~(!?)、“しらす”の魅力がわかっていただけたでしょうか。
“しらす”は、クセがなくて食べやすいだけでなく、カルシウムやビタミン類などの栄養を豊富に含んだカラダに良い食材だと言うことですねー!
そこで、今回はステイホーム中にお家で簡単に作ることができ、たっぷりと“しらす”を食べることのできる【しらす丼】を紹介します。
実は【しらす丼】にピッタリの、釜揚げしらすの絶品『特製だれ』のご紹介かもしれません~♪
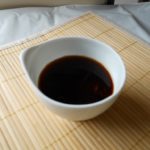
【しらす丼の『特製だれ』】 2~3人分
●釜揚げしらす 30g
●料理酒 30ml
●みりん 20ml
●水 30ml
・醤油 20ml
①鍋に、●を入れて強火でひと煮立ちさせる。
②弱火にして、約2分位アルコール分を飛ばし、アルコールの匂いが無くなり、磯の香に変わったらOK!で火を止める。
③②に醤油を入れ混ぜたら完成です。

【しらす丼】 2人分
・熱々のごはん 2杯分
・釜揚げしらす 約100g
・かつお節 ひとにぎり
・炒りゴマ 大さじ1~
・青ネギ(小口切り) 3~4本
・大葉(千切り) お好みで2~3枚
・もみ海苔 適量
・温泉卵 各1個
・ごま油 各大さじ1
①釜揚げしらすにかつお節と炒りゴマを混ぜる。
②熱々のごはんを器に盛り、青ネギや大葉を周りに散らして①を適量のせ、中央に温泉卵やもみ海苔をトッピングし、ごま油を回しかけておく。
③食べる直前に『特製だれ』のお好みの量をかけて、いただきます。
レモンの効果
レモンの生産日本一を誇る広島県!
スーパーにはレモン味のお菓子や瀬戸内レモンを使った調味料、いろんな種類のレモンサワーのお酒などが、ずらりと並んでいます。最近、レモンは大ブームなんだとか!
レモンと言えば、果汁を搾って、唐揚げや魚、野菜にかけたり、紅茶に入れたり、添え物だったりとメインになるような感じではありませんが、意外なレモンの効果があるのです。
<レモンの効果>
①骨を丈夫にする。~レモンのクエン酸がカルシウムの体内への吸収率をアップします。
②血圧を下げる。~酸味は塩味を引き立てる効果があるため、減塩につながります。
③疲労回復を助ける。~ビタミンCが疲労状態での風邪予防としても有効です。
どの効果も、お子様にとって気になるものですが、「“カルシウム”の体内吸収率が高くなる」というのはポイントです。
‘キレート効果’と言われるものらしいのですが、レモンに含まれるクエン酸と一緒に摂取することで、“カルシウム”の体内吸収率が高まって骨密度もアップするというものです。
育ち盛りのお子様に必要な栄養素のひとつに挙げられる“カルシウム”。子どもたちに“カルシウム”が必要な理由は、子どもはカラダが小さくても成長するために、たくさんの“カルシウム”が必要になるからです。(一例では、3~5歳の子どもが1日に摂取した方がよいカルシウム量の目安は、30代女性の摂取基準とほぼ同じなのだそうです。)また、そんな“カルシウム”は身長を伸ばし、カラダを作ることだけに必要な栄養素ではありません。
受験生のお子様にとってはさらに気になる【脳を強化し、集中力を向上する】栄養素でもあるのです。脳細胞の興奮を鎮めて、動揺やイライラすることを治め、速やかに正常な落ち着きを取り戻す状態が保てるのです。
“カルシウム”が取れる食材と言えば、乳製品や小魚、大豆やひじき、小松菜、ほうれん草、胡麻などがありますが、それだけを食するだけではなく、+レモンを摂取することで、“カルシウム”の体内吸収率がアップするって、凄くないですか!
新年度4月を迎えて、何だか疲れやすい私自身の、ちょっとしたマイブームになっている【レモンラッシー】!~ご存じですか。
先日、NHKの『ガッテン!』で紹介されていた【レモンラッシー】なのですが、“カルシウム”と言えば「牛乳」に、+レモンを搾り、シェイクしていただきます。
「牛乳」だけを飲むよりもサッパリしているので飲みやすいのですよ~♪
あっさりとした飲むヨーグルト!といった感じでしょうか。“カルシウム”が体内に溢れて、元気になっていくみたいです。(笑)
まさに‘キレート効果’です。

【レモンラッシー】 1人分
・牛乳 200cc
・レモン果汁 大さじ2
・はちみつ 大さじ1.5
①清潔な蓋付きビンや容器、ペットボトルに材料をすべて入れて、しっかりと蓋を閉めた状態で上下に振って、シェイク!シェイク!
②全体によく混ざれば完成です。
★お子様とご一緒に楽しく作って、美味しく召し上がってみてください~♪
レモンの効果を最大限に取り込んでみませんか。
ストレス・デトックス!春野菜
春キャベツに新玉ねぎ、筍、ふき、アスパラ、菜の花、そら豆にえんどう豆、ニラや三つ葉等々、今が旬の『春野菜』がスーパーには溢れています。今が旬の『春野菜』は、前年の寒い時期(晩秋から冬)に種まきをしたり、苗を植え付けた野菜たち。寒い冬の時期に地中に根を張り、我慢してじっと暖かくなるのを待っていたのです。春が来て気温が上がってくることでムクムクと大きくなってきた野菜たちなので、柔らかくて甘味もあり、みずみずしいのだそうですよ。だけど、強い香りや独特な苦味を持つものも多いのが、『春野菜』の特徴のひとつです。この香りや苦味の成分には、あらゆる病気の原因やカラダを老化させる原因にもなる活性酸素を除去する抗酸化力がたくさんあるようです。
特に香りと言えば、「三つ葉」ですが、春のストレス解消に効果あり!なのだそうです。
その香りの成分が、健康面でも効果的な役割を果たしていると言われていて、食欲増進や消化促進の働きがあり、ストレスやイライラなどを鎮め、不眠症にも効果があると言われています。新生活などで、メンタルの乱れやストレスを感じやすいこの時期は、特に積極的に食べたい食材のひとつです。
「薬膳」の考え方では、春は植物や食物同様に人間のカラダも目覚める季節で、冬の間に落ち込んだ新陳代謝のせいで、結果的に溜め込んだ脂肪や毒素、老廃物などを解毒・浄化するデトックス効果を発揮するのが『春野菜』ということです。
4月になり、お勉強等に頑張っているお子様にとって(いえ、大人にとっても)、ストレスは切実です。疲労感も相当なものだと思いますので、『春野菜』をふんだんに使った簡単レシピで、食卓を彩ってみませんか!
ということで、一品目は、お子様にも食べやすいクリーミーなパスタレシピです。
筍etc.の『春野菜』のえぐみは、牛乳や生クリーム、さらにチーズのような乳製品との相性が抜群なんですよ~♪牛乳や乳製品のコクと旨味のおかげで、筍etc.の『春野菜』がまろやかでミルキーな味わいに仕上がります。乳製品の風味が加わることで、『春野菜』の特有のえぐみも気になりません。

【春野菜たっぷり★クリーミーパスタ】 2人分
・牛乳 1と1/2カップ
・小麦粉 小さじ2
・コンソメ(顆粒) 小さじ2
・粉チーズ 大さじ2
・バター 10g
・塩こしょう 適量
<春野菜>
・筍、新玉ねぎ 各1/2個(約100g)
・そら豆 3~5房(房から取り出し、下茹で後皮をむく)
・グリーンアスパラ 4本(はかまをとり、食べやすい長さにカット)
・菜の花 Ⅰ/2束
・春キャベツ 2枚(一口大にカット)
・ベーコン 2枚(細切り)
・パスタ:~フェットチーネ 150g (クリームが絡みやすいように平麺にしました!)
①筍は、ヌカで下茹でした状態から、穂先は薄切りに、根本は繊維に沿って短冊切りにする。そら豆も下茹でして、準備をしておく。他の春野菜はカットのみ、パスタと一緒に茹でていきます。
②鍋に熱湯を沸かして、パスタを茹でていく。パッケージの茹で時間の2~3分前から、アスパラ・菜の花・キャベツを入れて茹で上げます。
③フライパンにバターとベーコン、玉ねぎ、筍を入れて炒め、小麦粉を入れて炒め絡めていく。そこに牛乳を2~3回に分けいれて、ダマをのばしながら、コンソメと粉チーズも入れていく。そら豆も入れて、ごく弱火でトロミが付くまで煮たら、火を止める。
④塩こしょうで調味して、②が茹で上がったら水気を切って加え、サッと絡めたらすぐにお皿に盛り付けて完成です。
★春野菜は、なんでもOK!野菜の固さによって、下茹でするかを考えます。
基本はパスタと一緒に茹でていきますが、お鍋に入れるタイミングは調整してください。
二品目は、簡単にできる「三つ葉」を使ったサラダです。「三つ葉」は汁物やごはん等の添え物として使うだけではないんです。生食することで、そのままのたっぷりの栄養価が取り込めます。

【三つ葉のサラダ】
・三つ葉 1パック
・ツナ缶 1缶
・生姜のすりおろし 小さじ2~
・焼海苔 2枚(あぶっておく)
●マヨネーズ 大さじ2
●醤油、すりごま 各小さじ1
①三つ葉は洗い、3㎝幅位にカットし、水気をしっかり切る。
②ボウルにツナ缶とすりおろし生姜を和え、①を入れて、小さくちぎった海苔とあらかじめ混ぜ合わせておいた●を入れて、サックリと混ぜ合わせたらできあがり!
*「三つ葉」の葉の緑の濃い部分は、ビタミンCやβカロテン、カリウム、カルシウムなどが豊富で、旬の時期にはより含まれる栄養価が高くなるので、旬に食するのはオススメの野菜ですから、サラダで大量消費はいかがでしょうか~♪
“塾デリカ”のヒミツ!
新年度“塾デリカ”がスタートしました!
“塾デリカ”とは、「学びにも体にもよいお食事をお届けすること」をコンセプトに、『一汁三菜』を基本とした、成長期のお子様に必要な栄養素や学びに必要なビタミンなどの栄養を含む10~15品目の食材を使ったバランスの良い食事&温かいお味噌汁付きでお届けする‘お弁当’です。安心・安全な食材はもちろん、無添加に近い天然素材の調味料にこだわった、カラダにやさしくて頭にも良いものを提供し続けているのが “塾デリカ”なのです。
『一汁』は、こだわりのある出汁(アゴだしや昆布だし等)から作られている‘だしの素’を使い、甘味のでる野菜を煮込んで作るカラダの芯からホッ!とできる一品として提供している人気の味噌汁です。人気のヒミツは、味噌に国内産の大麦こうじと有機大豆から作られている‘麦味噌’を使っているこだわりの「田舎味噌」を使用していることでしょうか。
『三菜』は、毎回10~15品目の食材を使用した‘メイン&副菜’で構成されていて、体力&脳力、精神面にも強化できることを目指した、塾ならではのこだわりのあるものに仕上がっています。そして、いろいろな野菜を召し上がって欲しいので、野菜が豊富に使われていることは“塾デリカ”ならではの自慢のひとつにもなっています。
1日のメニューコースは、魚や肉がバランス良く組み込まれている『一汁三菜』を基本とした【応援デリカ】、そして、栄養バランスが瞬時に摂り込めて、ガッツリ!と食べていただけるように考えられた丼ものを基本とした【のっけデリカ】となっています。★どちらもお味噌汁付きですよ~♪


それと、単品シリーズとして、今年度から導入されるワンハンドで食べられるように‘国産鶏肉’を米油で揚げた【オリジナル唐揚げ棒】と、【プチ贅沢果物】がお目見えします。【プチ贅沢果物】は‘旬のフルーツ’基本となりますから、プラスαすることで、免疫力を強化することもできて風邪予防や疲労回復には欠かせない1品ですね~♪
そして、毎月19日は、語呂合わせで‘塾の日’!
それにちなんで、白石学習院専属食育インストラクターの私から受験生の皆さんに向けてのエール(!?)として、スペシャルメニューを提供させていただいています。脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けてのゲン担ぎの縁起物など、大神家の子どもたちが喜んで食べたものなどがメインになっているスペシャルメニューです。お楽しみに~♡
“塾デリカ”の中でも、手軽に食べられて、なおかつ栄養がしっかりと摂れる【のっけデリカ】の中で、いつも人気があり、リクエストの多いのが【ロコモコ丼】です。
カフェランチでも、よく見かける【ロコモコ丼】!
ハワイのファストフードが発祥と言われる【ロコモコ】は、ハンバーグと目玉焼きをごはんの上にのせて、グレービーソース(=調理される肉から出る肉汁を素に作られるソース)をかけたワンプレートごはんです。
ガッツリ系の男子にも、おしゃれ女子にも人気のカフェ風丼となっている【ロコモコ丼】です。
そこで、いつも【ロコモコ丼】を作ってくださっているハーストーリィハウス・デリキッチンさんに、【ロコモコ丼】でもお味の要となるソースのレシピを教えていただきました!
ハンバーグがあれば、すぐにできる【ロコモコ丼】です。
【のっけデリカ】の【ロコモコ丼】のポイントは、手作りハンバーグの中に隠れた栄養をたっぷりと混ぜ込んでいること!ミンチ肉だけでなく、野菜のみじん切りがかくれんぼしています。おまけに、つなぎとして豆乳がたっぷりと使われているので、とってもふんわり柔らかなハンバーグになっているんですよ。
ご家庭では、ハンバーグはお家の味と愛情たっぷりのレシピでどうぞ~♪
少し多めに作っておいて、残りを冷凍しておいてもOKですね。
そして、ソースはハーストーリィハウス・デリキッチンさんにお教えていただいたレシピで、ぜひ愛情たっぷりの【ロコモコ丼】に仕上げてみてください!

【ロコモコソース】 2人分
・ハンバーグ 2個
(合挽ミンチ 200g、人参、グリーンアスパラ、玉ねぎ適量)
- ケチャップ 20cc
- お好みソース 20cc
- 豆乳 20cc
- 赤ワイン 10cc
- 鶏ガラスープの素 小さじ1/3
- 醤油 小さじ1/2
- 砂糖 小さじ1/2
・マヨネーズ 大さじ1~
①手作りのハンバーグを焼き、●を合わせてソースを作っておく。
②焼けたハンバーグを取り出し、余分な油を拭き取ったところに●を入れてグレービーソースにし、ハンバーグを戻し入れて煮込みハンバーグにする。(器に、ごはんを入れてベビーリーフやグリーンアスパラ、トマト等の野菜をのせ、②のハンバーグと目玉焼きをトッピング!)
③残ったロコモコソースにマヨネーズを適量、混ぜ合わせてオーロラソースにし、回しかけたら、できあがりです。
★二種のソースが美味しいですよ!
2021年★パワーフード
三月になりました。2021年度、新年度がはじまります!
コロナウイルスに翻弄された昨年から少しでもより良くなりたくて(!?)、昨今ブームになっている占いを調べていたら、今年の開運パワーが強い食べ物=【パワーフード】に出会いました。
2021年の開運パワーが強い食べ物は、嘘か誠か(!?)、【魚】なんですって!(←風水占いより)。ラッキーフードの【魚】は、マグロやカツオなどの赤身の魚はもちろん、鯛やヒラメ、かれいなどの白身の魚でもOK!で、美味しくいただくことが大切なのだとか。
偶然にも、“受験生のパワーフード”のひとつは、学びにも良い栄養素で脳の働きを活発にすると言われるDHAを多く含む【魚】です。
DHAとは、正式名称は「ドコサヘキサエン酸」。
青魚などの脂肪に多く含まれている不飽和脂肪酸の一種で、脳の記憶学習中枢を構成する物質のひとつです。脳細胞の働きを活発にし、記憶力を高めると言われているため、【魚】は脳に良い食材で、頭が良くなると言われる所以です。ただし、DHAは脳や神経組織の発育に重要な役割を果たす大切な栄養素なのですが、カラダの中で作り出すことができません。そのため【魚】からの摂取を心掛けることが大切となるため、“受験生のパワーフード”のひとつだといつもお話をさせていただいています。
DHAが多く含まれている食材は、マグロ、鰹、ぶり、イワシ、さばなどの魚類です。
“信ずる者は救われる”ではありませんが、美味しい【魚】をたくさん食べて、2021年を美味しく運気アップと行きませんか~♪

【鰹のたたき】
鰹のたたきを買ってきて、玉ねぎスライスと、たっぷりの小口切りの青ネギとポン酢で食べる!
“大神さん家の鰹のたたき”です。
今が旬の‘春鰹’!【鉄分】がたっぷり摂れるのも魅力のひとつですから、毎日の食事で細目に摂取するというのが意外と大事なんですって。
【魚】は、お刺身やたたきなどで超シンプルにいただくのが何よりも美味しいのですがワンパターンになりがちですよね。そこで、お刺身用のマグロを使った<マグロのガーリックステーキ>はいかがでしょうか。

<マグロのガーリックステーキ> 2人分
・お刺身用マグロ 約200g ~切り身でOK!です。
・ニンニク 1片(スライスして中の芯を取っておく)
・オリーブ油 大さじ1
*醤油 大さじ2
*酒 大さじ2
*粒マスタード 大さじ1
*すりゴマ 大さじ1/2
①フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火でニンニクが色付くまで炒めて、一旦容器に油ごと全部取り出す。(ガーリック油)
②フライパンは洗わずにそのまま強火で加熱し、マグロを入れて片面づつ焼き色が付く程度(各1分位)に焼く。焼けたらマグロを取り出して(柵の場合は2㎝幅くらいにカットして)お皿に盛り付ける。
③マグロを取り出したフライパンに*の調味料と①で取り出したガーリック油を入れて加熱し、温まったら盛り付けたマグロにかけてできあがり!~青ネギをトッピングしても美味しいですよ!
★シンプルなマグロのお刺身がちょっぴりボリューミーになるレシピです。ゴマ(ソースの中に入っています)と一緒に食べ合わせると、これまた【鉄分】がアップするそうですから、お試しあれ~。
もっと身近に【お赤飯】!
何かとお祝い事の多いこの時期です。まだまだ寒い時期ですが、気分は春めいて~♪
そんな明るい気分の時のごはんや、お祝い飯のシンボルといえば【お赤飯】。
【お赤飯】は、もち米にあらかじめ煮た小豆=ささげを混ぜて蒸し、途中で煮汁を混ぜ込んで赤く染めた赤いご飯です。
ビタミンやミネラルなどの栄養をバランス良く含むので栄養的にも良く、最強なごはんとでも申しましょうか、“強飯”(こわめし)=「おこわ」とも呼ばれます。
【お赤飯】がおめでたいと思われる秘密は「赤色」にあるようで、古来より「赤」は邪気を払い、厄を除けるパワーがあるとされていたため、祝い事や特別の行事に用いられるようになったそうです。また、【お赤飯】に小豆を用いるのは、小豆に薬効があるからとのこと。
ちなみに、小豆には良質のタンパク質はもちろん、豊富なビタミン類(B1,B2)やカリウム、リン、鉄、食物繊維等幅広く含まれているようです。
これを、日本の主食のお米と食べ合わせることで、さらに最強パワーを発揮するのが【お赤飯】です。
【お赤飯】は、糖質の代謝を助けてエネルギーを作り出し疲労回復に役立つビタミンB1や、細胞の新陳代謝を促進し、皮膚や粘膜の機能維持や成長に役立つビタミンB2、また脳神経を正常に働かせるのに役立つと言われているナイアシンやビタミンB6、またストレスを和らげる働きのあると言われるパントテン酸や、貧血を予防し、細胞の生まれ変わりに欠かせない葉酸を含んでおり、抗酸化作用、動脈硬化や血管の老化を防ぎ、免疫力を高めてくれるようです。また、骨や歯を構成するのに必要なミネラルであるカルシウムやリン、マグネシウムを含み、カリウムも多く含みますのでさらに疲労回復、高血圧の予防に役立つということですよ。
どうですか~(!?)まさに、最強パワーのごはん=“強飯”な【お赤飯】ですね!
お祝い事だけでなくても、普段からもっと積極的に食べたい、食べて健康や免疫力UPを図りたい【お赤飯】。~これは、受験生のための“元気パワー飯”にエントリーですね!
そこで、普段日常でもいただけるように、簡単に、炊飯器でも作れる【お赤飯】レシピを紹介してみます。基本はもち米で作りますが、普段にいただくご飯ということで、お米だけで作ります。もち米をお米に変えるだけですが~~笑!

【炊飯器で☆お赤飯】
・米 3合 ~しっかり洗米してザルにあげておきます。
・小豆 1/2カップ(約80g)
・水(小豆用) 800cc
・塩 小さじ1/2
・ごま塩 適量
<小豆の下処理>
①小豆を洗い、鍋にかぶるくらいの水と一緒に入れて火にかける。(水につけずにすぐ茹でます!)
②沸騰してから2~3分煮て、一旦ザルにあげる。(茹で汁は捨てます。)
③再度、鍋に水800ccと②を入れて火にかけ、煮立ったら弱火にし、蓋をして30分程度煮る。~指でギュッとつまむとつぶれる程度まで煮る。
④茹で上がった小豆は、小豆と茹で汁に分ける。
*小豆は乾燥防止のためラップをしておく。
*茹で汁は空気に触れさせて酸化させ、赤色を鮮やかにします!~そのため、数回お玉ですくっては、上部から落として空気に触れさせます。(冷めるのも早いですね)
⑤ここからは、<赤飯の炊き上げ>です!
茹で汁が冷めたら、炊飯器に洗米をした米を入れ、茹で汁を炊飯器の‘おこわ’の目盛まで入れて、塩を加えてかき混ぜたら、小豆を上に散らして、スイッチON!
⑦炊き上がったら、ご飯をほぐし混ぜ合わせて、器に盛り、ごま塩をふったらできあがり!
★小豆の下処理が面倒だと思われる方に、小豆を下茹でしない方法です。
⇒小豆を洗って、2カップの水で24時間漬けておくだけ!です。
普段から【お赤飯】を楽しむために(!?)、もっと簡単に、お米と混ぜて炊飯器で炊くだけの【お赤飯の素】を使うのもありだと思います。白米でもモッチリ食感でいただけますし、炊き込みご飯の感覚でいただくのもよいのではないでしょうか。
なんてったって、受験生のための“元気パワー飯”ですから~♪
カラダを温める朝食!【スープごはん】
「寒い~っっ!」、そんな毎日が続いています。
まだまだ気の抜けないコロナウイルスの猛威で、本当に大変な昨今ですが、“寒い、寒い”も我慢してしまうと免疫が下がってしまい、体調を崩してしまう恐れがあり~~大変です。
そこで、意識したいのが<何を食べるか>!です。
冬はカラダの活動力が落ち、冷えからくる様々なカラダや心の不調を招きやすくなると考えられているため、それを補うために冬の食事で積極的に取り入れたいのが“カラダを温める”食事です。
そこで、要注目なのが、寒い季節ならではの栄養満点で、“カラダを温める”作用のある【冬野菜】。【冬野菜】を食べて、カラダの内から温められると良いですよね~♪
【冬野菜】の中でも、
「温」の野菜=かぼちゃ、白菜、かぶ、小松菜、ニラ、ねぎ、etc.
「熱」の野菜=ニンニク、生姜、唐辛子、etc.
特に、上手に使いたいのが、温める作用の強いニンニクや生姜などの「熱」の食材。調理に少し加えるだけで、美味しいだけでなく、カラダが温まる効果も高まります。
そして、【冬野菜】を使うだけでなく、寒~い朝からポカポカ&ほっこりする朝食を食べることはポイントになりそうですよ!
そこで【スープごはん】はいかがでしょうか。名前のとおりスープとごはんが一緒になった【スープごはん】。作るのも簡単だし、食べるのもラク~♪お母様にとっても洗い物が少なくて済むという忙しい朝の朝ごはんには持って来い!ですよ。
今回は、朝からビタミン、カルシウムがたっぷり!だけど、とっても簡単なカップスープの素を使った簡単リゾット【コーン&チーズの和風リゾット】と、鮭フレークを使ったスープをご飯にかけて、サラッと食べられる【鮭&卵のスープごはん】を紹介してみます。どちらもスピードメニューです!

【コーン&チーズの和風リゾット】 1~2人分
・ごはん 茶碗軽く2杯分
・水 400cc (2カップ)
・コーンスープの素 1袋
・鶏ガラスープの素 小さじ1
・ブロッコリーや小松菜、白菜etc. 適量
(冷蔵庫にあるもので)~今回はブロッコリーを使用
・粒コーン(缶詰) 大さじ2~3
・醤油 小さじ1/2
・塩こしょう 少々
・スライスチーズ 2枚
・桜えび 大さじ1~2
①鍋に水と鶏ガラスープを入れ、煮立ったところに小房に分けたブロッコリーと粒コーンを入れて、火が入ったらコーンスープの素を入れてしっかり溶かす。
②味を見て、醤油と塩こしょうで調味する。
③②にごはんを入れ、ひと煮立ちしたところに桜えびとチーズを入れたらできあがり!

【鮭&卵のスープごはん】 1~2人分
・ごはん 茶碗軽く2杯分
・溶き卵 1個分
・鮭フレーク 大さじ2位
・小松菜&ニラ 1房~
・白ネギ 1/2本~
・白ごま 少々
・おろし生姜 小さじ1/2
<スープ調味料>
- 水 400cc(2カップ)
- 鶏ガラスープの素 小さじ1/2
- 塩 小さじ1/4
①鍋にスープの調味料●をすべて入れて、小松菜、ニラ、白ネギを煮る。(野菜はすべて食べやすい大きさにカットしておきます。)
②①に火が入ったら、鮭フレークと溶き卵を入れて、白ごま&おろし生姜を入れたらスープのできあがり!
③ごはんに②のスープをかけて、お好みで白髪ネギやおろし生姜、海苔etc.をトッピングしたら完成です。
カラダを温めることは、呼吸器系の健康を守る働きや風邪予防、食欲不振や疲労回復にも効果的なのだとか。常日頃からの“カラダを温める”朝食で、もう少しだけ手抜かりなく乗り切っていきましょう!!
咀嚼で脳を活性化
食事をする上で欠かせない「咀嚼」=‘噛むこと’!
食べ物を噛み砕いて小さくし、カラダに食べ物を取り入れるだけでなく、全身の健康に大切な様々な良い効果をもたらします。例えば、胃腸の働きの促進、肥満防止、味覚の発達、虫歯予防や歯並びを良くすることetc.とカラダに嬉しい効果がたくさんあります。
そして、『噛む力の強い子どもは活発で成績が良い傾向にある』(第51回全学校歯科医協議会における調査結果)という発表もされています。
「咀嚼」は子どもの顎の発達や歯並びに大きく影響していることが知られている一方で、「咀嚼力」によって脳が刺激されて記憶力のアップにもつながっていることも昨今多く報告されていることが上記からも伺えます。
それでもまだ、意識的によく噛んで食べるという人は少数なのが現実なのは、「噛む」という行為が呼吸と同じくらい当たり前のことになっているからなのかもしれません。
よく‘噛むこと’の重要な働きは、食べ物を咀嚼してカラダに取り入れるためだけではなく、その他注目したいのは“唾液”の存在です。
“唾液”にはデンプンやたんぱく質を分解する消化酵素が含まれていて、よく‘噛むこと’で“唾液”分泌も活発になるため、食物とよく混ざり、胃や腸での消化を助けます。また、消化液の分泌を促すため胃腸の働きも促進します。そして、口の中を流れている“唾液”には、自浄作用によって虫歯や歯周病を防ぎ、歯を保護する働きもあります。
「咀嚼」と同じように、普段あまり意識しない“唾液”ですが、食べ物とカラダとを密接に結ぶ重要な存在なのです。
おまけに、よく‘噛むこと’で、心理的な満足感も得られ、精神的にも安定するそうですよ。ちょっとイライラする時などは、硬いおせんべいやナッツ類などを食べるのもオススメです~♪
最近の‘軟食’傾向により、さほど噛まなくても食べられるメニューが増えています。
食育の本などを読むと、できるだけ避けた方が良いメニューの代表ということで、『おかあさんやすめ』『ハハキトク』という言葉で表現されているのをご存じですか。(少々ドッキッリ!とする感じですが)
どんなメニューかと言うと、『お:オムライス か:カレーライス あ:アイスクリーム さん:サンドウィッチ や:やきそば す:スパゲッティー め:目玉焼き』『ハ:ハンバーグ ハ:ハムエッグ キ:ギョウザ ト:トースト ク:クリームシチュー』。
子供たちが大好きで、比較的簡単に料理ができるという共通点があるメニューです。
このメニューがすべてダメということではなくて、糖質や脂質を過剰に取り過ぎてしまう点や、子どものみならず私達の噛む回数が確実に減ってしまうメニューだということが問題のようです。その点をどう解決していくかが大切で、再度「咀嚼」の重要性を踏まえて、日々の食事にちょっとした工夫をしてみませんか。
ただ今、受験真っ最中の頑張っているお子様のためにも、腹ごしらえや食事に噛みごたえのある根菜や乾物などの食材をあえて使ってみて、「咀嚼」を促す!レシピで、意識せずとも噛む回数を増やしてみる。
食材選びや料理法の工夫で「咀嚼回数」を自然に増やすことができるのですから、これも隠れた母の愛情かもしれませんね~♪

【根菜ごはん】 2人分
・ごはん 2杯分
・豚ミンチ 80~100g
・切干大根 20g(戻しておく)
・人参 1/3本
・れんこん 小1個
・ごぼう 50g位
・いんげん 30~50g
・炒りごま 大さじ1
・醤油 大さじ1
・砂糖 大さじ1.5
・和風だしの素 小さじ2
・みりん 小さじ2
①人参、れんこん、水戻しした切干大根、いんげんは食べやすい大きさに切り、ごぼうはささがきにする。
②鍋に①を入れ、調味料を入れて、煮付ける。
③水分が無くなるまでにたら、熱々のごはんに混ぜて、炒りゴマも混ぜたらできあがり!
買い置きの乾物食材や根菜の煮物でおかずにもなり、食物繊維も取れて「咀嚼」もいっ
ぱいできます。おにぎりにして小腹を満たすのにもバッチリ!ですよ。
よく「噛むこと」を意識して、味わってみませんか。
【合格ひじき】でエール!
受験にむけて、「お子様が食べやすくカラダにやさしくて、頑張る毎日を応援できる食べ物!」として思いついた【合格ひじき】!
薄味に煮たひじきに、五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせた、各自各々で作る“ひじきのウエットタイプのふりかけ”です。
考案の基となっているのが、今でこそ広島のデパ地下や通販でも購入できるようになった『えとやの<梅の実ひじき>』です。

ご存じですか~(!?)
九州の合格祈願の神様として有名な「太宰府天満宮」に位置するお店の『えとや』のふりかけで、大宰府の名産品であるカリカリ梅の実を使ったあっさりとしたひじきのふりかけです。(熱々のごはんにのせていただくととっても美味しいです~♪)
我が家の子供たちの受験期に「太宰府天満宮」のお守りと一緒に<梅の実ひじき>をいただいたことがきっかけで、受験シーズンには欠かせない縁起物となっていました。
それを簡単に身近に取り入れて、いつも応援すると同時に、お子様に食べてもらえるように、と思いついた【合格ひじき】です。
薄味に煮たひじきに五色になるような食材を取り入れる!
~五色の食材とは「赤・白・黄・緑・黒」色の見た目の判断でOK!のすべての食材が対象で考えます。*五色になるように食材をなんでも取り入れて作ると、不思議とカラダに必要な栄養がほぼバランス良く揃う!という、塾デリカや塾弁作り、また日々の食事作りにも率先して取り入れ、提案をしているひとつの方法です。
五色の食材の栄養素はもちろんですが、五色の色のパワーもじつは侮れないんですよ!
*赤色の効用として、活力を与えてバイタリティーを高めます。血となり肉となる食材が豊富です。
*白色の効用として、心を落ち着かせます。“カラダの素となる”エネルギーを作り出す食材が豊富です。~ごはんのイメージです!
*黄色の効用として、脳を刺激して希望につなげるパワーになります。頭&カラダを働かせる原動力となります。
*緑色の効用として、ストレスを和らげてココロの安定効果があります。カラダの調子を整える、野菜や果物に多いイメージです!
*黒色の効用として、安心感や強さ、自信を与えます。カラダ&頭の健康維持に必要な食材が豊富です。
専門的に立証されていることではあるのですが、専門的に考えながら食事を作る毎日も疲
れてしまいますので、ザックリと大まかに捉えての【合格ひじき】です。

【合格ひじき】
・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で100g位
・だし汁 120cc ~ひじきがヒタヒタに浸かる位(水120cc+和風だしの素 小さじ1)
・醤油 大さじ2
・砂糖 大さじ1
・みりん 大さじ3
・昆布茶 小さじ2~3(*ポイント=隠し味になります!)
- トッピングはお好みで
赤:カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老など
白:白ゴマ・タラの身・ちりめん・かつお節・大豆の水煮など
黄:柚子の皮(細く千切りしたもの)・炒り卵など
緑:あおさ海苔・いんげん・枝豆・パセリなど
黒:黒ゴマ・刻みのりなど
①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水で戻します。(約10分~)
約8~9倍に増量します。
②①の水切りをしたひじきを鍋に入れ、だし汁と調味料をすべて混ぜ合わせて煮ます。
③汁気が無くなるまで、時々混ぜながら煮たら【合格ひじき】の素=“ひじき”の完成!
*少し乾煎りするようにしっかりと水分を飛ばしながら煮ることがポイント。
*お好みのトッピングを適量混ぜ合わせたら【合格ひじき】のできあがりです~♪
お母様のエールを送るためにも、我が家の【合格ひじき】を手作りして、卵やお肉と混ぜ
合わせて焼いたり、野菜と炒め合わせたり、ごはんと混ぜたり炒めたりでチャーハンやオムライスにしたり~~と、【合格ひじき】を使ったアレンジで塾前の腹ごしらえや塾弁にも活用してみてください。今回は甘辛に煮付けた“油揚げ”に【合格ひじき】を寿司飯に混ぜ合わせて詰めた【合格いなり】を作りましたよ!

【合格いなり】
・寿司用油揚げ 1パック(5枚位)
- 砂糖 60g
- 酒 60cc
- みりん 60cc
- 醤油 60cc
- 水 60cc
①油揚げを半分にカットして、熱湯にくぐらせて油抜きをしておく。
②鍋に●を合わせてひと煮立ちさせ、しっかり水分を切った①を入れて、落し蓋をして弱火で15分程度煮含める。
③落し蓋を取り、強火で煮汁を煮飛ばしたら、そのまま冷まして完成です。
*お好みの寿司飯に【合格ひじき】を混ぜ合わせて、寿司揚げに詰めたら【合格いなり】のできあがりです!
暖かい【チャウダー】で免疫力アップ!
12月に入り、寒さが増して来ました!朝晩の冷え込みがカラダにしみるこんな季節にぴったりなのが、“スープ”です。中でも【チャウダー】が気になるのは、私だけでしょうか~。
【チャウダー】とはフランス語で、語源は「大鍋、煮込み」と言われています。魚介類や乳製品を使うことが多く、アメリカ東海岸の名物料理である「クラムチャウダー」などがよく知られています。今では、小さめの具材がたっぷりと入り、ややトロミのあるクリームベースやトマトベースのものが多くみられるようになりました。シチューよりは、具が小さくてソースのトロミも少なく、また一般的にはスープと呼ばれるものと比べると、具がたっぷりと入っていて、ソースにトロミがついていることが多いことから、「スープとシチューの中間」くらいに位置付けされた煮込み料理と言えそうです。
食事を作る立場の母からすると、具がたっぷりと入るし、魚介類も簡単に取り込めて、栄養満点の暖かいスープですし、小さめの具材ということで火通りが早く、シチューよりも時短で本格的なスープができあがりますので、大助かりの一品です。
具材は、定番のあさりを使った‘クラムチャウダー’のほか、今が旬の広島の特産である牡蠣も簡単に使えてしまいます。また、さつま芋やジャガイモ、いろいろな種類のきのこや旬の野菜、おまけに、冷蔵庫内に転がっている細々しているものまで使えるのが【チャウダー】の嬉しい点です。寒い時期に、カラダを温めるのは必須!体温が一度下がると、免疫力が一気に下がってしまうと言われていますから、ラストスパート真っ只中のこの時期には、免疫力を下げてしまっては大変です。免疫力をアップすることを考えて、たっぷりのきのこと旬の白菜を使った【白菜&きのこのミルクチャウダー】と、【ツナのクラムチャウダー】【カレー風味のチャウダー】のレシピを紹介してみます。【チャウダー】のレシピパターンさえ、押さえてしまえば何でもOK!ですよ~♪

【白菜&きのこのミルクチャウダー】 2人分
・白菜 2~3枚
・玉ねぎ 1/4個
・しめじ、エリンギ、しいたけ、舞茸etc. 全てで1パック
・ベーコン 2~3枚
・バター 15g(大さじ1位)
・薄力粉 大さじ2
・牛乳 400cc
・顆粒コンソメ 小さじ1
・塩こしょう、粉チーズ 適量(味を見ながら)
①具材は食べやすい大きさに、カットしておく。
②鍋にバターを熱し、ベーコン、玉ねぎを炒める。しんなりしてきたら、薄力粉を振るい入れて、玉ねぎに絡めるように炒める。
③さらに、白菜、きのこ類を炒めたところに、牛乳の半量とコンソメを入れて伸ばすように混ぜ合わせていく。
④牛乳の残りを加えて、煮ていき、塩こしょうで味を調整しながら、粉チーズをふり入れて完成!(粉チーズはお好みですが、コクがでます♪)

【ツナのクラムチャウダー】 2人分
・ツナ缶 1缶(油を切っておく)
・むき海老 3尾位
・玉ねぎ 小1/2個
・ニンニク 1片(みじん切り)
・バター 15g ~大さじ1位
・牛乳 400cc
・白ワイン 大さじ1 ~水で代用OK!
・顆粒コンソメ 小さじ1/2
・塩こしょう 少々
・片栗粉&水 各大さじ1/2
①油を切ったツナをフライパンで乾煎りする。(残った焼き魚があれば、ほぐして使えますよ!)
②海老は細かめにカットし、木べら等であら潰しにする。(ツナの身と食感が合ってくるので食べやすいです。)
③鍋にバターを熱し、みじん切りのニンニクを入れて炒め、角切りにした玉ねぎも炒める。
④しんなりしてきたら、海老を加えて色が変わったら、白ワイン、牛乳の半量を加え、煮立ったらコンソメを加えて混ぜ合わせ、残りの牛乳を入れてひと煮立ちする。
⑤味見をして、塩こしょうで味を整えたら、水溶きの片栗粉でトロミをつけて、できあがりです。

【カレー風味のチャウダー】
*具材は冷蔵庫に眠っていた
・かぶ ・さつまいも ・人参
・玉ねぎ ・しめじ ・ウインナー
を使いました!
①すべてを角切りにし、【ミルクチャウダー】の分量に、カレー粉を大さじ1を追加して、同じ要領で作りました!
★風味が変わって、美味しくいただけますよ。
具材は何でもOK!なのが嬉しい【チャウダー】のポイントです。
笑顔満点の【肉巻きおにぎり】
いよいよ追い込みシーズンのスタート12月です。
今年度は、コロナウイルスで始まって、未だ好転が望めないままの今までとは全く違った様相を呈している受験期です。そんな中での受験に立ち向かって行くお子様にとって、ストレスは半端ないものだと思います。そうなると、しっかり栄養と休息を取らせないと…と思ってしまう親心も大変な葛藤がありますよね!しっかりと食事を取らせるためには、栄養バランス=食事バランスが整った『一汁三菜』(日本型食生活)が大切と言われます。
わかってはいても塾のある日など毎回家での食事は難しくなってくるのがこのシーズンです。すべての時間を惜しんで、勉強に頑張っているお子様たちですから、そんなお子様のためにも簡単に食べられるおにぎりで一工夫してみませんか。
そのおにぎりとは、宮崎のB級グルメでもお馴染みの【肉巻きおにぎり】!
こんがり焼いた豚肉に甘辛いタレが絡んだ、やみつき必須のおにぎりです。
おにぎりのごはんにはいろいろな具材を取り混ぜて、薄切りのお肉で包むので、栄養価のアップは間違いなしです。脳の栄養補給には、お米のブドウ糖が大切ですし、脳のスタミナにはお肉が大切なんですよ!豚肉を使えば、疲労回復効果も望めますから、ワンハンドで簡単に食べられて、お子様に喜んでもらえ、笑顔満点になる【肉巻きおにぎり】は、束の間の癒し気分に浸ってもらえる一品だと思います。
今回はおにぎりの具材として、“ちりめん入りひじき煮”を混ぜました。(前日の“ひじき煮”の残りです。~笑)
長ネギや大葉を刻んだもの+白ごま、カットしたチーズ+刻んだたくあんetc.とても美味しいですよ。うずらの卵をごはんで包んでもテンションUP~♪です。

【肉巻きおにぎり】 4~5個
・ごはん 2杯分
*まぜる具材はお好みで!
*ごはんには塩を少々しておきます。
・牛or豚 薄切り肉 2~3枚使用(1個につき)
・塩こしょう(肉の下味用) 少々
・ごま油 大さじ1程度
★タレ用合わせ調味料 ~合わせておく!
・醤油&酒 大さじ1 ・みりん&醤油&水 大さじ2
①食材を混ぜたごはんでおにぎりを作る。
*固めに握るのが、ポイントです。
②ラップにお肉を広げて下味をし、①をのせて、おにぎりが見えなくなるまで隙間なく
しっかりと肉を巻く。
*その後、ラップを使って、さらにギュッと握っておくのもポイント!です。~崩れずにキレイに仕上がりますよ♪
③ラップを外した肉を巻いたおにぎりに、薄く薄力粉をまぶす。(分量外)
④ごま油をひいた中火のフライパンで、肉の巻き終わりを下にして焼き目がこんがり付くまで動かさずに焼いていく。焼き目が付いたら次の面次の面と転がしながら焼いていく。
⑤肉に火が通ったらタレを加えて煮絡め、味をしみこませてできあがり!
*ポイントは長く焼きすぎないこと!全体に照りが出たら完成です。
★お好みで、白ごまを散らしてもOK!です。

【うずら卵+肉巻きおにぎり棒】 4本分
・ごはん 2杯分
・青ネギ、白ごま 適量
・うずら卵(水煮) 12個位
・豚バラ肉 200g~1本に付き3枚位
・塩こしょう 少々
・ごま油 大さじ2
★タレ用合わせ調味料は上記レシピと同じです。
①ごはんに青ネギ+白ネギを混ぜ合わせておく。
②竹串にうずらの卵を3個刺しておく。
③ラップに①のごはんの1/4をのせて、うずらの卵が包める大きさに四角く広げる。
その上に②をのせて、ラップをそのまま使って巻き込む。
④別のラップに、豚肉を広げて、塩こしょうをした後、③のラップを外したごはんをのせて、しっかりと包み込む。*しっかり包み込むのがポイントです!
⑤フライパンで焼いていくのは、上記レシピの④~と同じです。
タレを市販の焼肉のタレや生姜焼きのタレ、めんつゆを使っても、時短になって助かります。しっかりしたお味&冷めても美味しいおにぎりなので、お弁当にもバッチリですよ。
“秋鮭”で秋の美味しさ&栄養の再発見!
今が旬の“秋鮭”!
お弁当やおにぎりに定番の塩鮭や生鮭ならムニエルやフライ、鍋物etc.と食卓には欠かせない魚の代表選手です。身は鮮やかなサーモンピンクをしているので、赤身の魚と思われがちですが、実は“鮭”は白身魚!(~豆知識でした。)
体づくりや脳の活性化、抗酸化作用と、頭にもカラダにも関わる良い栄養素がいっぱいの“鮭”は、受験生のお子様だけでなく、大人も積極的に食べたい食材のひとつです。
殊に“秋鮭”は、産卵前のために身が引き締まり、脂分が控えめです。卵や白子を成長させるために栄養価はひとしおで、身自体があっさりしているので、バターを使った料理やムニエル、フライといった料理に向いていると言われています。日頃の食事やお弁当でも使い易い“鮭”ですから、そんな“鮭”を使って、受験に向けての大切なこれからの時期に、母の愛情をたっぷりと注ぎ込んでみませんか~♪
まずは、美味しさとともに、見逃せないのが“鮭”の成分!
1体をつくるたんぱく質が豊富!
2カルシウムの吸収を助ける。
3脳を活性化するDHAもたっぷり!
4ビタミンEより、すごい抗酸化力。
5EPAで血液サラサラに!
6肉に比べて低カロリー。
また、最近よく耳にする「オメガ3脂肪酸」。~これは青魚に豊富に備わっているものだそうですよ。「オメガ3脂肪酸」は、脳により多くの酸素を供給する働きがあって、その結果、以前に覚えたことを脳に留めたまま、さらに新しい情報を覚える力がふんだんに発揮されるのだそうです。
中でも、脳に良いとされる魚は、「鮭・マグロ・ニシン」!
私は常々「“鮭”は受験生の強~い味方!」ということをお話するのですが、それにはしっかり理由があったことをわかっていただけたでしょうか。(笑)
秋深くなってくると、ほっこりできる熱々の‘炊き込みご飯’が妙~に食べたくなりませんか(私だけ!?)栄養たっぷりの‘炊き込みご飯’に、+たっぷり具が入ったお汁で、なんだか安心できる食卓が出来上がるので、私は大好きなメニューのひとつです。
そんな‘炊き込みご飯’に、旬の“鮭”ときのこを入れた【鮭ときのこの炊き込みご飯】はいかがでしょうか。バター醤油の味で、食欲がUPしますよ~♪

【鮭ときのこの炊き込みご飯】 2~3人分
・米 2合
・鮭 大きめ1切れ
・しめじ、えのき等 1/2株位
- 醤油 大さじ1
- 酒 大さじ1
- 和風だし 小さじ1
・バター 10g
・塩 少々
・ゴマ、生姜、青ネギ 適量
①お米を研ぎ、炊飯器に入れて、●を入れ、水を2合の線まで入れて混ぜる。
②しめじ等、鮭、バターをのせたら、スイッチON!
~鮭の臭みが気になるようなら、料理酒を振ってしばらく置き、ペーパーで拭いた物を入れてみてください!
③炊けたら、鮭の骨と皮を取り除き、塩で味を整えたら、お茶碗に盛り、胡麻や千切りの生姜、青ネギ等でトッピングして完成。
*炊き上がり後、分量外のバターを少し入れると、風味が増しますよ!
そして、もうひとつ!“鮭”の‘付け焼き’【幽庵焼き】のレシピです。
和食のワザに【幽庵焼き】という焼き方があり、高級料亭風のようですが、実は至って簡単で、漬け込んで焼くだけの、下準備さえ済ませておけば、忙しい朝のお弁当作りでもOK!のレシピなので、ご紹介します。

【鮭の付け焼き★幽庵焼き】 2人分
・鮭の切り身 2~3切れ (生鮭・甘塩OK!)
・下処理の塩 少々
- 醤油:酒:みりん 1:1:1
*切り身2~3切れならば、大さじ1~2でOKです。
①切り身に塩をして、30分程度置き、その間に●の
調味料を合わせておく。
②①の切り身の水分、脂分をしっかりと拭き取る。
(~このひと手間で味のしみ込みが良くなりますよ。)
③●に、30分~1時間ほど漬け込んだ後、汁気を取ってからグリルやフライパンを使って焼いていく。~この時、漬け込みタレを捨てずに大さじ2~3位、取っておきます!
*8~9割焼いたら、仕上げの段階で、取っておいたタレをハケで(無ければスプーン等で)塗って、乾いたらまた塗って…という作業を4~5回繰り返す。
*焦げやすいので、弱~中火で少なくとも2~3回はトライしてみてください!
味ともに美味しく仕上がってくれますよ♪
風邪予防にピッタリ!の柿~♪
寒い日が増えてきていますが、日中との寒暖の差も大きくて、かえってそれが空気の乾燥による咳やノドからの風邪引きさんが増えているひとつの要因のようです。これから入試本番を迎えるとっても大切なこの時期に、カラダに優しくて、そして風邪対策にオススメのレシピを見つけました。
それは、今まさに旬を迎えている柿を使ったレシピです。

柿はビタミンCやβカロテンを豊富に含み、粘膜を強くして、免疫力を高めてくれるので、風邪予防にもピッタリの食材なんですって~♪
旬の柿は、薬膳的にも肺(呼吸器系)を潤し、乾燥による咳やノドの乾き、鼻の粘膜の乾きを癒やす効果が期待できるようです。
柿は、‘シャリシャリ食感’と‘やわらか食感’の両方が楽しめる果物ですが、みなさんはどちらがお好みですか。
硬めの柿の皮をむいて食べるのもよし、柔らかめの柿を食べるのも美味しいのですが、風邪予防にピッタリな食材の柿とは言え、カラダを冷やす作用もあるので、風邪予防のために食べるには、カラダを温める作用のある食材(生姜&シナモンetc.)と組み合わせて、加熱調理(温める)をすることがBest!なんですって。柿は温めることで、ビタミンCのさらなる宝庫となるそうですよ。
柿を温める~(!?)ということで、簡単にレンジでできて、オススメのレシピ【柿のコンポート】をご紹介してみます。温かいうちに食べれば、カラダがホカホカしてきて、ノドの潤いを感じていただけます。また、冷たいままでもデザート感覚で柿1個をペロリと食べてしまう感覚で、美味しく召し上がっていただけるはずです!

【柿のコンポート】
・柿 1個
・生姜スライス 1片
・千切り生姜 1片
- 砂糖 大さじ1
- ハチミツ 大さじ2
- レモン汁 大さじ1
- 水 大さじ2
(●あれば、白ワイン大さじ1~本格的なお味に!煮るのでアルコール分はなくなります)
①深めの耐熱容器に●をすべて入れて、混ぜておく。
②皮をむいた柿とスライスした生姜を入れ、ラップをしてレンジ600w約3分加熱をする。
*水分が上がってくるので、絶対深めの容器がいいですよ!
③粗熱が取れたら、お皿に盛り、千切り生姜をトッピング~♪そのまま冷蔵庫に入れて、一晩置いても美味しいです。
風邪予防に優れた柿を、加熱調理&温め食材をプラスして、風邪予防対策に活用してみませんか!
旬のきのこの山は、栄養の山(!?)
やって来ました“食欲の秋”!
山の幸や海の幸、野菜に果物と…美味しそうな物ばかりの中でも、実りの季節を代表する食材と言えば、今が旬の『きのこ』です。

「きのこの山」になるほどのいろいろな種類があり、ほとんどの種類が秋に旬を迎える『きのこ』は、美味しいだけでなく低カロリーで、それなのに栄養満点です。ビタミンB1,B2,B3,D等のビタミン類のみならず、食物繊維やミネラルの栄養分がたっぷりと含まれていて、免疫力を高めるべく、腸の力をアップする効果もすごいのですよ~♪
さらに、受験生の皆さんにはとても朗報なのが、『きのこ』に含まれるビタミンB群が複合的に‘脳を活性化’するということ。
この『きのこ』に含まれるビタミンB群は、栄養素の代謝に働きかけるだけではなく、神経伝達や神経細胞を正常に保つ働きがあるため、脳には不可欠な成分と言われています。
たとえば、ビタミンB1には、脳の唯一のエネルギー源である“糖”を代謝し、脳にエネルギーを供給する働きがあるため、不足すると集中力の低下やイライラ等が引き起こされます。また、「ナイアシン」と呼ばれるビタミンB3の十分な摂取は、うつ病や統合失調症を改善に導くという効果もあるようで、「ナイアシン」の不足を防ぐことで“幸せホルモン”であるセロトニンを増やす働きもあるため、精神的に安定し集中力や持続力の向上にもつながります。この他にも『きのこ』には様々なビタミンB群が含まれるため、複合的に脳の活性化を促すという訳なのです。おまけに、リラックス作用のあるGABA効果のあるアミノ酸も豊富なため、リラックス効果が発揮されることで集中力がさらにアップすることは間違いなし!
‘食欲の秋’こそ、受験生の皆さんには栄養バランスのよい食事を取ってほしいのはもちろんですが、秋の食材の代表格でもある『きのこ』を食べて、“旬の食材のパワー”=“脳の活性化パワー”をふんだんに取り込んでほしいのです。
そこで、今回ご紹介するレシピは、【きのこのポークソテー】です。たっぷりの「きのこの山」を使った【きのこソース】で召し上がれ~♪

【きのこのポークソテー】 2人分
<きのこソース>
・生しいたけ 120g
・マッシュルーム(ブラウン・白) 各100g
・しめじ、エリンギ 各50g
・玉ねぎ 1/2個
・オリーブ油 大さじ1
・バター 20g
・にんにく(みじん切り) 小さじ2
- しょうゆ 大さじ1/2
- 砂糖(ハチミツでもOK)小さじ1
- 塩こしょう~お好みで 少々
- ドライタイム 少々
<ポークソテー> ・豚ロース肉(トンカツ用) 2枚 ~筋切りします。
・塩こしょう 少々 ~肉の両面にします。
・サラダ油 大さじ1
・レモン 1/2個分
①<きのこソース>を作ります。きのこはすべて粗いみじん切りにする。
②フライパンにオリーブ油とバター、にんにくのみじん切りを入れて、香りが出るまで炒める。
③②に玉ねぎを入れて、しんなりしたら、きのこのみじん切りをすべて入れて、水分をとばす様に中火~弱火で10分位炒める。
*あまり触らないようにして焦がさないように、じっくり炒めます!
④③に●の調味料を入れて、炒めたら完成です。
⑤<ポークソテー>フライパンにサラダ油を入れ、中火でお肉を焼きます。
⑥焼き色を見ながら、両面カリッと焼いたら、<きのこソース>をかけてできあがり!
<きのこソース>は万能で、きのこソースとミンチを炒めて、牛乳適量で伸ばし、茹でたパスタとあえたら【きのこソースのクリームパスタ】のできあがりです!

トッピングにパルメザンチーズをふりかけて、召し上がれ!~美味しいですよ♪
【お月見つくね】でパワーアップ(!?)
ここ最近、朝夕はめっきりと涼しくなってきました!
どこからか虫の声も聞こえてきて、お月様を見上げることも似合う季節の到来です。

10月になり、早速『中秋の名月』で、【お月見】にはバッチリでしたね~♪(今月は、もう一度“フルムーン”があるそうですよ!)
昔から日本人は、月を眺めて楽しむ習慣がありました。
十五夜の月を『中秋の名月』『芋名月』と呼んで【お月見】をしてきました。一説には、平安時代に『中秋の名月』を愛でる【お月見】が始まったのだとか。
【お月見】とは、旧暦の8月15日に月を鑑賞する行事ですが、そもそも【お月見】って、月を眺めてお団子を食べるだけ…(!?)の風習なのでしょうか。
お団子やお餅、ススキや里芋などをお供えして月を眺める、【お月見】のルーツというのはよくわかっていないらしいです。
有力な説としては、中国ではお月見の日に里芋の収穫祭が行われており、その後、中国の宮廷行事としても行われるようになって、それが日本に伝わったというものです。
つまりは“秋の収穫を感謝するため”の行事、“秋に美味しい野菜や果物をいただけることに感謝するため”の風習が【お月見】ということでしょうか。
【お月見】に欠かせないものと言えば、ススキやお団子などのお供えものですよね。
ススキは、月の神様を招く依り代(=神霊や御霊が依りつく物や場所のこと)として供えられます。本来、月の神様の依り代は‘稲穂’なのですが、この時期に稲穂がなかったために、形の似ているススキを供えるようになったと考えられています。
また、古くから、ススキは魔除けの力があると信じられていて、【お月見】にススキをお供えすると、一年間病気をしないという言い伝えもあるようですよ!
【お月見】は、秋の収穫と深く関わりがあったことから、この時期に収穫される里芋をお供えするのが主流でしたが、その後、お米で作った団子も供えられるようになり、保存が効くことからお団子が主流になったのだとか。
白くて丸いお月見団子は、満月を表していて、そのお団子を食べることで、健康や幸せを得ると信じられるようになったということです。
また、昔~昔、その昔から…、月には何か不思議なパワーがあると信じられてきました。
月の満ち欠けは、海の潮の満ち引きにも関係することや、人の内なるパワーにも影響を与えること。そして、最近では、科学的な実証も進んでいるようですが、月のパワーから心身のリズムを整えていく『ムーンセラピー』というのもあるようです。
ともかく、月を眺める時に感じる心の静寂や高揚感、嬉しさや切なさ等々、私たちの心に強い印象を与えて止まないのが、月の不思議なパワーです。それらを含めて、昔の人は、【お月見】で日々の感謝を表して、心身のパワーもいただいていたのでしょう!
なんだか、風流で、感謝と祈りに満ちたステキな風習の【お月見】です。
心が和み、幸せの感情もアップしそうな、どことなく日本人の心根にも触れることができるような【お月見】を、『中秋の名月』の時だけでなく、忙しい毎日だからこそ、お子様とお月様を見上げて楽しんでみるちょっぴりの心の余裕も欲しいものですね!
そんな、「お月見」メニューとして、パワーアップ!できそうな【つくね】はいかがでしょうか。まん丸のお月様に模した【つくね】で、お家でも【お月見】なんて、楽しいかも!

【まん丸★つくね】 2人分(6個くらい)
・鶏ミンチ 200g
・里芋 3個
・芽ひじき ひとつまみ(水戻し)
・青ネギ 1本(輪切り)
・白ごま 少々
●生姜 1片(すりおろし小さじ1分)
●しょうゆ 小さじ1
●酒 小さじ2
●片栗粉 大さじ1
<タレ>・しょうゆ&酒 各大さじ3
・みりん 大さじ2
・砂糖 小さじ4
①里芋は、軟らかく茹でて、粗めにマッシュしておく。
②ボウルにミンチを入れて、●の調味料とともに均一に混ぜる。
(*鶏ミンチは混ぜすぎると固くなりますよ!)
③②に里芋、ひじき、ネギ、ごまを加えて、やさしく混ぜる。
④フライパンにサラダ油を小さじ1入れて熱したところに、スプーンを2本使って、まん丸になるよう形を整えて落とし入れていき、片面、2~3分づつ焼き付けていく。
⑤焼き色が付いたところで、別量の酒大さじ2を回し入れて、フタをして蒸し焼きにする。
(約1分位~)
⑥タレの調味料を合わせておいて、⑤の‘つくね’を取り出した後、軽く油を拭いて、合わせてタレを入れて少し煮詰める。
⑦クツクツとなったところで、⑤の‘つくね’を戻し入れて、タレを煮絡めてできあがり!
⑧温泉卵や目玉焼きをトッピングして、『満月お月様』にパワーアップです。
★熱々のごはんに、サニーレタスや大葉、ベビーリーフ等の上につくねをタレごとのせ、温泉卵や目玉焼きをトッピングしたら【つくね丼】!~美味しいですよ~。
気分転換に“食育メソッド”
コロナウイルスの影響で、短過ぎた夏休みも終わりましたが、学校生活も行事等が軒並み中止や変更になったり、未だ旅行や外食もままならず、気分転換をするのも何かと難しい日々が続いています。そのため、今まで以上に自炊の頻度が上がり、毎食の用意をするのにもなかなかモチベーションが上がらないというお母様、お父様も多いのではないでしょうか。そんな親の想いをよそに、お子様たちからは「あれは嫌だ!」「これは嫌い!」などと好き勝手なことを申します。
『子供たちの健やかな成長を支える基礎として、食に関する知識と食を選択する力を養う』=【食育】が重要とよく言われますが、【食育】の一環として、お子様と一緒にお料理をしてみませんか。これから受験に向けて、大事な時期を迎えるお子様ですが、気分転換は大切です。気分転換がゲームだけでは、それもそれで気になりますから、休日のランチを親子で作ってみる!のも、良いかもしれません。
案外、お料理って、食材や道具を準備したり、分量を計算して計ったり、手順の段取りを考えて、先の状況を把握したり…等、算数や理科、生産地の事を知る社会、国語の読解力のような推測して想像する力など、学習と重なるところが多いように感じます。
といっても、一体何から始めたらよいのかしら~!?という方も多いかと思います。
基本は、お子様の食べたいものや、作ってみたいものでOK!ですが、今回は、お子様も大好きで、簡単な親子作業でできそうな【親子どんぶり】にチャレンジしてみませんか。
ご家庭でも手軽にできる「食育メソッド」でお届けしてみます~♪

【親子どんぶり】 2~3人分
・鶏モモ肉 小1枚(約200g)
・玉ねぎ 1/2個(約100g)
・卵 3~4個
- 醤油 大さじ2
- みりん 大さじ3
- 砂糖 大さじ1
- だし汁 100cc
(水100cc+和風だし小さじ1)
・みつば、ねぎ、海苔等 お好みで
①親子一緒に、手を洗う。
②親子一緒に、材料と道具の準備。調味料を合わせる。
③子 ・玉ねぎを剥く。とんがった方から剥くとむきやすいよ!
親 ・鶏モモ肉をひと口大に切る
④子 ・ボウルと菜箸を準備し、卵を割って混ぜる。
親 ・玉ねぎをスライスする。
⑤子 ・フライパンに調味料と玉ねぎを入れる。トッピング用の海苔やみつばをちぎる。
親 ・玉ねぎがしんなりするまで煮て、切った鶏肉も入れて裏表返しながら煮る。
⑥子 ・丼にごはんをよそう。
親 ・鶏肉に火が入ったら溶いた卵の2/3量を回しかけ、蓋をして卵が固まるまで煮る。
・火を止めて残りの卵を回しかけて、できあがり!
⑦親子一緒に、盛り付けて、手でちぎった薬味をトッピングする。
⑧*いただきます!*
⑨親子一緒に、お片付け~~♪
フライパンで簡単に、とろっとろの【親子どんぶり】ができあがります。
卵は「栄養価の優等生」と言われますし、ふわとろの卵でハッピーな気分にしてくれること、間違いなし!です。
何より親子一緒に作ることで美味しくて、楽しい嬉しい食卓になりますね。
【冬瓜】は夏が旬!
‘とうがん’は‘冬の瓜’と書きますが、実は夏が旬(7月~9月)の野菜です。
冷暗所に保存しておけば冬まで保つとされることから【冬瓜】と呼ばれるようになったと言われています。水分を多く含みクセが少なく、煮物や汁物など様々な料理に活用しやすい野菜で、この【冬瓜】には健康に必要な栄養素が豊富に含まれています。

【冬瓜】には、たっぷりと水分が含まれていることから、夏の暑い時期にはカラダを冷やす効果があり、暑い時期にあたり熱中症予防として積極的に取り入れたい野菜のひとつと言われています。
さらに【冬瓜】には、お子様だけでなくご家族皆様にとって嬉しい栄養効果がたっぷりと含まれています。免疫力を高めて、頭&カラダを活性化させる効果が期待できる栄養素を含んでいるのです。
【冬瓜】に含まれるこれらの効果が期待できる栄養素とは、
- カリウム
- ビタミンC
- 食物繊維
*“カリウム”は、主に野菜や果物に多く含まれるミネラルで、ナトリウムと相互に作用して細胞の浸透圧調整をする働きがあります。むくみ対策や高血圧予防があります。
*“ビタミンC”は、強い抗酸化作用を持っており、健康な細胞を保つことが期待できます。
夏風邪でノドが痛くなる…、なんてお子様にはイチオシです。
*“食物繊維”は、便秘の解消や腸内環境の改善に持って来い!です。
また、もともと【冬瓜】はその95%が水分ということもあり、100gあたりのカロリーがなんとたったの16㎉という低カロリー食材ですから、ダイエット中と言われるお父様お母様(!?)、要注目ですよ~♪
そんな【冬瓜】を使った料理の代表といえば、煮物です。【冬瓜】自体にクセが少ないので、あっさりと和風の味付けで煮込むことで食欲の低下しやすい暑い夏でも食べることができます。この煮物には豚肉のミンチや薄切り肉、バラ肉等を入れることが多く、これらのお肉を使うことで、流れ出てしまうビタミンB1の量を減らすことができます。
ビタミンB1といえば、疲労回復効果がバツグンで、夏バテ予防にも持って来い!の栄養素です。ビタミンCだけでなくビタミンB1も補えることで、まだまだ暑くてバテ気味等からくる食欲のダウンしがちなこの時期におすすめの‘元気の出る食材’となります。
でも、【冬瓜】は長時間の煮込みにはNG!水に溶ける性質の“カリウム”の流れ出てしまう量が増えてしまいますから、【冬瓜】を煮込んだり、スープにしたりする際は、大きさを大きめにカットして、レンジであらかじめ加熱した後煮込む等、煮込む時間を少なくしてみてください!
そこで、今回のレシピは、【冬瓜と豚バラ肉の南蛮煮】です。豚バラのブロック肉を使ってボリューミーに仕上げます。‘南蛮’とは、油や赤唐辛子を使った料理のことを言います。
豚肉は余分な油を落としてスッキリあっさりと仕上げますが、コクと旨味と少しの辛味で食欲がアップする一品ですよ~♪

【冬瓜と豚バラ肉の南蛮煮】 2人分
・冬瓜 1/4個(約500g)
・豚バラ肉(塊) 200g
・サラダ油 大さじ1/2
- だし汁 1/2カップ
- 酒・砂糖・醤油 各大さじ2
- みりん 大さじ1
- 赤唐辛子(小口切り)1本
- 生姜(薄切り) 1片
①<冬瓜を切る>・冬瓜は4㎝幅に切って、種とワタをスプーンで取り除く。・皮を薄く剥き、水に放す。
~*ワタはしっかり、皮は薄めに取り除くのがポイント!です。

②豚肉は2㎝長さに切って、フライパンにサラダ油を熱して、豚肉の全面を中火でよく焼く。ザルに取り、熱湯を回しかけて余分な油を落とす。~あっさりと仕上がります!
③鍋に水気を切った冬瓜と豚肉、生姜、赤唐辛子を入れ、●をすべて加えて強火にかける。煮立ったらアクを取り、落し蓋をして中火で10~15分煮る。
④煮汁が無くなったら、鍋の手前から向こう側に動かすようにあおり、具の上下を入れ替えて均一に味を馴染ませる。(鍋返し)盛り付けて完成です!
【冬瓜】の冬という漢字から冬に食べるイメージを持たれていた方も多くおられたかもし
れませんが、早速食べてみたくなったのではないでしょうか(!?)
ぜひ、スーパーで購入される際は、鮮やかな緑色でどっしりと重く、水分をしっかりと含
んだ、みずみずしい【冬瓜】を探してみてくださいね。
体の中からクールダウン!
8月になり、一層ムシムシジメジメの暑苦しさが増してきました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
コロナ対策のための‘暑さの中のマスク’に加え、熱中症対策もあって、‘エアコンにこまめな水分補給’と、「何となくだるい!」「食欲がない~」などといった、早くも夏バテのような症状はありませんか?!
夏バテの原因として考えられるのは
- 汗をたくさんかく事で、体内の水分が不足する上に汗と一緒に失われるミネラルも不足してしまうケース。
- 暑さで胃の消化機能が低下し、体に必要な栄養素の吸収が悪くなり、食欲不振を起こすケース。また、冷たい飲み物ばかりを飲み、胃腸が冷えて胃の働きが低下して食欲がなくなるケース。
- 冷房の効いた室内から暑い屋外に出ることで、体温調節している自立神経が気温の変化に対応しきれなくなるケース。
など、いずれの原因も暑さからくるものです。
人は体温が36~37度の時が一番スムーズに活動できると言われています。火照ったカラダは、この体温に保つため汗をかくことで体温調節をするというわけです。
夏の旬の野菜や果物には、この火照ったカラダを冷ます効果があるそうです。
これを『クール・ベジ』(‘ベジ’とはベジタブル(野菜)のこと)と呼ぶそうです!
この『クール・ベジ』のポイントは「カリウム」という成分。これがカラダを冷やすのに一役買っているそうです。この「カリウム」は尿の排出を促して、カラダの余分な熱を逃がす働きがあり、また夏野菜や果物には水分を多く含むものが多く、水分とともにカラダの余分な熱を対外に放出してカラダをクールダウンさせる効果があるようです。
『クール・ベジ』は<食のクール・ビズ>!カラダの余分な熱を逃がすカリウム&水分を含む夏野菜で熱中症予防や夏バテ予防に活用してみましょう。
『クール・ベジ』=夏が旬の野菜
・トマト きゅうり ゴーヤ オクラ とうもろこし 茄子 ピーマン 枝豆 冬瓜
ズッキーニ かぼちゃ モロヘイヤ みょうがetc.
『クール・ベジ』=夏が旬の果物
・桃 メロン ぶどう ブルーベリー オレンジ パイナップル マンゴー パパイヤ スイカ キウイフルーツetc.
旬のものは、その季節に栄養価が一番高くなります。夏のストレスに負けずに育った
夏野菜、果物は私達の体調を整えてくれる心強い味方。
これらの『クール・ベジ』を食べて、=<食のクール・ビズ>!食欲のない時でも、
しっかりたくさん食べられる【冷製スープ】のご紹介ですよ。

【枝豆のヴィシソワーズ】 3~4人分
・枝豆 150g~今回は冷凍を使用
・じゃがいも 1個
- 牛乳 400~500cc
- コンソメ 1個
- 塩 適量
・レモン汁 小さじ1程度
①じゃがいもは、ラップで包んでレンジで軟らかくして、皮を剥き5㎜幅くらいにスライスしておく。
②枝豆は茹でて、皮から取り出しておく。
③①②と●をミキサーに入れてしばらく回し、トロリとしたらできあがり!
仕上げにレモン汁を加える。
④冷たくして、食べる前にパセリや生クリーム、クルトン等をトッピングしてOK!
~クセになる美味しさです~♪

【楽チン!ガスパチョ】 3~4人分
- トマト 2個
- 赤パプリカ 1/3個
- 玉ねぎ 1/3個
- きゅうり 1/2本
- アボカド 1/3個
- レモン汁 小さじ1~
- ニンニク 少々(チューブでOK)
- 塩 小さじ1/2
- 砂糖 小さじ1
- コショウ 少々
- オリーブ油 小さじ2
・パセリ、バジル、タバスコ、粉チーズ お好みで!
①●の材料をミキサーやフードプロセッサーに入れて、なめらかにする。
②冷やしてできあがり!
*冷凍のトマトを使うと、皮はすぐに剥けるし、すぐに冷たいスープでいただけます♪
③刻んだ野菜や・のトッピングをお好みで!
~“飲むサラダ”とも言われている【ガスパチョ】です。
パンを入れてトロミをつけたりしますが、今回はアボカドを加えて、少しトロリ~っとさせてみました!
カリウムだけでなく、ビタミンやカロテンとの相乗効果で抗酸化作用や免疫力も高まります。汗をかいた時、食欲のない時の【冷製スープ】でカラダの中からクールダウン!
暑い夏を元気に乗り切っていきましょう!
旬のトマトでケチャップ~♪
長かった梅雨がようやく明けたと思ったら、毎日、うだるような暑さ!
コロナウイルスの心配もあり、もうすでにバテバテ気味の予感です。
とかく日本の夏は高温多湿で、その蒸し暑さばかりが強調されがちですが、昨今は高温過ぎて…つらいですね!エアコンなしで過ごすのはつらいですし、どこに行ってもエアコンが効いていて(涼しくて気持ちはいいのですが)エアコンに疲れてきませんか!?
その上、冷たい飲み物や食べ物ものばかりで、食欲もなくなってくるし体内は冷えて内臓機能も鈍ってくるようです。
- 体がだるい●食欲がない●お腹周辺が冷たい●下痢をする●肩や手足が痛い
このような症状が出てきたら要注意!
これは“夏バテ=「冷房病」”だそうです。この“夏バテ=「冷房病」”を防ぐのに東洋医学、漢方の世界の薬膳レシピでは、夏の旬の野菜である『トマト』が良いそうです。
赤色の食材は薬膳では夏の色とされ、“夏バテ=「冷房病」”にもいいそうです。
赤色の食材は<心>の機能を高めるといわれています。<心>とは血液の循環機能や精神活動をコントロールする場所のことをいうそうですが、夏は高熱や汗で血液が濃縮されることによってカラダがだるかったり、ボーッとしたり、イライラしたりするのだそうです。
そこで、旬の野菜 赤色の‘トマト’!
‘トマト’は旬の野菜ということもあって、家の庭やプランターでもどんどんできたり、いただいたり、安く買えたり…とたくさんあり過ぎて消費に困ったりすることもあるのではないでしょうか?そんな時は、まずトマトを洗って水分を取った状態でジップロックの保存袋に入れて、冷凍庫で冷凍保存がGOODですよ!食べたい時は、凍ったままのトマトをたっぷりの水につけた中で、指先でこすると皮がツルっとむけるんです。
生食するなら、半解凍ぐらいでおいしく食べられます。
‘トマトが苦手!’というお子様も時々おられますが、(実は、我が家の三男も形のあるトマトは食べられません~というか、食べません!)煮込んだり、スープにしたりだと大丈夫だったりしますから、この際【トマトケチャップ】を手作りしてみませんか!
手作りの 【トマトケチャップ】は、冷蔵庫で3週間ほど保存が可能ですから、つけたりのせたり、混ぜたりと美味しくて安心な手作り調味料になりますよ。

【手作りトマトケチャップ】
・トマト 5~6個(カットする)
・りんご 1/2個(すりおろし)
・玉ねぎ 1/2(みじん切り)
・ニンニク 1片(みじん切り)
・塩 小さじ2
・砂糖 大さじ1/2
・ローリエ 1枚
・黒コショウ、オレガノ・バジル・パセリ・ナツメグ(お好みで) 適量
- カットした食材をミキサーに入れて撹拌する。(ツブツブ感が好きな人はつぶさなくてもOKです。)
- ①を鍋に移し入れ、砂糖、塩を加え、ローリエをのせて、お好みのトロミになるまで煮詰める。(1時間程度に詰める。)
- ローリエを取り出し、お好みで黒こしょうやスパイス等加え混ぜたら、できあがり!
身近にある材料たったの4つだけで、無添加でおいしいトマトケチャップの出来上がりです。お子様たちの大絶賛も間違いなし!
コロナの影響で今年は短い夏休みですが、この【トマトケチャップ】を使って【ナポリタン】でランチはいかがでしょう~♪
たっぷりの‘トマト’の入った【ナポリタン】を食べて、“夏バテ予防”です。

【ナポリタン】 2人分
・パスタ 200g
・お好みの野菜
・ベーコンorウインナー
①たっぷりのお湯に、飲んでみて美味しいと思う分の塩を加えて、パスタの袋表示の時間プラス1分茹でる。(7分表示の場合は8分茹でます。)
②①の湯切りをしたら、水洗いして、しばらく冷蔵庫で寝かせると、モッチリ感がUPします。
③フライパンにお好みの野菜、ベーコン等を炒め、トマトケチャップを加えて炒め合わせ、②のパスタを炒め合わせればできあがり!
お子様もお母様と一緒にケチャップ作りをお手伝いすると食べてみたくなると思いますから、万が一トマトが苦手のお子様でもきっと美味しく食べてくれるはずです!
大切な栄養素【鉄分】!
コロナに始まり、ジメジメ蒸し蒸しの暑~い毎日で、疲れなのか何だか毎日カラダがだる~いお子様も多いのではないでしょうか(!?)
大人のみならず、子供たちだって体調を整えるのは大変です。
風邪でもないのに頭が重かったり、だるくて疲労感が抜けなかったり、お肌もムズムズカサカサして掻きむしるせいで、さらにボロボロ~~。
集中力にも欠けてしまいそうで、大切なお勉強タイムにも影響してしまいそうです。
こんな症状って、どうも【鉄分の不足】が一要因になっているようなのです。
【鉄分不足】=‘貧血’と思いがちですが、貧血だからめまいや立ちくらみ等~というわけではなく、様々な症状として、疲労感や倦怠感、睡眠障害や頭痛、肌荒れ、鬱感などが挙がってくるらしいのです。
【鉄分】は、日々の元気のために欠かせない大切な栄養素!
毎日を元気いっぱいで過ごすためにも、セッセと【鉄分】が含まれる食材を摂ることはとても大切になって来ます。
【鉄分】が豊富に含まれている食材として、真っ先に思い浮かぶのがレバー!!
レバーなんて下処理が面倒な上に、食べにくいせいか子供にもなかなか受け入れてもらえずで、日頃の食卓にはなかなか取り入れにくいメニューのひとつではないでしょうか。
そんな【鉄分】を毎日の食事からマメに摂取するというのは結構難しいものがありますから、他にも【鉄分】の多い食品のほんの一例のご紹介です。
豚・牛・鶏レバーはもちろん、かつお、いわし、マグロ、うなぎ、アサリ、小松菜、パセリ、枝豆、大豆等の豆類、高野豆腐、ごま、ひじき、アオサ海苔、黒砂糖etc.
これらは、動物性食品やビタミンCと一緒に摂取することで【鉄分】の吸収率がアップするそうです。摂取できる鉄分量に数倍の差が出てくるようです!
今が旬のかつおやあさり、枝豆などはおつまみにも最適ですし、うなぎはもうすぐ‘土用の丑の日’がやって来ますから、家族みんなで食べていただけそうですね。
しかし、今回は絶対に家族みんなに食べてもらえる【ニラレバ炒め】で、【鉄分】の王様=レバーに果敢にアタックです!

レバーでも、お惣菜の‘鶏レバー串’や‘甘辛味のレバーのしぐれ煮’etc.を使って、超簡単に作ります。これなら、しっかりと味が付いていて、レバー特有の味や匂い、食感も消されているので大丈夫!我が家の全員が食べられるのですから~♪
炒めたら終わりの時短料理なので、暑い時期の料理にもバッチリです。

【ニラレバ炒め】 2~3人分
・レバーのしぐれ煮 約100g
・ニラ 1束(90g位)
・もやし 1/2袋~カサ増しです!
・ゴマ油 大さじ4
・ごま 適量~トッピング
<タレ>
醤油&オイスターソース 各大さじ1
砂糖 小さじ2
酒 大さじ2
にんにく&生姜 各小さじ1(すりおろし)
片栗粉 小さじ1/2~1
*タレは焼肉のタレで代用OK! 約大さじ3~4 お好みで!
①タレを混ぜ合わせておく。
②ニラ、もやしを食べやすい大きさにカットしたら、フライパンにゴマ油を入れ、レバーとニラ&もやしを入れて炒めたら、①のタレを絡めてできあがりです。ごまをトッピングして栄養価をアップしましょう!
【鉄分】がたっぷり含まれている食材を覚えておいて、それらを細めに取り入れるように日々心がけるだけでも効果がありそうです。
“元気=健康は、食事から~!”ということですね!
『脳腸相関』で脳を育てる(!?)
大人のみならずお子様だって、学校やプライベート等、人間関係や日常生活において何かとストレスを感じることが多い昨今です。
ストレスを感じると、平常心を乱したり気持ちの余裕を奪うだけでなく、不眠や、お腹が痛くなり便意をもよおしたりと腸の不調にもつながります。これは脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるからで、様々な症状は、腸の状態が脳の機能にも影響を及ぼすことを意味しています。
このように、脳と腸には密接な関係があり、生活のリズムが崩れると脳と腸の活動パターンにズレが生じてしまいすし、また脳の活動時間と腸の活動時間の歩調が揃うと、腸が正常に機能しやすくなり、腸内細菌も活発に働くようになるようです。
こうした脳と腸との意外な関係を『脳腸相関』と呼ぶそうです。
これまでは、「脳から腸」への影響については認められていましたが、最近では「腸から脳」への影響も明らかになってきているようなのです。
人に影響を与える3つの脳内物質と言われている“セロトニン(幸せホルモン)”“ノルアドレナリン(集中ホルモン)”“ドーパミン(やる気ホルモン)”=これらの脳内物質の素となるものは、腸や腸内細菌の働きによって作られているのだとか。
特に、リラックスや幸せを感じる時に分泌される“セロトニン”の素となる物質は90%程度が‘腸の粘膜’にあるそうです。腸で脳を司るような脳内物質の生成が始まる訳ですから、腸内細菌で脳を育成する(!?)ことになるのかもしれません。なぜなら、腸内環境を整えることで、免疫力が上がるだけでなく、集中力が上がったり精神的に安定することができるのですから!
【脳の活性化=腸の活性化】
“腸は第二の脳”と、よく言われるのもこういった事からでしょうか。
そこで、大事なのが日頃からの<腸活>!!
<腸活>はデトックスを促し、腸内フローラのバランスを整えることで、腸内に毒素が停滞するのを防ぐことができます。それによって、大腸から栄養素がしっかりと吸収され、身体機能が活発に働きやすくなっていくので、この『脳腸相関』を良好にして、<腸活>=脳活を活発にすることで脳を育成することが、受験を控えているお子様にとってはポイント!となるかもしれませんね~♪
そこで侮れないのが、腸の活発な活動に大活躍する‘水溶性食物繊維’を持つ食材たちです!
【水溶性食物繊維】の代表食材
・人参・キャベツ・ごぼう・オクラ・長芋、里芋・納豆・こんにゃく
・海藻、きのこ類・果物
暗記力や集中力を上げたり、精神的に不安定な状況を改善したいのであれば、腸内環境を整えるためにもオススメです!
今回は、腸活に持って来い!のお手軽二品のご紹介ですよ。

【オクラナムル&長芋のビビンバ丼】 2人分
・オクラ 1パック(約80g)
・A ごま油 小さじ1
ニンニク 小さじ1/4(すりおろし)
塩 小さじ1/6
・長芋 80g
*酢を小さじ2程度混ぜておくと変色しません!
・豚こま肉 150g
*酒 大さじ1/2、こしょう少々、片栗粉小さじ1/2を揉み込んでおく。
・B コチュジャン 大さじ1
酒 小さじ2
醤油、砂糖 各小さじ1
サラダ油 小さじ1
①オクラは分量外の塩で、板擦りをして下処理をしサッと洗って小口切りにする。
②熱湯で色よく茹で上げたら、水気をしっかり切って、Aを混ぜ合わせる。
③長芋はすりおろし、酢をまぜる。
④豚こま肉は、一口大に切り、*の下味を付けて、フライパンに油を熱し、豚肉を炒める。
Bを加えてサッと絡める。
★コチュジャンが辛いようであれば、味噌で味付けます!
⑤器にごはんを入れ、②③④を盛り付けてお好みで、白ごまと焼き海苔を、またコチュジャンをトッピングして完成です。

【ごぼうのきんぴら汁】 2人分
・ベーコン 2枚
・ごぼう 50g
・人参、しめじ 適量
・厚揚げ 1枚
・だし汁 800cc
・味噌 大さじ3~4
・ごま油 小さじ2
・山椒 お好みで
①食材は食べやすい大きさに切っておく。
②鍋にごま油を熱し、①の食材を入れて炒めたら、だし汁を加えてアクを取りながら、
やわらかくなるまで煮る。
③柔らかくなったら、味噌を溶き入れて器に盛る!お好みで山椒をふりかけていただきます。
デトックスでストレスフリーに!
長~い長いコロナ自粛生活に少し光が射し、やっと新学期・新クラスの学校生活が始まりました。自粛生活に端を発して、何かと新しいことが多すぎる新生活でカラダが、心が疲れてしまっている、そんなお子様たちも多いことだと思います。
何だか疲れてしまった自粛生活の後から新しい環境のスタートで、お勉強等で新しいことを学びつつ人間関係にも順応していく…、って案外ストレスがMAX!なんてことも。
そんなお子様に限らず、大人の方々にもストレスが緩和できるように、少しでもリラックスできるように“食でデトックス”の提案です。
カラダに良い食事を意識しながら栄養豊富な食材や目新しいスーパーフードなど、食品そのものには案外注目しがちですが、実は「摂る」と同じくらい重要なことが「出す」ことです。
せっかく意識して摂った食材や食品も、量が過剰だったり、消化不良や便秘などで体内に残ると毒素となってしまいます。ですから、時々は“デトックス”を意識して、毒素を出してくれる食で、巡りの良いカラダを目指してストレスフリーになりましょう!
ところで、ストレスって、どんなものなのでしょうか?
例えば、ボールに圧力がかかって、ゆがんだ状態のことを“ストレス”というようです。
ストレス状態を引き起こす要因が加わって、心身に負荷がかかった状態なのだそうです。
“ストレス”も受け止め方で違ってきて、大きく二つに分かれます。
- 良いストレス:目標、夢、良い人間関係(ライバル等)など、自分を奮い立たせてくれたり、元気にしてくれたりする刺激とその状態
- 悪いストレス:過労、悪い人間関係、不安など、自分の体や心が苦しくなったり、嫌な気分になったり、やる気を無くしたりするような刺激やその状態
- リラックスできる方法で良いストレス状態になることも必須となりますよ!
そこで、今回はお休みの日のランチや時短料理にもバッチリ!の「ニラ」をたっぷりと使用した【中華混ぜそば】をご紹介します。今回のキー食材は「ニラ」!
「ニラ」には、カリウムという栄養素を多く含み、体内の塩分濃度を調節しながら余分な水分を排出する働きがあります。むくみ改善にも効果があり、ビタミンAやC、Eなどβカロテンも豊富なので、血流を良くして免疫力アップの効果も期待大です。
そして、なんといっても「ニラ」はスタミナ料理に使われることが多く、疲労回復に効果的な食材としても有名です。ビタミンB1との相性が良く、豚肉やうなぎ、レバーや納豆などと摂取することで、さらに効果的になります。
簡単に「ニラ」の効果を最大に活かすポイントは、ニラを摂取する時に油と一緒に食べることなので、是非、頭の片隅に入れておいてくださいね!

【中華混ぜそば】 2人分
・ニラ 1束
・豚ミンチ 150g
・中華麺 2玉
・白ネギ 1/2本
(半分はみじん切り、半分は白髪ネギにします。)
・ごま油 大さじ1&大さじ2
・水溶き片栗粉 小さじ1程度
- オイスターソース 大さじ1
- 酒 大さじ2
- 醤油 小さじ2
- 酢 小さじ1
- 豆板醤 小さじ1/2~お好みで
- にんにく(すりおろし)少々
<トッピング>:糸唐辛子、鰹節、酢
①ニラは5㎜幅位に切って、大さじ1のごま油でサッと炒めて一旦取り出す。
②大さじ2のごま油と白ネギのみじん切りを炒めて香りが出たら、豚ミンチを炒め、色が変わったところで、合わせておいた●を入れて、1~2分位炒めた後、水溶き片栗粉でトロミをつけたらOK!
③中華麺は袋の表示どおりに茹でたら、ザルにあげて水気を切り、器に盛りつけたらニラと②をのせて、白髪ネギに鰹節、糸唐辛子をトッピングして完成。
*お好みで、お酢をかけながらお召し上がりください!あっさりサッパリとした味になりますよ♪
「朝ごはん」で生活リズムを整えて!
コロナによる自粛生活後の学校再開等で、思った以上に毎日疲れていませんか。
梅雨時という体調を崩しやすい季節でもありますので、しっかりと栄養と休養をとることが大切ですね。
本当に、体調管理の難しさを感じるだけでなく、長い長い休み明けということもあり、「生活リズムを整えること」の大変さを感じます。
「生活リズムを整える」には、一にも二にも朝ごはんをきちんと食べること!
朝ごはんは、1日のエネルギーの源ですから、朝はきちんと早起きをして、しっかり‘朝ごはん’を食べましょう!(百も承知だとは思いますが…)
こんなダルダルの自粛休みボケから早く抜け出すには、集中力を高める「レシチン」を含む食べ物が良いそうですよ~!
「レシチン」には、情報伝達などをスムーズにする働きがあり、記憶力アップの働きもバッチリ!です。
カラダ&頭が資本となる受験生にとって、最強の栄養素のひとつでもあります。
この「レシチン」は、特に大豆製品に多く含まれていて、納豆や豆腐、味噌やきな粉などいろいろな食材に含まれます。
そこで、ダルダルな休み明けの‘朝ごはん’に、「レシチン」を多く含む “納豆”と“お味噌汁”で、簡単だけど最強な【朝定食】にしてみてはいかがでしょうか。
ダルダルな休み明けだけでなく、寝起きはなかなか頭が働かないもの。
午前中から集中力を高めて、シャッキリ!と、おまけに勉強の効率も上がるように、朝からモリモリいただける<納豆朝定食>のオススメレシピです。
実は、冷蔵庫内にあるものをごはんにのせるだけ!
“納豆”が苦手なお子様でも、納豆臭さを感じることなく食べられてしまう、味噌+梅肉を混ぜた納豆ですから、忙しい朝には重宝すること間違いなし~♪です。
‘朝ごはん’で “納豆”と“お味噌汁”を食べていれば、どことなくホッ!とする私です。

【納豆の梅味噌丼】 1人分
・ご飯 1膳
・納豆 1パック
- 梅肉 大さじ1
- 味噌 大さじ1
- 水 小さじ2程度
- 付属のタレ 1パック
・大葉 2~3枚
・白ごま 適量
①ボウルに●を入れて混ぜ合わせておく。
②大葉は軸を切落として千切りにしたら、①に混ぜる用とトッピング用に分けておく。
③器にご飯を盛って、粘り気が出るまで混ぜ合わせた納豆をのせたら、大葉のトッピング用と白ごまを振ったらできあがり!
*ご家庭のお味噌汁とご一緒に、【朝定食】の完成です。
パワーフードのお米!で【みたらし団子】
お米はパワーフード!
お米は炭水化物や糖質というイメージが強いですが、実はその他の栄養素も豊富です。炭水化物が一番多い割合ですが、ビタミンやミネラル、食物繊維、たんぱく質も含まれていて、同じ炭水化物のパン類よりも脂質が少なく、たんぱく質が豊富なため、たんぱく質源としてよく働くという利用効率が高いのです。
さらに、持続力が発揮できる炭水化物の食品ということで、長い時間、運動やお勉強などカラダや頭を使うエネルギー源として働くのが得意なのです。私達が思っている以上に“お米の栄養”は優れていますので、やっぱり<何といっても日本人はお米!>ということでしょう!
カラダと脳のエネルギー源のお米ということですが、皆様もご存じのとおり、人間の脳は糖質しかエネルギーとして利用することができません。いわゆるブドウ糖です。糖質を摂らなければエネルギーが供給されず、脳は活発に活動することができなくなります。
おまけに、なんと人間のカラダに必要なエネルギーの50%~70%程度は炭水化物から摂ることが理想とされているそうです。そして、お米は粒食のため、「しっかり噛める」というメリットがあります。よく噛むということは、脳を刺激して脳機能をアップし、自律神経のコントロールを促すことはもちろん、唾液がよく出て消化吸収率が上がるので、胃腸をしっかり鍛えて動かしてくれる食材でもあるのです。
お米は、カラダと心と脳を活性化させて、持続力と集中力アップにつなげるためには持って来い!の【受験生のパワーフード】と言えそうです。
そんなお米のパワーを見逃すわけにはいきませんよね!まだまだ続くステイホーム。
お子様の三食の食事やおやつ等、切実な関わりの中でアレコレと言うつもりはありません。
ただ、お子様にも喜んで楽しんでもらいたくて、“お米のパワー”を活用しながら、皆様ご一緒に、残りご飯で【みたらし団子】を作って、おやつにしてみませんか~♪残りご飯なのに、素早く作って食べられ、パワーフードでかつエネルギーチャージにもなる【みたらし団子】ですよ!

【みたらし団子】
・残りご飯 茶碗1杯
~約15個位のお団子ができます!
(・片栗粉:水 各大さじ1)
<みたらしのタレ>
- 醤油 大さじ2
- 砂糖 大さじ3
- みりん 大さじ2
- 片栗粉 大さじ1
- 水 80~100cc位
①タレの●を鍋に入れて火にかけ、よくかき混ぜる。お好みのトロミがついたらOK!
*レンジ600wで1分20秒くらい加熱でもOK!ですが、固まるので途中でかき混ぜなら行なってください。
②ご飯を温めてボウルに入れ、水で濡らした麺棒でつく。多少潰したら、(水と片栗粉を入れて、さらについて粒が無くなってきたら)ひと塊になるようにこねる。
③手を濡らして、丸めて団子を作り、(沸騰したお湯に入れて浮いてきたら水に取り上げて)タレをかけて、できあがり!
*テフロン加工のフライパンで丸めた団子に焼き目をつけたら、本格的なお団子に~♪
★もっと、簡単に手抜きでもOKならば、ご飯をついて丸め、タレをかけるだけでも美味しい【みたらし団子】です。
ココアの力!
5月になり、楽しいはずのGWも、そのまた後も、外出自粛要請の延長でまだまだ‘ステイホーム’の日々が続きます。そんな中、ほんの少しほっこり~♪できそうな、気分転換ができそうな一品を見つけました!
それは韓国で人気の飲み物の【ダルゴナコーヒー】です。牛乳の上にフワフワのコーヒーがのっていて、ほろ苦いコーヒーとミルクがデザート感覚で楽しめるドリンクです。~♡
でも、お子様にはコーヒーはちょっと…。
それならば、カラダに良いと言われている“ココア”で、【ダルゴナココア】はいかがでしょうか。

“ココア”は冬の飲み物のイメージがありますが、お勉強に頑張るお子様にはいつでも毎日でも飲んでほしいのが、絶対“ココア”です。
“ココア”がカラダに良いと言っても何がいいのか(!?)
“ココア”の原料はチョコレートと同じカカオ豆。カカオ豆を粉砕して分離したカカオマスから脂肪分を除いたものが“ココア”です。“ココア”の主成分はカカオポリフェノールで、強い抗酸化作用があり、血糖値の抑制や血流の促進の他、多様な健康効果ある‘カカオ’がカラダに良いと見直されるきっかけになった成分です。ほかにもリラックス効果があって、食物繊維やカルシウム、マグネシウム等ミネラル類も含むのが、「ココアの力!」なのです。
“ココア”の健康効果を効かせるには、ピュアココアを1日に2~3杯を目安に飲むのが良いそうです。
“ココア”の健康効果を挙げてみました。
①リラックス効果:【ココア】に含まれる香り成分と体を温める働き等で深くリラックスできます。ストレスも和らげてくれますよ!
②冷え改善効果:【ココア】には生姜よりも冷えを改善する効果があるとされています。体を温める保温効果が持続します!
③風邪予防・ウイルス予防効果:【ココア】は免疫を高め、風邪を予防します。インフルエンザウィルスに対しても強い感染阻害効果があるそうで、特に今の時期、免疫力は大切です。
④胃の健康効果:【ココア】の豊富なポリフェノールは胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌の除去効果が高いそうです。
⑤貧血の改善:【ココア】はミネラル・鉄分が多く、貧血気味の人の予防や改善に効果を発揮します。
おまけに、
⑥がん予防
⑦美肌効果・アンチエイジング効果
⑧心臓・動脈硬化予防の効果があるので、お子さんだけでなく、お父様、お母様にもオススメしたいたくさんの「ココアの力!」です。
そんな“ココア”のアレンジレシピとして、お子様からの羨望の眼差しを浴びそうな【ダルゴナココア】の紹介です。お子様との長い長いステイホームに一役かってくれそうな【ダルゴナココア】で、「ココアの力!」を発揮して頑張っていきましょう。

【ダルゴナココア】 1人分
- ピュアココア 大さじ2
- 砂糖 大さじ1~2
- 生クリーム 大さじ6*植物性の生クリームが◎!~コーヒーフレッシュ6個でもOK!です。
- 冷たい牛乳 150~200ml位
①ボウルに●をすべて入れて、ひたすら混ぜるだけ!ハンドミキサーを使うと簡単です。
2~3分位混ぜて、モッタリしたらOK!
★ココアは油分があるためか、生クリームがないとクリーム状になりませんでした!
(水だと、泡立ってペースト状にはなりますがクリーム状にはなりません。)
②グラスに冷たい牛乳をグラスの2/3量注いで、①を盛り付けたらできあがりです。

お母様のための【ダルゴナコーヒー】のレシピもお伝え致します~♪
- インスタントコーヒー 大さじ2
- 砂糖 大さじ2
- 水 大さじ2
- 冷たい牛乳 150~200ml位
~グラスの2/3量まで注ぐとBEST!です。
作り方は同様です!
★コーヒーは簡単に水で、クリーム状になります。
ビニール袋に入れて振り続けるだけでもクリーム状になりますよ~♪
ご家族皆様でお楽しみくださいませ。
LET’S CHALLENGE!ワンポットパスタ♪
今年の春は、いつものような桜が咲いてルンルンうきうきの春気分とは違います。
コロナウイルスによる土日外出自粛要請等で、本当に自宅に居ることの多い日々ですね
気分が滅入ってしまいますが、こんな時だから、お子さまたちと“Let’s Challenge!パスタクッキング”はいかがでしょうか。
フライパンに食材を投入するだけで、フライパンひとつでパスタができる、最近流行りの‘ワンポットパスタ’です。
お子さまと一緒に、冷蔵庫内にあるもので何が食材にOK!かを探しながら、切ったり炒めたりするお手伝いでもOK!ですし、お母様は後方で見守り隊としてお子さんに作ってもらうのもOK!かもしれません。 それほど簡単な‘ワンポットパスタ’です。
フライパンでお好みの具材を炒めて、いつものパスタソースより多めの茹で汁と調味料でスープを作り、後は同じフライパンにパスタを投入で茹で上がるのを待つだけ! パスタを茹でている間に具材の旨味も溶け出して、スープはますます美味しくなるし、洗い物もフライパンのみ(!?)程度の最小限度で済みます。
お子さまたちにとっても、きっと何にでも自信満々に(!?)取り組むことのできる やる気に変わってくれるはずですよ。

【ワンポット★クリームパスタ】 1人分
・パスタ 100g
・ベーコン 1枚(1㎝幅にカット)
・玉ねぎ、きのこ 1/4切
(食べやすい大きさにカット)
・プチトマト 1/2パック(半分にカット)
・ブロッコリー 1/8切
(食べやすい大きさにカット)
・ツナ缶 1/2缶(油を切っておく)
・水 300cc~茹で汁が足りなければ水を追加してください。
・塩 小さじ1/2
・コンソメ 1個(大さじ1)
・オリーブ油 大さじ1
・牛乳 200cc
・ミックスチーズ 大さじ2位~適量
・パセリ(乾燥OK) 適量
①フライパンにオリーブ油を入れて、ベーコン・玉ねぎやきのこ・トマトを軽く炒める。
②水を300cc加え、沸騰したら塩とコンソメを加えて、パスタを半分に折って入れる。
中火で時々混ぜながら、パッケージの茹で時間を参考にして煮込む。
③パスタの茹で上がる3分前に、ブロッコリーとツナを加え、茹で上がる1分前に牛乳&チーズを加えてできあがり!
④お皿に盛り付けて、パセリを振りかけます。
★冷蔵庫の余り物を何でも使っても、充分に美味しいパスタです。
★今回は、ツナも入れて、頭の回転が良くなる脳活メニューに早変わりさせました~♪
バランス良く食べよう!
落ち着きを見せない“コロナウィルス”!
恐ろしいくらいにガラッと生活が変わってしまいました。TVでは、先の見えないような報道ばかりで、気が滅入ってしまいそうな毎日です。そんな日々に負けないためにも、ひとりひとりが免疫力を落とさないように毎日の食事に目を向けてみませんか。どうせ同じ食べないといけない食事です。ちょっとだけ‘バランスの良い食事’の事を意識するだけでも免疫力強化につながると思います。でも、毎日の食事で栄養素のことをイチイチ考えるなんて、面倒くさくてできませんよね。献立でいろいろな品数を作って‘バランス良く’も大切ですが、時短が勝負の日々の食事です。ひとつの料理でも栄養のバランスが摂れる方法を考えてみませんか。
そのひとつの方法が、“五色の食材を寄せ集めて作ってみる!五色の食材をひとつの料理の中に取り入れて作ってみる!”というもの。これは、『色彩フードセラピー』というもので、「五色」とは、「赤・白・黒・黄(茶)・緑」の組み合わせで、中国陰陽五行説から来る薬膳料理にも用いられる考え方に基づくものです。住まいやインテリアに取り入れられたりする“色彩セラピー”と相まって、『色彩フードセラピー』として欧米で注目を集めている考え方です。
「五色」の色とは、見た目の色で判断して良いのですが、
赤色:人参、トマト、赤パプリカ、牛肉etc.
白色:白米、もやし、玉ねぎ、大根、じゃがいも、カリフラワー、レンコン、豆腐etc.
黒色:昆布、わかめ、ひじき、黒ゴマ、皮付き茄子etc.
黄色:豆類、南瓜、コーン、レモン、さつまいも、卵の黄身、きのこ類、ツナetc.
緑色:ほうれん草等緑黄色野菜、ブロッコリー、ピーマン、キャベツetc.
こんな感じで、ザックリと選んでいきます。そうして、組み合わせて取り入れていくと、不思議と栄養が摂れるそうなのです。ストレスに脳が反応することで、カラダにも影響を与えるので、“フードセラピー”はいろんなストレスを軽減させるためにも“バランス良く食べることで、脳を健康に保つ!”と考えて、そこに五色の食材の栄養を取り入れます。これが、『色彩フードセラピー』です。お子様もご家族の方もなかなか外に出られない状況が続きますから、こんな時期を利用しつつ、冷蔵庫の中の‘五色の食材探し’をゲーム感覚にして気分転換を計りながら、ランチや夕飯をバランスの良い食事にしてみませんか~♪
そこで、今回はお子様ともワイワイ楽しめそうなランチメニューにもぴったり!の【五色★クリスピーピザ(!?)】はいかがでしょうか。簡単に餃子の皮で作りますよ~♪

【五色★クリスピーピザ(!?)】
・餃子の皮 お好みの数量
(1パック=約30枚)
・ピザソース(ケチャップでもOK!)
・マヨネーズ
・とろけるチーズ(シュレッドチーズ)
・オリーブ油
<具材>
・ベーコン、ソーセージ、ツナ、しらす干し、ゆで卵、プチトマト(赤・黄)、ピーマン、
ブロッコリー、大葉、赤黄パプリカ、オニオンスライス、粒コーン、黒ゴマ、青海苔etc.
①具材の野菜等は薄切りにする。ツナ、粒コーンは水分を切っておく。
②ホットプレートにオリーブ油を薄く敷いて、餃子の皮を並べる。(フライパンでもOK!)
③②の餃子の皮にソースやマヨネーズを塗り、各々お好みの具材をのせてチーズを散らす。
*しらす干しは、マヨネーズ+チーズが美味しいですよ♪
④ホットプレート160℃で、蓋をして5分位焼く。野菜がしんなりしてチーズが溶けてきたら蓋を外して、餃子の皮がパリッとなるまで焼いたらできあがり!
*今回は、具材も具材のグラム数もお好みで準備してみてください。
『塾デリカ』★レシピ特集
各教室で、『塾デリカ』のお話をさせていただきながら、プチデリカを召し上がっていただいた“塾デリカ試食会”!コロナウイルスの影響で、試食会を開催できない教室がいくつかありました。試食会に来ていただいた保護者の方から、「家でも食べたい!」や「デリカのレシピを教えて!?」のお声をいただきましたし、試食会を開催できず、プチデリカを召し上がっていただけなかった方々のために、ご要望にもお応えしつつ、今回は『塾デリカ』の人気メニューの中でも簡単にできるレシピを(少しですが)特集しちゃいます。もちろん、毎回『塾デリカ』を提供してくださっているハーストーリィハウスさんにお聞きして、教えていただいたレシピです。やさしいお味の『塾デリカ』を、ご家庭でもたっぷりと作って、召し上がってみませんか(!?)
まずは、お母様方からのリクエストメニュー!№1、【ドライカレー】から。
プチデリカとして、召し上がっていただいているものですが、「たっぷりと食べたい!」のお声をもとに、教えていただきました。

【噂の!★ドライカレー】 4人分
・合挽ミンチ 200g
・玉ねぎ・人参 各200g(みじん切り)
・なす Ⅰ/2本 (みじん切り)
・パプリカ赤・黄 各1/4個(みじん切り)
・生姜・ニンニク 各1片(みじん切り)
・カットトマト缶 200g~1缶
・塩こしょう 少々
・ケチャップ 50cc(Ⅰ/4カップ)
・コスモカレー(中辛) 70g(約Ⅰ/2袋)
①フライパンに油をひき、生姜・ニンニクを炒めて、香りが出てきたら、ミンチとみじん切りにした野菜を入れて、塩こしょうをして炒める。(しんなりするまで、炒めます)
②①にカットトマト缶、ケチャップ、コスモカレーを入れて、後は煮込むだけ!
*普通のカレールーでもOK!2~3かけを細かく砕いて、使います。この場合は、煮込む時に、適量の水分(約30~50cc)を入れて、お好みの味に調整してください。焦げずに美味しくできますよ。ご家庭のお味でどうぞ!
毎年塾デリカの中でも、お子様方に人気のある『のっけデリカ』のひとつ!【豚肉ののっけ丼】の豚肉の味付けレシピを特別に教えていただきました。
たっぷり生姜がポイントですよ~♪

【豚肉ののっけごはん】 2~3人分
・豚バラ肉 500g
・炒め油 適量
- ざらめ 100cc ~無い場合は少しでもコクの出る三温糖・キビ砂糖等がいいかも。
- しょうゆ 75cc
- 酒 40cc
- 水 125cc
・生姜 100g~(すりおろし):スーパーで売っている1袋分を全部使います。
①豚肉を炒め、ザルにキッチンペーパーをひいたところに上げて油をしっかり切ります。
②●の調味料を鍋に入れ、グラグラと少しトロミが出るまで煮詰め、そこに生姜と①の豚肉を入れて、サッと火を通してできあがり!
*ごはんの上に茹で野菜等をのせて豚肉をのせ、お好みでマヨネーズの線引きトッピングで召し上がれ~♪
そして、今回の『応援デリカ』の一品として入っていた、【春野菜のゴマ和え】。

お母様方ととても美味しくて、「家でもぜひ作りたいので、レシピが知りたい」というお話で盛り上がった副菜で、早速、ハーストーリィハウスさんに教えていただきましたよ。
旬の春野菜をたっぷりと使って、ご家庭でもぜひ作ってみてください。
【春野菜のゴマ和え】 3~4人分
・春キャベツ 1/4カット
・ほうれん草 1袋
・人参 小1本
- 砂糖:醤油:みりん:酒=1:1:1:1 各大さじ2~3
- だしの素 大さじ1/2
・白すり胡麻 大さじ5
①各野菜を塩ゆでし、しっかり水分を切る。
②●を合わせて、一度沸騰させて、乾煎りをした胡麻とともに、①の野菜と混ぜ合わせる。
*『塾デリカ』では、和風本枯れだしと万能タレを少し入れているそうです。
*旬の春野菜で、冷蔵庫にある野菜で、何でもゴマ和えにできそうですね!
祝10周年!塾デリカ★試食会
今年度も始まりました【塾デリカ試食会】!新年度への移行に伴い、「塾デリカ」を知っていただきたくて毎年開催させていただいています。
19時前といったお腹のすいた夕飯時に塾で食べるお弁当=‘塾弁’から端を発した「塾デリカ」。そんな「塾デリカ」も、なんと10周年!を迎えました。愛情たっぷりに作っていただいている「塾デリカ」を、たくさんの先輩たちに利用していただいている「塾デリカ」を、新5年生、そして新6年生のお弁当が必要となる生徒の皆さんと保護者の方々にご試食いただく【塾デリカ試食会】です。

「デリカ」とは、ドイツ語で‘美味しい!’という意味!
「塾デリカ」は、“一汁三菜”を基本としたお食事パターンのお弁当で、安心・安全な国産の食材や無添加に近い天然素材のお出汁と調味料にこだわった、カラダにも頭にも良い献立構成になっています。まさに、【頭とカラダを育む「塾デリカ」】です。“一汁”は、こだわりのある出汁(アゴだしや昆布だし、合わせだし等)で提供している味噌汁やスープで、カラダの芯からホッ!とできる一品です。また、“三菜”は主菜を含めた三品で、毎回12~15品目の食材料から作られており、体力や脳力のパワーアップを目指したお勉強に頑張るお子様方のための、「塾」ならではのこだわりのあるものに仕上がっています。*お野菜が豊富に使われていることは「塾デリカ」ならではの自慢のひとつです!

1日のメニューには、魚or肉がバランス良く組み込まれている「応援デリカ」+みそ汁、丼ぶりタイプの「のっけデリカ」+みそ汁、単品シリーズの「プチ贅沢果物」と「国産鶏肉唐揚げ」の4種類となっています。そして、毎月19日の「塾デリカ」は、「19」=‘塾の日’ということで、私から受験生のお子様に向けてのエール(!?)として、応援スペシャルメニューを提供させていただきます。スペシャルメニューですから、脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、また縁起物や受験に向けてのゲン担ぎのもの等、何が登場するか乞うご期待!です。メニューを見ていただくひとつのお楽しみ~♪にしていただけると嬉しいです。
そこで、今回は特別に、新年度3月メニューに登場する‘19日=塾の日’スペシャルメニューをひと足早くお知らせしましょう!

【キラッキラの宝石BOX】です。一年のはじまりの、3月の「塾デリカ」スペシャルメニューですから、これからの塾デリカに登場しそうなものをたくさん詰めた、食べやすい一口サイズの“手毬寿司”にしてみました。3月は“桃のお節句”でもあったり、何かと明るい春を連想させるようなシーズンですから、かわいらしく“手毬寿司”にして、キラキラと輝く宝石箱をイメージしてみましたよ。キラッキラ!に見えるといいな、そして、みなさんがキラキラ!と輝いてくれますように、と願いを込めました。
お家でも簡単に、“手毬寿司”を作っていただけるように、【簡単★寿司酢】のレシピをご紹介してみます。
【寿司酢】さえできれば、後は炊き立てのごはんに混ぜ合わせ、ラップを使ってキュッと固めに丸く形を整えれば、何をのせても、何を包んでもOK!の“手毬寿司”です~♪
【簡単★寿司酢】 作りやすい分量の2合分です。
・米酢 大さじ4
・砂糖 大さじ3
・塩 小さじ2/3
*お米2合は洗ってザルに上げて水を切り、炊飯器のすし飯の目盛まで水を入れ、昆布(5×10㎝)を1枚のせて炊きます。
①寿司酢は、容器に分量を入れ、レンジに10~20秒(砂糖・塩が溶ける程度)かけて、よく混ぜたらOK!レンジのかけ過ぎに注意です。
*炊き上がったら、昆布を取り出したすし飯が熱いうちに、寿司酢を切り混ぜるようにして合わせます。
元気になる(!?)★チョコレートパワー
この時期、何かと目にすることの多いチョコレート~?目にもココロにもスウィートな幸福感をくれるチョコレート!普段何気無く食べているチョコレートですが、そんなチョコレートには、驚くべき健康効果が続々と報告されていることをご存じですか(!?)最近では、美味しくてカラダにも良い‘健康チョコレート’というようなものもたくさんお目見えしています。

なぜなら、昔々、チョコレートは薬として重宝されていたのだとか!実は、チョコレートに含まれるカカオ成分には、傷の回復を早めたり、免疫細胞を活性化させたりと、健康や美容面にも効果があるようです。元々は「薬」だったチョコレート。そのためか、‘神の食べ物’とされていたそうです。チョコレートって、甘いお菓子のイメージですが、元々はカカオ豆をすり潰した飲み物だったそうで、その歴史は紀元前の古代文明の頃まで遡るのだとか。チョコレートが伝えられたヨーロッパでも「薬」として利用されていた記録書が残っていて、今のチョコレートとはだいぶ違うものだったようです。それをスウィートな現代のようなチョコレートにするため、カカオから抽出される脂質‘カカオバター’をたっぷり加えることと、糖分をたくさん加えることから、高カロリーな食べ物となりました。
そして、チョコレートにはカラダに嬉しい成分がたくさん含まれています。ポリフェノール(抗酸化作用、老化防止)、テオプロミン(大脳を刺激して記憶力、集中力を高めて気力をアップ)、ブドウ糖(脳にとって最も効率のよい栄養)、食物繊維(便通改善、肌荒れ防止=元気な腸に!)、ビタミン・ミネラル(身体を安定させてくれます)など!そして、“免疫調節作用”もあるようです。「疲れた時には、チョコレートが食べたくなる」「チョコレートを食べると落ち着く」などと言われますが本当かもしれませんね。
ということは、【チョコレートは受験生の強~い味方!】になってくれるかもしれません。
<チョコレートのメリット>
★ストレスに強くなる
★チョコレートには集中力・記憶力を高める効果が!
★チョコレートには良質のミネラルが豊富
★チョコレートは体内ですぐにエネルギーにかわる etc.
<チョコレート~オススメの食べ方>
★勉強や仕事の合間に!
★ココロ&カラダが疲れた時。
★健康のために(カカオ比率が高いチョコレートがオススメ!)
★非常食に(持ち運びがしやすく、高エネルギーなので)
★温めると、効果アップ
そこで、冬の時期を健康的に乗り切る二大食材【チョコレート&キウイ】を使って、健康効果がパワーアップする食べ方を紹介してみましょう!
【キウイ】は、冬の時期に栄養満点で美味しくなり、ビタミンCがレモンの4倍、食物繊維がバナナの3倍含まれます。
選ぶ時には、やや平べったいものがいいそうです。幹に近い【キウイ】ほど平べったくなり、栄養たっぷりで美味しいということですよ。
そんな【キウイ】の健康効果をアップする食べ方が、冬に食べたくなる甘いチョコレートと一緒に取ること!
冬を元気に乗り超える効果が期待できるという、【キウイのホットチョコ】です。

【キウイのホットチョコ】
・板チョコ 2枚
・牛乳 大さじ4
・キウイフルーツ 2個
~ゴールドキウイを使ってもOK!
①耐熱ボウルに板チョコを刻んで入れる。(今回はDARSを使ったので、そのままで!)
②①に牛乳を加えて、レンジ600wで40秒加熱する。
③取り出して、よくかき混ぜて、再びレンジ600w40秒加熱して、チョコソースの完成です。
④キウイをしっかり水洗いして、皮付きのまま輪切りにし、耐熱皿にのせてラップをしてレンジ600w40秒加熱する。
*キウイを加熱すると酸味が減り、甘味がアップします!
⑤キウイソースを付けて、お召し上がりください!
キウイやいちごetc.フルーツをチョコソースにつけながら食べるのも、なかなか面白いです。
まさに、お子様が大好きなチョコレートフォンデューです~♪
【節分】の“福豆”のリメイク!
「鬼は外、福は内」!
【節分】の日には、ご家庭で‘豆まき’や‘恵方巻き’を食べたりされましたか。そもそも【節分】とは、「季節の変わり目」という意味の言葉です。旧暦では【立春】は新しい年を迎える大切な節目だったために、昔から豆や米などをまいてお祓いする習慣があったそうです。昔々、季節の変わり目には鬼がやって来て、病気や災いをもたらすと信じられていたようです。豆や米には不思議な力があるとされており、‘豆’を鬼の目である「魔目」にめがけて投げれば、魔が滅する=「魔滅」という意味から、“豆をまく”と鬼を追い払うことができるという由来なのだとか。この由来から、一年の大きな節目に当たる【節分】に豆をまき、その後一年間無病息災に過ごせるよう、歳の数だけ豆を食べると良いという習慣になったということです。そのため、“節分豆”は“福豆”とも呼ばれます!
‘豆まき’の豆の主流は大豆!大豆には、あなどれないほどの健康効果があるのは皆さんもご承知のことと思います。「畑の肉」とも呼ばれることも多い大豆は、たんぱく質が豆類の中で一番多いだけでなく、動物性たんぱく質に非常によく似た性質を持つ、とても優れた栄養食品です。また、お勉強に頑張る子供たちには嬉しい、頭を活性化させる「ブレインフード」でもあるのです。大豆には、脳の働きをサポートし、脳の神経細胞を構成するのを担う<大豆レシチン>が多く含まれていて、脳内でのスムーズな情報伝達を促進することができる働きをしてくれます。
‘豆まき’が終わった後、一年の健康を祈って歳の数だけ“福豆”を食べることには、健康面での裏付けだけでなく、脳活効果もあったのですね。
でも、意外と‘節分’の後、豆が余ったりしていませんか。せっかく、栄養面でも優秀で「ブレインフード」でもある“福豆”ですから、余ってしまった豆を処分するのはもったいない!です。ぜひ、“福豆”をリメイクしてみませんか!
そこで、いくつかお子様にも人気のある、受け入れてもらえそうなリメイクレシピをご紹介してみましょう。案外、普段のお食事にも使えますよ~♪

【大豆&さつま芋の炒り煮】 4人分
・戻した福豆 100g
・さつま芋 80g(小1本)
・ちりめんじゃこ 適量(30g位)
・片栗粉 小さじ2
・油 大さじ2
・青のり 適量
- 醤油 大さじ1 ●砂糖 大さじ1強
- 和風だしの素 小さじ1/2 ●酢 大さじ1/2
①さつま芋はサイコロ状に切り、水にさらした後、水分をしっかり切る。
②ビニール袋に片栗粉を入れ、①と大豆を入れて、振って混ぜ合わせる。
③フライパンに油を入れて、①を炒め揚げにし、さつま芋に火を通す。火通りが悪いようだったら、少量の水を入れて蓋をしながら、炒め煮にする。
その間に、●を合わせておく。
④最後にちりめんじゃこを入れて炒め、合わせておいた●の調味料を入れて、煮絡めたら
完成!青のりをトッピングしてできあがりです。
★戻した福豆は、節分豆の“炒り大豆”に熱湯をヒタヒタになるくらいに回しかけて、約30分ふやかしたものです。

【福豆★ポークビーンズ】 4人分
・戻した福豆 200g
・豚ミンチ 100g
・じゃがいも 小2個位
・人参 小1/2本
・玉ねぎ 1/2個
・グリーンピース 少量
・油 小さじ2
・コンソメ 大さじ2.5
・ホールトマト 100g
- ケチャップ 大さじ1.5 ●砂糖 小さじ1 ●塩こしょう 適量
①じゃがいも、人参、玉ねぎは、食べやすい大きさに切る。
②鍋に油を入れ、ミンチと①、福豆を炒めて、ヒタヒタの水とコンソメを入れて煮る。
③しばらく煮たら、ホールトマトを入れ、●を入れて調味する。
④味をみて、グリーンピースを入れたらできあがり!(グリーンピースは色取りです)

【福豆の炊き込みごはん】 2合分
・米 2合
・節分豆 20g(大さじ2~3)
~薄皮を取っておきます。
・塩昆布 15g(一握り)
・人参 Ⅰ/3本(千切り)
・しめじ Ⅰ/4パック(石づきを取ってほぐす)
・油揚げ 1/3枚(油抜きして細切り)
・枝豆 大さじ2~3(むき身)
- 酒・みりん 各大さじ1 ●醤油 大さじ1.5 ●和風だし 小さじ1
①米をといて、炊飯器に米と水を入れ、●の調味料を入れたら全体を混ぜる。
②人参、油揚げ、しめじ、節分豆、塩昆布を①の上にのせたら、いつもどおりにスイッチON!
③炊き上がったら、枝豆のむき身を上に散らして、10分程度蒸らしたらできあがり!
体調万全!免疫力UPの食べ合わせ
いよいよ受験本番の時期がやって来ました。広島県では、早い時期からインフルエンザの流行期に突入しています。皆様、体調は万全でしょうか!“体調&コンディションだけは万全で本番を迎えさせたい!”そんなお母様方の心の声を代弁しつつ、免疫力がUPする【風邪の季節に覚えておきたい食べ合わせ法】をご紹介します。食べ合わせとは、1つ1つの持つ食材の栄養が他の食材と食べ合わされることで、栄養素に相乗効果を持たせてくれること!サンマに大根おろしは、消化吸収を助けることで、サンマの持つ栄養DHA(ドコサヘキサエン酸)という脂肪酸が脳の活性化をとてもよくしてくれるというものだったり、スタミナ料理として知られるレバニラ炒めはニラの成分がレバーに含まれるビタミンB群の吸収を高めるので、体内に長く留まることができ、疲労回復にとても効果があるという、理にかなっている事なのです。この時期、ひたすら頑張っているお子様のためにも、風邪になんか負けさせるわけにはいきませんから、ぜひとも免疫力UPの食べ合わせが必須です。
★ホウレン草+生姜
生姜の辛味成分(ショウガオールとシンゲロン)は発汗作用や血行促進の効果があり、冷えの改善にバッチリ!抗酸化作用の高いβカロテンやビタミンCの豊富なホウレン草と組み合わせると風邪予防の効果が格段にアップします。
★鮭+トマト
鮭は魚にはあまり含まれていないビタミンB群がすべて含まれている食材で、疲労回復や貧血予防にもよいとされています。これに抗酸化作用の高いトマト(リコピン)と組み合わせることで細胞から元気にしてくれます。
★ブロッコリー+ホタテ
ビタミンCとβカロテンを豊富に含むブロッコリーは抗酸化作用が高く、細胞を強くする良質なたんぱく質のホタテと組みわせることで免疫力がアップし、風邪の予防になります。
体温が下がることは免疫力もダウンすることです。これらの免疫力を高める食材を使ってスープにして体を温めたり、季節柄、温サラダやパスタにあわせたりと、食べ物から風邪を防いでいきましょう。これらの食べ合わせの中から、お子様たちを元気づけられそうなレシピをご紹介してみます。

【鮭のトマトクリームパスタ】 2人分
・鮭(切り身) 2枚
・酒 小さじ2
・玉ねぎ(薄切り) Ⅰ/2個
・しめじ(小房に分け
る) 適量
・トマトの水煮缶
1カップ
・牛乳 1カップ
・パルメザンチーズ 大さじ2
・オリーブ油 大さじ1
・にんにく 1片(みじん切り)
・ブイヨン 1個
・塩こしょう 少々
・パスタ(フェットチーネ使用) 180g位
・イタリアンパセリ 適量~ほうれん草でもOK!です。
- 耐熱皿に鮭を入れ、酒を振り入れてラップをかけ、レンジ500wで2分~くらいかける。レンジ後、皮と骨をとっておく。
- パスタを茹でている間にソースを作る。
- フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて弱火で炒め、香りがしてきたら、玉ねぎとしめじを炒めて鮭も軽く炒める。トマト缶とブイヨン、チーズを入れ、軽く煮る。(この時、お好みで水を+100ccしてもOK!)火を止めて、生クリームを混ぜ、クレイジーソルトで味を整える。
- パスタが茹で上がったら、湯を切ってソースに混ぜ、お皿に盛りつけてイタリアンパセリをトッピングしてできあがり!
*濃厚なクリームソースには平たいパスタ(フェットチーネ)が良く合います。表示されている茹で時間より1分短く茹であげるのがポイントです。
*ストレス?!から食欲のない我が家の受験生には食べやすかったようで好評でした~♪

【ほうれん草&生姜の中華スープ】 2人分
・ほうれん草 1/3パック
・ブロッコリー 1/3株
・プチトマト 5~6個
・生姜(千切り) 1片
・溶き卵 1個分
・ごま油 大さじ1
・水 500cc
・中華スープの素 小さじ2~
・塩、醤油 少々(お好みで)
①鍋にごま油、生姜を入れて香りが出るまで炒め、ほうれん草・ブロッコリーを入れてサッと炒めたら、水と中華スープの素を入れて煮たたせて、カットしてトマトを入れてさらに煮る。
②塩、醤油で味付けしてら、溶き卵を流し入れて、火が通ればOK!

【ホタテ&ブロッコリーのガリバタ炒め】 2人分
・ホタテ 200g(約1パック)
・ブロッコリー&カリフラワー 各1/2株
(小房に切り分けて茹でておきます)
・ガーリックオイル 大さじ1
・クレイジーソルト 適量
・バター 大さじ1(10g)
・しょうゆ(お好みで) 少々
- フライパンにガーリックオイルを入れ、ホタテ、茹でたブロッコリーとカリフラワーを炒めてクレイジーソルトで味付け。仕上げに、バターを入れて馴染んだらOK!
*カリフラワーがお好みでないお子様もこれなら食べてくれます。カリフラワーも抗酸化作用が強いので使いました~♪
【合格ひじき】の“合格弁当”!
白石学習院の専属食育インストラクターとなって、早十数年~♪
私の原点でもある“お子様が食べやすく、カラダにやさしくて、頑張る毎日を応援できる食”として、初めて「食育イベント」をした際に、紹介した【合格ひじき】!

基礎案となっているのが、今でこそ、広島のデパートや通販でもお見かけするようになった『十二堂えとやの“梅の実ひじき”』です。
ご存じですか(!?)昨今は、インターネットhttp://www.1210-etoya.com でも注文ができるようになっていて、有名になり過ぎて、驚きです!
福岡の合格祈願の神様で有名な「太宰府天満宮」に位置する『十二堂えとや』のふりかけで、大宰府の名産品のカリカリ梅の実が入ったあっさりとしたひじきがメインのふりかけです。
昨年は、令和元年ということもあり、新元号「令和」の縁の地でもある、万葉集=梅花の歌の梅でも一役かっているようです。
我が家の子供たちの受験期に「太宰府天満宮」のお守りと一緒に“梅の実ひじき”をいただいたことがきっかけの縁起物で、【合格ひじき】とは、ひじきを薄味に煮たものに、カリカリ梅をはじめ、五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせた、各自各々が思い思いに作る【ひじきのウエットタイプのふりかけ】です。
熱々のごはんにのせていただくと、とっても美味しいんですよ♪
薄味に煮たひじきの中に、五色になるような食材を取り入れる!
五色の食材とは「赤・白・黄・緑・黒」色の見た目の判断でOK!のすべての食材が対象です。食材によって、栄養効果は多少変わってきますが、五色になるように食材をなんでも取り入れて作ると、不思議と必要な栄養素がほぼバランスよく摂れるというもので、塾デリカやお弁当作り、日々の食事作りにも率先して取り入れつつ、提案しているひとつの方法です。
五色の食材の栄養素はもちろんですが、五色の色のパワーもじつは侮れません。
*赤色の効用として、活力を与えてバイタリティーを高めます。血となり肉となる食材が豊富です。
*白色の効用として、心を落ち着かせます。“カラダの素となる”エネルギーを作り出す食材が豊富です。~ごはんのイメージですね!
*黄色の効用として、脳を刺激して希望につなげるパワーになります。頭&カラダを働かせる原動力となります。
*緑色の効用として、ストレスを和らげてココロの安定効果があります。カラダの調子を整える、野菜や果物に多いイメージです。
*黒色の効用として、安心感や強さ、自信を与えます。カラダ&頭の健康維持に必要な食材が豊富です。
専門的に立証されていることらしいのですが、専門的な事を考えながら食事を作る毎日は疲れてしまいますので、ザックリと大まかに捉えていくのが私流!
これからいよいよ試験本番を迎え、頑張るお子様にとってはとても大切な時期となります。
まずは、お母様特製の『我が家の“合格ひじき”』を手作りして、食事に塾弁に腹ごしらえetc.に取り入れて見ませんか!

【お手製☆合格ひじき】
・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で100g位
・だし汁 120cc ~ひじきがヒタヒタに浸かる位です。(水120cc+和風だしの素 小さじ1)
・醤油 大さじ2
・砂糖 大さじ1
・みりん 大さじ3
・昆布茶 小さじ2~3(*隠し味になりますよ!)
- トッピング
赤:カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老など
白:白ゴマ・タラの身・ちりめん・かつお節・大豆の水煮など
黄:柚子の皮(細く千切りしたもの)・炒り卵など
緑:あおさ海苔・いんげん・枝豆・パセリなど
黒:黒ゴマ・刻みのりなど
①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水で戻します。(約10分~)約8~9倍に増量します。
②①の水切りをして鍋に入れ、だし汁と調味料をすべて混ぜ合わせて煮ていきます。
汁気が無くなるまで、時々混ぜながら煮たら【合格ひじき】の素=“ひじき”のできあがり!
★少し乾煎りするようにしっかりと水分をとばすことがポイントですよ♪
★お好みのトッピングを適量混ぜ入れて、【お手製☆合格ひじき】のできあがりです。

せっかく作った【合格ひじき】のアレンジバージョンとして、お母様特製の“合格弁当”なんて、いかがでしょう。
卵やお肉と混ぜ合わせて焼いたり、野菜と炒めたり合わせたり、ごはんと混ぜたり炒めたりしてチャーハンやオムライスにしたり~~と、縁起物(!?)【合格ひじき】を使った “合格弁当”に活用してみてください!
ちなみに、我が家のアレンジバージョンTOP1のご紹介です。

*<豚肉の落とし揚げ>:豚こま肉に塩こしょうで下味を付け、少量の薄力粉と水で衣を作った中に【合格ひじき】と豚こま肉を入れて、混ぜ合わせ、食べやすい大きさにスプーン等ですくいながら、揚げ油の中に落として4~5分位揚げたら完成です。