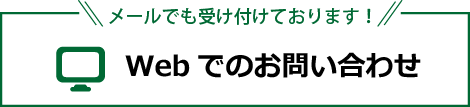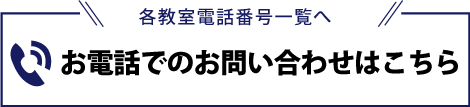満腹日和
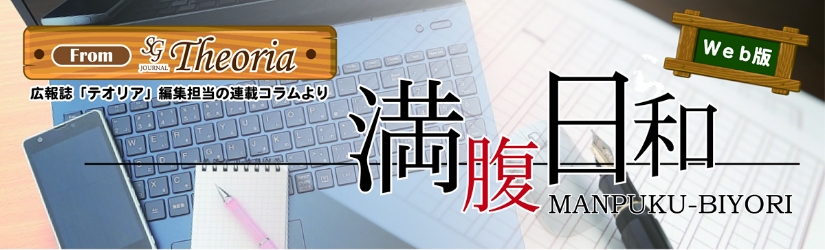
満腹日和 Vol.3
季節が変わった実感のないまま、今年の夏は終わりました。もうしばらく続きそうな暑さの延長戦の中に、少しでも秋を感じたい気分です。
今年の8月は戦後80年という節目の年だったこと、また戦争体験の継承という意味でもきちんと報道すべきという理由もあり、例年以上に太平洋戦争を扱ったメディアが多かったように思います。先の大戦の結果が軍民合わせて300万の犠牲であり、広島・長崎の悲劇であり、焦土と化して衰亡の淵に立たされた国家であるとすれば、どこで道を間違えたのか、どこで引き返すべきだったのか、そんなことを思いながら見ていました。一方で「1945年」は終戦の年であると同時に、私たちの「今」に続く起点でもあると思えば、「1945年まで」の検証と同時に、「1945年から」の検証も同じように必要なのではないかという気もしました。
8月9日、長崎平和祈念式典で小学生が合唱したのは福山雅治さんの「クスノキ」という歌でした。被爆し大きな傷を負ったにもかかわらず、今も当時の場所に立ち続ける山王神社の被爆樹木(大クス)を題材に、「すべての生命が等しく生きられる世界」への願い、「生命の尊さ、逞しさ」という普遍的なメッセージが描かれた楽曲です。それは怒りでもなく悲しみでもない、静謐な祈りにも似た「心の声」として私たちにゆっくりと染みわたってきます。
我が魂はこの土に根差し
決して朽ちずに 決して倒れずに
我はこの丘 この丘で生きる
幾百年越え 時代の風に吹かれ
片足鳥居と共に 人々の営みを
歓びを かなしみを ただ見届けて
我が魂は奪われはしない
この身折られど この身焼かれども
涼風も 爆風も 五月雨も 黒い雨も
ただ浴びて ただ受けて ただ空を目指し
我が魂は この土に根差し
葉音で歌う 生命の叫びを
戦後80年、昭和100年。その連続した歩みの上に今私たちは生きています。改めてその意味を深く考えたい、そんな気になる今年の夏でした。夏が明けた翌日、2025年9月1日は白石学習院の創立記念日。こちらも50周年の節目を迎えました。夏の初めに思いがけない悲しみも抱えつつ、迎えた誕生日。その連続した歩みの上に、今私たちは生きています。
満腹日和 Vol.2
6月後半、深夜の雷雨に耳をそばだてていたら、その数日後に梅雨は明けてしまいました。いや、ちょっとまだ心の準備が、と言いたくなるような中国地方に観測史上最も早く訪れた不意打ちの夏です。
1993年。政治の世界ではいわゆる「55年体制」が崩れ、日本は連立政権の時代に入りました。Jリーグが開幕し、日本中がブームに沸き立ちました。一方でバブル後の大型不況は深刻化し、「失われた30年」の入口に立っていたことを後に知ることになります。そしてその年の夏は梅雨が長引き、極端に日照時間が少なくなったことで記録的な冷夏となりました。これが原因となってこの年の米の作況指数は74(「著しい不良」の場合でも90)となり、全国的な米不足が発生して、店頭から米が消えるという事態が発生しました。このとき政府はタイや中国、アメリカから米を緊急輸入して供給不足への対応を図りました。ところがタイから輸入された米が日本の米とは種類の違うインディカ米だったことから消費者には非常に不人気で、新聞やテレビではタイ米の調理法や工夫について連日報道されました。当時高校生だった編集担当も、普段見かけない長細く粘り気の少ないお米を珍しく思ったことを覚えています。
この「平成の米騒動」に限らず、もともと熱帯の作物である稲にとって寒さは最大の敵なのですが、気候変動によって実は近年は暑さ対策に主眼が置かれているそうです。そして今年の記録的な早い梅雨明けは作物にどんな影響を与えるのか、そこに不安を感じます。
物価高が人々の生活を圧迫する中で、原因こそ違いますが、32年前と同じようにまた米不足が大きく報道されました。価格の高騰、備蓄米の放出、安定供給と適正価格のバランス、そして日本の農業のあり方。日本の主食であるがゆえ、どうしても注目を浴びてしまいます。
大陸から約3000年前に伝来した稲作は、それまで狩猟中心だった日本の社会を大きく変えました。米作りを基盤とした農村共同体の形成と「富」の蓄積は古代国家の成立の原動力であり、江戸時代に至るまで統治機構の存立基盤でもありました。一方で、稲作を行うための土地をめぐる争いが生まれ、その後も農地=領土の奪い合いは絶えることなく続きました。こうしてみると、稲作こそ生活と経済の基本であり、日本の古代史~近世史そのものだといってよいのではないでしょうか。
いつもの年よりも早く訪れた今年の夏。特に受験生にとっては重要な「鍛えの夏」です。長く、暑い夏を充実したものにしていってほしいと思います。きっとその先には、豊かな実りがあると信じて。
満腹日和 Vol.1
万国博覧会には180年近くの歴史があり、その起源は19世紀半ばにまで遡ります。
世界初の万博は1851年、産業革命が進むイギリス・ロンドンで開催されました。
鉄とガラスで造られた「水晶宮」に集められた世界各国の文物は、「世界の工場」と呼ばれたイギリスの工業力、技術力を示すものでした。
この博覧会の成功を受け、西欧諸国もそれに倣って万博を開催するようになります。
花の都・パリの象徴であるエッフェル塔は1889年のパリ万博に合わせて建設され、1933年のアメリカ・シカゴ万博ではドイツが巨大飛行船ツェッペリン号を飛行させて世界に航空技術を見せつけました。
国力を誇示する場であった万博はその後、開催ごとに設定されたテーマ性を重視する形態へと変化します。
1970年アジア初の開催となった大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」。
過去最多の6421万人が会場を訪れました。
1964年の東京オリンピックとあわせ、戦後日本の復興、高度経済成長期の象徴として記憶され、令和の時代の子どもたちも歴史の教科書で学んでいます。
かくいう編集担当は大阪万博から少し後に生まれた世代。
当時の様子を残した映像や写真、現在も残る万博公園と太陽の塔、そして実際に会場を訪れた祖父や母の話を通じて、その昂奮を知りました。
そして時代は2025年。大阪は再び万博の地となりました。
その賑わいぶりとともに、欠点や不備を指摘する報道も散見され、成功を危惧する声を聞かれます。
ただし多額の国費を傾けて「モノ」をつくり、来場者数や経済効果という指標だけで成功を語るのはテレビというメディアを視聴率で評価するのと似た前時代的発想のように思えてなりません。
SNSの発達によって、誰もが発信できる時代です。
ここ数年、大きな自然災害や事件や選挙などで、SNSの影響力の大きさを感じる機会は何度もありました。閉幕の10月までの半年間、万博に訪れた人、体感した人、働いた人、つくった人、様々な立場の人がメッセージを発信し、動画や写真をシェアし、そしてそれが拡散されていくことでしょう。
それらの情報のうねりが、社会の人々と万博との距離感を変えていきます。
55年前、祖父はひどい混雑で「月の石」も「人間洗濯機」もよく見られなかったけれど、戦後の困難な時代を乗り越えた多幸感を万博の中に見たと語り、学生だった母は輝くようなパビリオンの数々に明るい未来を感じたと言っています。
参加国数や来場者数もさることながら、55年前の記憶を語る人がいて、それを受け取る人がいて、万博を知らない世代も万博を知っていること、それもひとつの大きな成功。2025年の万博が55年後も「やってよかったね」と言われるものであってほしいと思うのです。