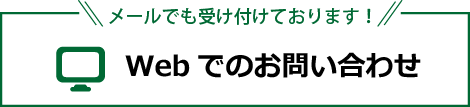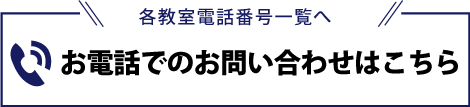満腹日和 Vol.2
6月後半、深夜の雷雨に耳をそばだてていたら、その数日後に梅雨は明けてしまいました。いや、ちょっとまだ心の準備が、と言いたくなるような中国地方に観測史上最も早く訪れた不意打ちの夏です。
1993年。政治の世界ではいわゆる「55年体制」が崩れ、日本は連立政権の時代に入りました。Jリーグが開幕し、日本中がブームに沸き立ちました。一方でバブル後の大型不況は深刻化し、「失われた30年」の入口に立っていたことを後に知ることになります。そしてその年の夏は梅雨が長引き、極端に日照時間が少なくなったことで記録的な冷夏となりました。これが原因となってこの年の米の作況指数は74(「著しい不良」の場合でも90)となり、全国的な米不足が発生して、店頭から米が消えるという事態が発生しました。このとき政府はタイや中国、アメリカから米を緊急輸入して供給不足への対応を図りました。ところがタイから輸入された米が日本の米とは種類の違うインディカ米だったことから消費者には非常に不人気で、新聞やテレビではタイ米の調理法や工夫について連日報道されました。当時高校生だった編集担当も、普段見かけない長細く粘り気の少ないお米を珍しく思ったことを覚えています。
この「平成の米騒動」に限らず、もともと熱帯の作物である稲にとって寒さは最大の敵なのですが、気候変動によって実は近年は暑さ対策に主眼が置かれているそうです。そして今年の記録的な早い梅雨明けは作物にどんな影響を与えるのか、そこに不安を感じます。
物価高が人々の生活を圧迫する中で、原因こそ違いますが、32年前と同じようにまた米不足が大きく報道されました。価格の高騰、備蓄米の放出、安定供給と適正価格のバランス、そして日本の農業のあり方。日本の主食であるがゆえ、どうしても注目を浴びてしまいます。
大陸から約3000年前に伝来した稲作は、それまで狩猟中心だった日本の社会を大きく変えました。米作りを基盤とした農村共同体の形成と「富」の蓄積は古代国家の成立の原動力であり、江戸時代に至るまで統治機構の存立基盤でもありました。一方で、稲作を行うための土地をめぐる争いが生まれ、その後も農地=領土の奪い合いは絶えることなく続きました。こうしてみると、稲作こそ生活と経済の基本であり、日本の古代史~近世史そのものだといってよいのではないでしょうか。
いつもの年よりも早く訪れた今年の夏。特に受験生にとっては重要な「鍛えの夏」です。長く、暑い夏を充実したものにしていってほしいと思います。きっとその先には、豊かな実りがあると信じて。