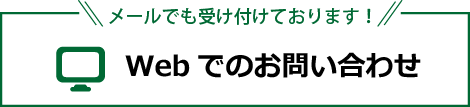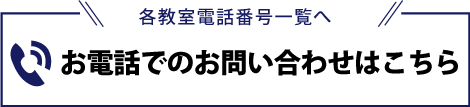満腹日和 Vol.1
万国博覧会には180年近くの歴史があり、その起源は19世紀半ばにまで遡ります。
世界初の万博は1851年、産業革命が進むイギリス・ロンドンで開催されました。
鉄とガラスで造られた「水晶宮」に集められた世界各国の文物は、「世界の工場」と呼ばれたイギリスの工業力、技術力を示すものでした。
この博覧会の成功を受け、西欧諸国もそれに倣って万博を開催するようになります。
花の都・パリの象徴であるエッフェル塔は1889年のパリ万博に合わせて建設され、1933年のアメリカ・シカゴ万博ではドイツが巨大飛行船ツェッペリン号を飛行させて世界に航空技術を見せつけました。
国力を誇示する場であった万博はその後、開催ごとに設定されたテーマ性を重視する形態へと変化します。
1970年アジア初の開催となった大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」。
過去最多の6421万人が会場を訪れました。
1964年の東京オリンピックとあわせ、戦後日本の復興、高度経済成長期の象徴として記憶され、令和の時代の子どもたちも歴史の教科書で学んでいます。
かくいう編集担当は大阪万博から少し後に生まれた世代。
当時の様子を残した映像や写真、現在も残る万博公園と太陽の塔、そして実際に会場を訪れた祖父や母の話を通じて、その昂奮を知りました。
そして時代は2025年。大阪は再び万博の地となりました。
その賑わいぶりとともに、欠点や不備を指摘する報道も散見され、成功を危惧する声を聞かれます。
ただし多額の国費を傾けて「モノ」をつくり、来場者数や経済効果という指標だけで成功を語るのはテレビというメディアを視聴率で評価するのと似た前時代的発想のように思えてなりません。
SNSの発達によって、誰もが発信できる時代です。
ここ数年、大きな自然災害や事件や選挙などで、SNSの影響力の大きさを感じる機会は何度もありました。閉幕の10月までの半年間、万博に訪れた人、体感した人、働いた人、つくった人、様々な立場の人がメッセージを発信し、動画や写真をシェアし、そしてそれが拡散されていくことでしょう。
それらの情報のうねりが、社会の人々と万博との距離感を変えていきます。
55年前、祖父はひどい混雑で「月の石」も「人間洗濯機」もよく見られなかったけれど、戦後の困難な時代を乗り越えた多幸感を万博の中に見たと語り、学生だった母は輝くようなパビリオンの数々に明るい未来を感じたと言っています。
参加国数や来場者数もさることながら、55年前の記憶を語る人がいて、それを受け取る人がいて、万博を知らない世代も万博を知っていること、それもひとつの大きな成功。2025年の万博が55年後も「やってよかったね」と言われるものであってほしいと思うのです。